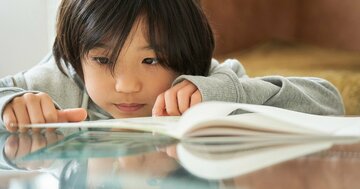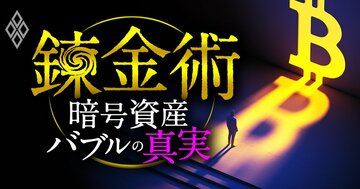「頑張れ」はプレッシャーになる
「いい内容にするように」と伝える
大切なことは精一杯やる、力を出しきることですから、よく話すのは「いい内容にするように」です。
「頑張れ」と言ってしまうと本人はもう十分頑張っていてプレッシャーに感じてしまうかもしれないし、負けた時に「頑張れなかったのか」と思ってしまうかもしれません。でも「いい内容」というのは、自分の力を出しきったという意味ですから、結果が負けであってもできること。勝つ・負けるは二の次なのです。
もっとわかりやすく、「あとから振り返った時にいい経験になるはずだから、悔いのないように全力で戦うように」と言うこともあります。「頑張れ」「勝て」などの言葉を発せず、「負けたら終わり」というような状況に追い込まない。そして本人の力を発揮させる。これが大切だと思います。
実力が互角なら
前向きな気持ちの人が勝つ
ただ中には、プレッシャーをかけることでそれがモチベーションにつながる子、プレッシャーがほぼなく、大一番でも平常心で戦える藤井七冠のような棋士もいます。彼は例外です。私自身は師匠・(故)板谷進九段からまだまだ弱い時期に「心配するな。お前はいつか必ずプロになる」と言われたことが励みになりました。
そして強くなってからは「奨励会というのは駆け抜けるところで、長くいるもんじゃない」と言われ、“将来は棋士になる。仲間として見られている”気になり、自信を持てた面があります。
実は将棋の世界で自信を持つことは、とても大事です。「これだけ勉強したんだから合格するはずだ」というように、できれば根拠のある自信であったほうがいいですが、たとえ根拠がなくても気持ちは前向きであることが重要。
人対人の勝負ですから、いわゆるオーラといいますか、やる気に満ちた強い気を発している人がいる一方で、自信がない、調子が悪そうな気を発している人がいます。その気持ちの強さが指し手に現れるのでしょう。
実力が互角であると、最後は強い気の人、前向きな気持ちの人が勝ちます。
先ほど2割未満しか棋士になれないと述べましたが、そういう環境で「でも、自分は棋士になるんだ」というような熱い気持ちが必要なんですね。技術(実力)はもちろん大事なのですが、自信がないとその先で技術がいかされない。自信と技術は両輪で、両方ないと勝てないのです。
だからなるべくいいところを見つけて、自信をもたせる――それは一般的な子どもたちへの対応に置き換えても大事だと思います。
親のどんな言葉よりも
ライバルの存在が火をつける
また子どもの才能を伸ばす観点では、「ライバルの存在」が大切です。私自身、12歳で奨励会に入り、14歳で一才年下に完敗して、とても悔しい思いをしたことが伸びるきっかけになりました。
それまでは奨励会で私がほぼ最年少だったため、負けてもそこまでではなかったのです。初めて年下の子に負けて、それはもう悔しかった。親にどんな言葉をかけられるより、ライバルの存在は子どもにとって響きます。
だから親として「ライバルがいない大会のほうに、子どもを出場させる」というのは、できればしないほうがいいですね(笑)。その大会の優勝が最終目標ならいいのですが、先を見据えるならライバルを避けるのは、あまり良くないと思います。
次回は、「才能をつぶさないために絶対にしないこと」をお伝えしましょう。
◆◆◆
>>【第2回】「子どもの才能を「つぶす親」と「伸ばす親」の決定的な違いとは?【藤井聡太の師匠・杉本八段が明かす】」は10月17日(金)に配信予定です
第2回は「才能が伸びる子」と「伸びない子」の違い、子どもの才能をつぶさないために大人はどう接すればいいのかを聞きました。周囲の大人が全面協力しているつもりでいて、有望な子の足を引っ張っている例はすごくよくある、と言います。