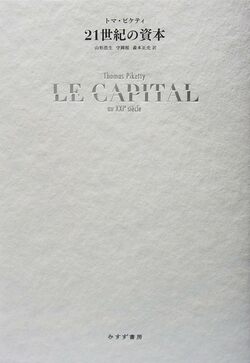現代の政治や経済、社会について語るときの大前提は、「経済格差が拡大している」だ。その原因は「資本主義」や「グローバリズム」で、だからこそその暴威を国家の力によって制御しなければならない、という議論が巷(ちまた)にはあふれている。
 Photo/タカス / PIXTA(ピクスタ)
Photo/タカス / PIXTA(ピクスタ)
「格差拡大」が当然のファクトとされたのは、いうまでもなく、フランスの経済学者トマ・ピケティの『21世紀の資本』(山形浩生、守岡桜、森本正史訳/みすず書房)の影響が大きい。2013年に刊行された(日本語版は2014年)この世界的ベストセラーで、ピケティは資本主義社会における経済格差の拡大を「r > g(資本収益率が経済成長率を上回る)」という不等式で説明し、資本をもつ者の富が加速度的に増えて格差がとめどもなく拡大しているとして、真の平等を実現するために累進的な資本課税が不可欠だと説いた。
ピケティが提示したナラティブ(物語)を要約するならば、以下のようになるだろう。
「18~19世紀のヨーロッパは、低い税率と最小限の市場規制によって野放しの資本蓄積が可能になる「世襲資本主義」で、ごく一部の超富裕層が富の大部分を所有し、それが相続によって維持されていたが、20世紀前半の2つの世界大戦と社会政策(福祉国家化)によって格差が縮小した。だが20世紀後半(1970~80年代以降)になるとこの流れは逆転し、富の不平等は歴史的な水準に押し上げられた――」
こうしてピケティは、「資本が帰ってきた(資本の支配力が戻った)」と宣言する。現代の先進国(西欧諸国)では資本の総額が国民所得の5~6倍に達し、19世紀の水準に近くなったというのだ。
この分析はきわめて説得力があるが、スウェーデンの経済学者ダニエル・ヴァルデンストロムは、『資産格差の経済史 持ち家と年金が平等を生んだ』(立木勝訳/みすず書房)で、最新の調査文献にもとづいて西欧(アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン)の富の分布を詳細に検証し、ピケティの主張に真っ向から反論している。
ヴァルデンストロムによれば、「わたしたちが生きている時代は比類のない不平等の時代」というのはフェイクニュースの類いで、ピケティが提示する「古いナラティブ」は新しいデータによって否定されており、(リベラルにとって)不都合な事実とは、「過去1世紀のあいだに、西欧諸国の人びとは以前よりずっと豊かに、平等になってきた」ことなのだ。
ここまで読んで「そんなバカな」と思うひともいるだろうが、とりあえずヴァルデンストロムの主張を見てみよう。
「富の大平等化」を証明する3つの事実
ピケティは「資本(所有財産)」に工場・機械などの生産手段を含めているが、ヴァルデンストロムはよりシンプルに、富を「金融資産と不動産資産の合計から負債を除いた純資産」と定義する。わたしたちの一般常識にちかいこの指標で見ると、以下の3つの事実が明らかになる(これは頑健なデータに基づいているので議論の余地はない)。
事実1 今は以前より豊かになっている
第二次世界大戦後は国民の平均純資産が大きく増加していて、1950年から2020年までに7倍にもなっている。所得で見ても、現在のわたしたちの購買力は1980年と比べて3倍以上、1世紀前との比較では10倍近くと、圧倒的にゆたかになっている。
事実2 今日の富は質が違う
個人の富の多くが住宅と年金積立金に紐づいていて、この資産は大衆のあいだでずっと均等に分布している。「富はほぼエリートに集中した状態から平均的な家計に広く分散する状態に移った」のだ。
事実3 今は以前より平等になっている
1900年にはもっとも富裕な1%が下位90%の4倍の富を保有していたが、2010年時点で、下位90%はトップ1%の2倍の富を保有している。とりわけもっとも貧しい層の実質純資産の成長率は、最富裕層を大きく上回っている。
ヴァルデンストロムが本書で提示するあらゆるデータが、過去100年間で、西欧のどの国でも一貫して最富裕層(トップ1%)の富のシェアが低下し、大衆(下位90%)の富が大きく増えていることを示している。そしてこの趨勢(すうせい)は、経済格差がとめどもなく拡大しているはずの1980年以降でも変わらない(ただし平等化の勢いは減速している)。
経済成長は格差を拡大するとされるが、この「富の大平等化」は最富裕層の富が大衆に移転するというゼロサムゲームではなく、社会全体がゆたかになるとともに大衆の富が拡大したことで実現した。
ピケティは、平等のためには累進課税のような国家による介入が必要だと主張しているが、ヴァルデンストロムによれば、平等の実現は不動産資産(すなわちマイホーム)の価値が大きくなったことと、年金積立金(税優遇制度を利用した株式などへの投資)でほぼ説明できる。――ここでの年金積立金は、日本でいうならNISAやiDeCoのような、個人が積み立て、運用結果によって給付額が変わる確定拠出型で、国民年金や厚生年金のような賦課方式の確定給付型ではない。
この主張がどこまで説得力があるかはそれぞれが本を読んでもらいたいが、ヴァルデンストロムの主張は以上のように要約できるだろう。