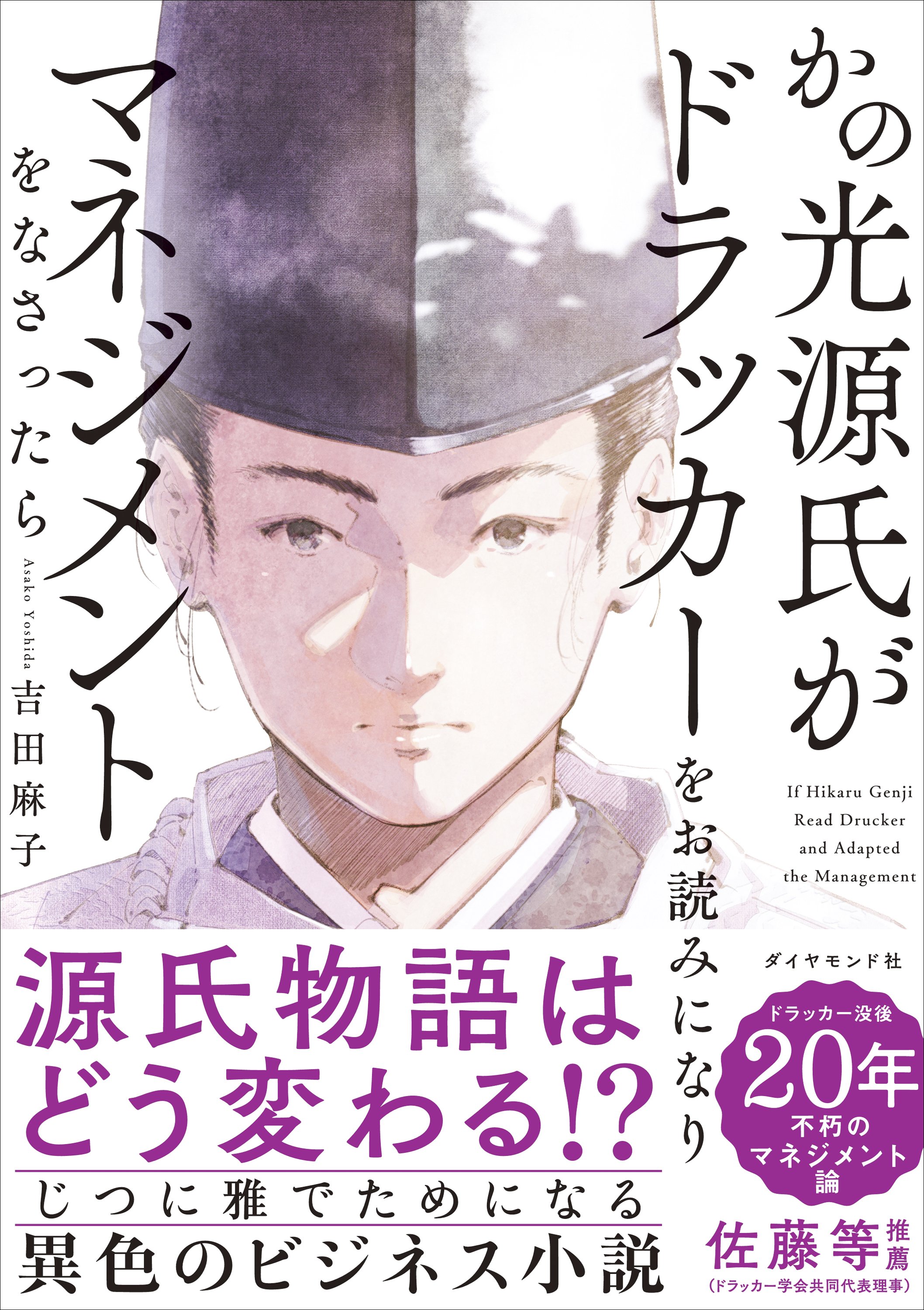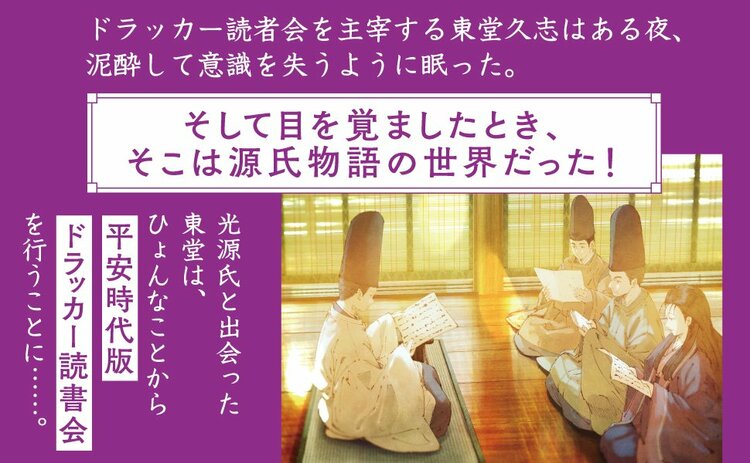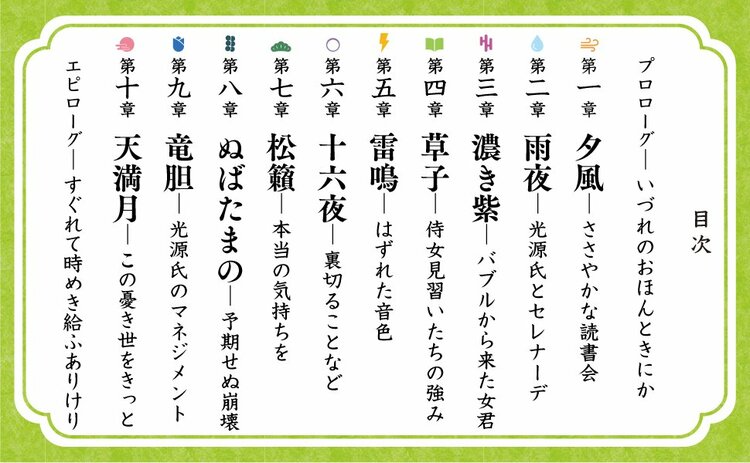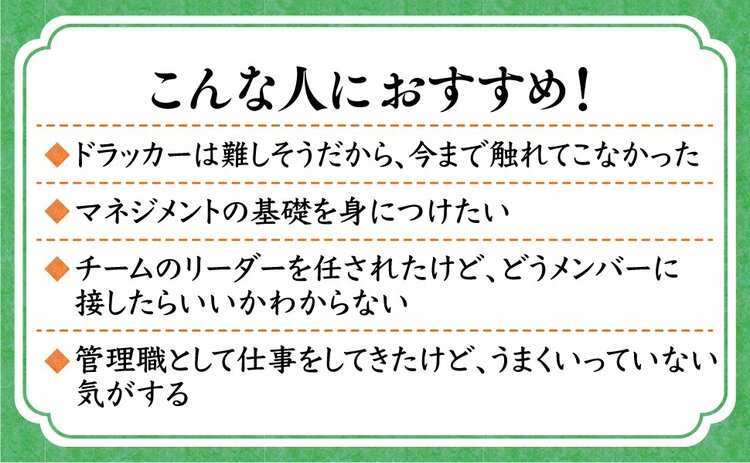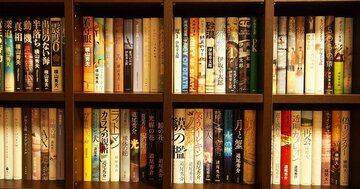なぜ今もドラッカーが読み継がれているのか?
――なぜ今もドラッカーが注目され続けているのでしょうか? 彼が亡くなってからも、企業やリーダーたちが彼の言葉を引用し続ける理由は何だと思われますか?
吉田:ドラッカーの書いた本は、すでに発行から何十年も経過しています。
それにもかかわらず、彼の言葉は色あせることなく、経営者やビジネスパーソンだけでなく、主婦や学生など、さまざまな立場の人々を魅了し続けています。
私は、「問題を抱えてドラッカーを読む人は、そこに必ず解決策を見出す」と思っています。
読むたびに違うページが光って見えるのは、ドラッカーの本が、じつに網羅性の高い“マネジメントの道具箱”として機能しているからではないでしょうか。
未来を予言したのではなく、「変化を観察」した人
吉田:また、ドラッカーは社会生態学者として、社会の変化を記述した人でもあります。
書かれているのは当時の出来事かもしれませんが、その着眼点には今も驚かされることが多く、まるで未来を予知していたかのように感じることすらあります。
彼は未来を予言したのではなく、社会の変化を丁寧に観察し、記録していきました。
そして、その“変化”とは単なる経済構造の移り変わりではなく、人の価値観、働き方、組織のあり方、そして人とテクノロジーとの関係の変化でもありました。
AI時代に甦る「人間への信頼」
吉田:たとえば今、私たちはAIと共に働く時代を生きています。
価値観は多様化し、正解が一つではない時代。
「ドラッカーならどう見るか」と考えながら、いま目の前の現象を観察することができる――それもまた、ドラッカーを読む醍醐味のひとつです。
ドラッカーの著作がいまも読まれる理由は、そこに原理が書かれているからです。
彼の本に登場するのは、状況を断定したうえでのハウツーではなく、時代や業界に依存しない、汎用性の高い普遍的な原理。
しかもそれが広範に網羅されています。
だからこそ、読む人によって心に響く箇所が異なり、「それぞれのドラッカー」と呼ばれているのではないでしょうか。
AIが台頭し、価値観が多様化するいまの時代にこそ、「人の強みをどう生かすか」「組織は何のためにあるのか」という彼の問いが、いっそうリアルに響きます。
彼の言葉は、時代の変化を記録すると同時に、“人間への信頼”を伝えるメッセージでもあるのです。