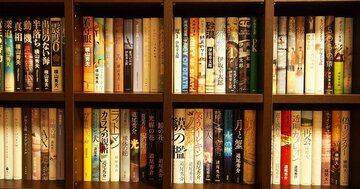もし光源氏がドラッカーを読んでいたら――。
想像するだけで少し愉快で、でもなぜか妙に気になる。
今年、没後20年を迎えるピーター・F・ドラッカーのマネジメント論は、リーダーが抱える悩みを今も鮮やかに解きほぐしてくれます。
「難しそうだから避けてきた」という人にこそ届いてほしいストーリー仕立てで学べる新しいドラッカー入門、『かの光源氏がドラッカーをお読みになり、マネジメントをなさったら』がついに刊行です。
本記事では、著者の吉田麻子氏にドラッカーの魅力を伺いました。(構成/ダイヤモンド社書籍編集局 吉田瑞希)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
優秀なリーダーは部下の「優れたところ」を見つける
―――著書『かの光源氏がドラッカーをお読みになり、マネジメントをなさったら』における光源氏は、「この邸の輝きは、わたしだけでない皆の優れたところの輝きが足し合わさったものなのです」と語ります。現代のリーダーは、どのようにして部下の「優れたところ」を見極めればよいのでしょうか?
吉田麻子(以下、吉田):本書のプロローグでの光源氏の台詞ですね。ここでは本編から二十年弱経った光源氏が出てくるという設定にしています。
この本の中では光源氏は、ドラッカーを学んだことにより「人の強みを生かす」という考え方を実践できるようになりました。
現代のリーダーもしかりです。現場でもよく耳にしますよね。
『部下が成果を出せない』
『どうしても育たない』
でもその見方自体が、成果を遠ざけているのかもしれません。
ドラッカーは部下の強みを生かせと言います。つまり、部下の「優れたところ」を見極める能力が必要となるのです。
これは実践していくことで能力になります。「人の強みを生かす」が「知っていること」から「習慣的能力」に変化していくとよいわけです。
どうやって強みを生かす?
吉田:この能力はどういうもので、どうやったら培っていけるのか考えてみましょう。
具体的には、『経営者の条件』にこのような記述があります。
「仕事と成果を大幅に改善する唯一の方法が、成果をあげる能力を向上させることである」
ここでいう“成果をあげる能力”とは何でしょうか。
このようにも書いています。
「成果をあげる人のタイプなどというものは存在しない」
「成果をあげることは一つの習慣である。実践的な能力の集積である。実践的な能力は修得することができる」
ドラッカーが、掛け算の九九のように何度も反復した練習によって修得できるとしたその習慣的能力が、この『経営者の条件』一冊まるごと使って書いてあります。
それがこの五つです。