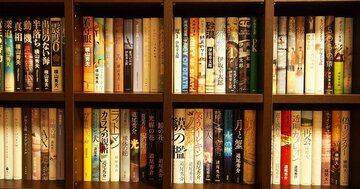「経営学の父」と呼ばれるのは誰か、あなたは即答できますか?
その名は――ピーター・ドラッカー。
彼が残した言葉は、時代を越えて世界中の経営者やビジネスパーソンの指針となっています。なぜ没後20年近く経った今も、ドラッカーは読み継がれ続けるのか。
その生涯と思想をたどると見えてくるのは、“人間への深い洞察”と“変化を見抜く力”。
『かの光源氏がドラッカーをお読みになり、マネジメントをなさったら』の著者である吉田麻子氏に、現代にこそ響くドラッカーのメッセージを伺いました。(構成/ダイヤモンド社書籍編集局 吉田瑞希)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
「経営学の父」と呼ばれた男の本質
――吉田さんの著書『かの光源氏がドラッカーをお読みになり、マネジメントをなさったら』は、平安時代の人物である光源氏がドラッカーのマネジメントを学ぶという異色の設定ですね。そもそも、ピーター・ドラッカーとはどんな人物なのでしょうか?
吉田麻子(以下、吉田):「人の強みを生かす」。
ピーター・ドラッカーがたびたび語ったこの言葉は、彼の考え方を象徴するフレーズとして知られています。
「経営学の父」と呼ばれながらも、彼自身は経営そのものに加え、“人間”や“社会”を見つめた観察者でした。
彼の著作を読むと、「企業にも企業以外の組織にも、本当の資源は一つしかない。人である」という根源的な思いが静かに流れています。
ウィーンで育まれた知と文化
吉田:ドラッカーは1909年11月19日、オーストリア=ハンガリー帝国の首都ウィーンに生まれ、2005年にアメリカ・クレアモントの自宅で95歳の生涯を閉じました。
ウィーンといえば、モーツァルトやベートーヴェンの音楽が響く文化と芸術の都。
彼の父は政府高官、母は神経科医。文化レベルの高い家に育ちました。
ドラッカー家は当時の知識人が集うサロンでもあり、幼い頃から多様な価値観と思想に囲まれて育ちました。
少年期に見た「文明の崩壊」
吉田:しかし、彼の少年時代に第一次世界大戦が勃発します。
かつて6000万人を擁したオーストリア=ハンガリー帝国は崩壊し、人口600万足らずの小国へ。
ヨーロッパ全体が戦争によって荒廃し、文明が崩れ落ちていく光景を、ドラッカーは少年の目で見つめていました。
その数年後、ハプスブルク家最後の皇帝が退位し、共和制が宣言された「共和国の日」。
ドラッカーはその日に行われた労働者のパレードに参加しました。
しかし、水たまりを避けようとしてふと隊列を離れ、そのまま2時間かけて家へ帰ったといいます。
そのとき彼は気づきました――自分は人の先頭に立って旗を振る者ではなく、傍観者である、ということに。
「傍観者」としての自覚
吉田:彼は後に『傍観者の時代』でこう記しています。
この「傍観者」という視点こそが、後のドラッカー思想の原点になりました。
彼は以後、社会や人間の営みを客観的に観察し、変化の本質を見抜こうとし続けます。
ヨーロッパを離れ、アメリカで「マネジメント」を体系化
吉田:ウィーンの進学校ギムナジウムを卒業後、ドラッカーはドイツ・ハンブルクの大学に籍を置きながら商社に就職。その後フランクフルトへ移り、証券会社で働くかたわら大学で学び、新聞社の経済記者としても活動しました。
ヒトラーの台頭を目の当たりにした彼はロンドンへ渡り、証券アナリスト兼パートナー補佐として働きます。
ロンドンでは妻ドリスとの結婚、日本画との出会いもありました。やがてナチスの足音が迫るヨーロッパを離れ、夫妻は新天地アメリカへ渡ります。
ファシズムへの宣戦布告『「経済人」の終わり』
吉田:アメリカで最初に著したのが『「経済人」の終わり』。
ファシズムへの宣戦布告ともいわれる処女作です。
続く『産業人の未来』ではこう述べています。
すでに企業が社会の中心的存在となっていたアメリカで、ドラッカーは「マネジメント」という概念を体系化しました。
「人が強みを生かして生き生きと働く社会」をつくることこそが、機能する社会の礎であると考え、数々の著作を世に送り出していきます。
「社会生態学者」としてのドラッカー
吉田:その著作は関連本を含め40冊を超え、「ドラッカー山脈」とも呼ばれます。
世界の経営者が彼を師と仰ぎ、日本でもイトーヨーカ堂創業者・伊藤雅俊氏やファーストリテイリングの柳井正氏らに多大な影響を与えました。
2009年には『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら』が出版され、映画化もされました。
「マネジメントの父」と称される一方で、ドラッカー本人は自らを「社会生態学者」と呼びました。
それは、経営を超えて「人間と社会の関係」を探求した観察者であり続けた――そんなドラッカーの姿勢そのものを表しているのです。