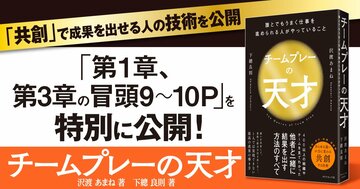最近、「チームで仕事をする」ことが増えていませんか? 自社の前例が通用しない現代において、他社、地域、行政など、他者と協力して答えを出すやり方にシフトする企業が増えています。一方で、価値観や背景のすれ違いや衝突にモヤモヤすることも……。
「立場やお金の力で人を動かすことは、正しいチームプレーではありません」
そう語るのは、組織開発の専門家である沢渡あまねさんと、デザイン経営の研究者・実務家である下總良則さん。400以上の組織やチームを見てきたふたりは、「他者と協力して結果を出せる人たちには共通する行動法則がある」と言います。それをまとめたのが、書籍『チームプレーの天才』です。これまで言語化されてこなかった「チームプレー」のコツを、具体的な93の技術として紹介。発売前から話題の同書から、内容の一部を紹介します。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
脚光を浴び始めた「共創」という言葉
チームプレー、あるいはチームワーク。
近年、チームで成果を出すよう求められるシーンが増えてきました。自分ひとりで、あるいは自組織だけでナントカできる領域が狭まりつつあるからです。
変化の激しい時代において、自分たちの専門性や意欲だけでは、ひいては従来の「勝ちパターン」では答えを出すことができない。よって他者と協力して答えを出すやり方にシフトする。その流れは必然とも言えます。
チームの仲間、社外の取引先、そして、これまで関係のなかった未知なる仲間たち。幅広く他者と手を組み、いままでとは異なる答えを出す。それができない組織や人は、イノベーションはおろか現状維持さえも厳しいでしょう。
過去何十年も個人の成果主義に重きをおいてきた企業が、ここへ来てチームで成果を出すマネジメントに方針転換。そのような記事やニュースも最近よく見聞きします。
その時代の流れの中で、脚光を浴び始めたある言葉があります。
「共創」です。
共に創ると書いて、共創。この言葉をビジョンやスローガンに掲げる企業が増えてきました。「共創企業」を謳う大企業やスタートアップ、「事業共創推進室」「地域共創部」などを立ち上げる企業や行政機関もあります。
共創は「悪気なく」うまくいかない
一方で、チームプレーも共創も「言うは易く行うは難し」の典型。なかなか思うようには進みません。
「共創できるチーム、組織にしていきたい。しかし、うまくいかない……」
企業の経営者や部門長、地方自治体の長などから、このような相談を私たち(あまねキャリア)は日々受けています。そのリアルな声の一部を紹介しましょう。
「個人主義が強く、そもそも皆、他人に無関心」
「ベテランや管理職がいままでのやり方を変えたがらない。過去のやり方に固執し、相手に押し付けようとする」
「上意下達のチームプレーしかできないリーダーが多すぎる(そしてメンバーや取引先が遠ざかるか、モノを言わない大人しい人たちになる)」
「指示・命令型のモノイイや、上から目線な態度が抜けきらない」
「“タテ割り”“内向き”で、他部署や他社と連携しようとしない」
うむむ。なかなか味わい深い(と、味わっている場合ではありません)。これではチームプレーも共創も、いつまでたっても絵に描いた餅。
特筆すべきは、いずれも無自覚で行われがちなところです。そう、私たちは「悪気なく」他者とのチームプレーを遠ざける振る舞い、いわば共創不全の呼吸をしてしまっているかもしれないのです。
これまでのチームプレーは「1.0」と「2.0」
なぜ私たちはなかなか共創の体質に進化できないのか。それは、共創が「ただのチームプレー」ではないからです。
厳密に言うと、これまでチームプレーだと言われてきた(そして多くの人がそう思い込んできた)ものと、共創の所作を伴う「これからの時代のチームプレー」は違うからです。