心理レベルがガクッと落ちる
トイレ介助、入浴介助の限界
家族が在宅介護の限界を感じる主な理由としては、トイレ介助の限界、入浴介助の限界、デイサービスへの送り出し介助の限界などが挙げられます。とりわけ親御さんがトイレをご自身ですませることができなくなると、介護する側、介護される側ともに生活の質や心理レベルがガクッと落ちてしまいます。健康寿命の延伸という意味でも要と言えるポイントです。
最近では、場所を選ばなければ待機期間が短くなったとの声もありますが、都市部を中心に人気のある特別養護老人ホームは入居まで1~2年待つ地域もあります。そうすると入居までの間は自宅で介護するしかありません。こうした待機期間に本人も家族も大変苦労されているケースが非常に多くあります。
一方、(2)のようにトイレ介助、入浴介助、デイサービスへの送り出し介助がしやすいように早めに対策しておけば、自宅に住み続けることが可能です。長いセカンドライフを先読みして将来に備えた対策をした方は、在宅生活が長い傾向にあります。
(3)の場合、在宅介護や在宅医療が可能な住まい・地域かどうか、将来的にさらなる住み替えが必要になるのかを、入居を決める前に必ず確認しておきましょう。ちなみにサ高住や自立型老人ホームなどの居住者を対象に実施したアンケート調査[図13・14]によると、現在の住宅に「住み替えたきっかけ」として、60代後半以降は「日常生活になんとなく不安を感じた」が最も多く、次いで「単身になった」「要支援、要介護になった」が多い結果でした。
![[図13]住み替えたときの年齢とそのきっかけ](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/b/c/-/img_bca48a87df09d9e4ebe353d0be8e794d625859.jpg) 同書より転載 拡大画像表示
同書より転載 拡大画像表示
![[図14]住み替えたときの年齢とその相談相手](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/6/8/500/img_6871ab790027b63515170b9bbee24c9b564261.jpg) 同書より転載 拡大画像表示
同書より転載 拡大画像表示
また、「住み替えの相談相手」は、70代前半までは大半が「配偶者」で、70代後半以降は半数以上が「子ども」と回答しています。
さらに、「現在の住宅を選んだ理由」は、全体として「見守りなどの生活支援サービスがある」「公共交通利便」が多く、「買い物利便」「医療機関・介護施設が充実」と続きます。[図15]が示すように、住み替えパターンの3つのケースを時間軸で見ると、早めにサ高住や自立型老人ホームに住み替えた人は、「成り行き任せ」の人よりも特別養護老人ホームなどの介護施設に移る時期が遅くなる傾向にあり、昨今、有識者のエビデンス研究が進んでいます。
![[図15]高齢期での住み替えパターン3 つのケース](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/4/3/500/img_439bce6e303d447ce1ff8ba9b1e59263339164.jpg) 同書より転載 拡大画像表示
同書より転載 拡大画像表示
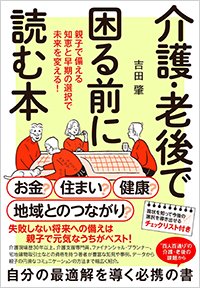 『介護・老後で困る前に読む本 親子で備える知恵と早期の選択で未来を変える!』(吉田肇、NHK出版)
『介護・老後で困る前に読む本 親子で備える知恵と早期の選択で未来を変える!』(吉田肇、NHK出版)







