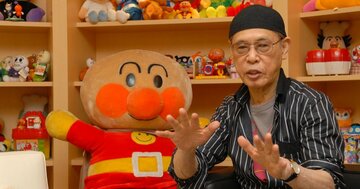別居が始まってほどなく、結婚生活の継続は困難だとして、家庭裁判所に離婚調停を申し立てた。しかし不調に終わり、訴訟へと進んだが、元妻は一貫してモラルハラスメント(精神的な暴力)などは認めず、「離婚したくない」と繰り返した。
別居後も、元妻が住む家の住宅ローン(月15万円)や水道光熱費などは男性が支払っていた。その上、別居中も配偶者に対して支払う義務がある婚姻費用として毎月15万円ほどを要求された。
判決で、離婚は認められなかった。別居期間が2年程度と短く、婚姻関係が破綻しているとは言い難い、というのが主な理由だった。
そこへきて、不幸も重なった。建設現場で起きた事故をきっかけに従業員の退職が続出し、会社をたたむことになった。知人のつてで事務の仕事に就いたが、収入は激減した。同居の父は自宅に戻ることなく亡くなった。
やっとの思いで離婚するも
家も預金もすべて失うことに
やりきれない思いは、元妻への恨みをいっそう募らせた。
反撃の一手として、住宅ローンの返済を停止した。返済が滞れば、金融機関が家を競売にかけ、元妻も出て行かざるを得なくなると考えた。
さらに別居が5年を経過した時点で弁護士を立て、離婚協議を再開した。一般的に別居が3~5年続いていれば、訴訟で離婚が認められやすくなる、と聞いたからだ。
2度目の訴訟。元妻は離婚を拒み続けたが、裁判官の心証は変わってきたようにみえた。
 『ルポ 熟年離婚』(朝日新聞取材班、朝日新聞出版)
『ルポ 熟年離婚』(朝日新聞取材班、朝日新聞出版)
「家に住み続けたいなら、買い取るなり、賃料を払うなりしないと」と元妻を諭した。
決着は意外な形でついた。
訴訟のさなか、家の屋根が壊れ、屋内が水浸しになるトラブルが発生した。多額の修理費がかかることに嫌気がさしたのか、元妻は手のひらを返して離婚に応じてきた。
金融機関の同意を得て家を売り、そのお金で残りの住宅ローンを完済。弁護士費用の約80万円を払うと、預金はほぼ底をついた。ほかに分け合う財産もなく、年金分割の手続きをして離婚が成立した。
「離婚のために家も、金もすべて失った。年金で細々と生きていくだけです」