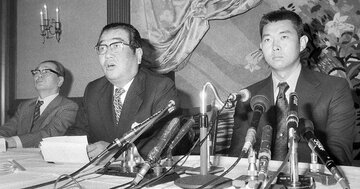そのとき、渡邉は途中で、「もういい!」と怒り出した。彼は最後までそのシステムの必要性や合理的な評価方式を理解しようとしなかった。
当時の彼は85歳だ。高齢はただちに能力の低下を意味するものではないが、メディアのドンがネットとデジタル時代に取り残されていることは誰の目にも明らかだった。
その紙媒体の危機を、トップの椅子に固執する本人は気づいていないか、真剣にとらえていないように見えた。
一方で、新聞の危機を物語る事象はあちこちで現れていた。グループ本社代表取締役社長だった内山斉は、それを象徴する話をしてくれた。
「カネをぶち込んでも、新聞の部数はもう増えない。経営が困難になっているんだよ」
新聞販売の限界がすでに来ている、というのだ。特に社長の座を追われた翌年の2012年以降、内山の打ち明け話は、聞いている私が息苦しくなるような内容となった。
「ナベツネ主筆は販売店会議で演説すれば部数が上がる、と側近の甘言で信じているようだ。だが、拡材をぶち込んでも部数は増えない。これが現実なんだよ」。
内山が細い声で言う。
「しかし、表向きは900万部台を維持していると発表されているじゃないですか」
私が疑問を投げかけると、彼は首を振った。
「いや、実は相当の部数が販売店への押し紙、積み紙だと思う」
苦境の新聞販売店からは
「ナベジョンイル」に恨みの声
新聞界のタブーである言葉に、私は絶句した。
「押し紙」とは、新聞社が新聞販売店に卸した新聞のうち、実際には新聞社が販売店に買い取りを強制する新聞のことである。
一方、「積み紙」は、販売店が、折込広告の受注を増やすためなどに、自ら希望して買い取る配達予定のない新聞を意味するという。
この境目は実に曖昧だ。私の父も地元紙の販売店主だったこともあり、新聞界の販売の一端を知っていた。
内山の話はいつも小声だった。
「販売店はみな困っている。販売店が読者に新聞を取ってもらう場合、3カ月単位で契約してもらうことが多かったんだが、今は単カードといって、1カ月単位の契約がかなりの割合を占めているようだ。自転車操業だ。経営が苦しい店主の中には、ナベツネのことを『ナベジョンイル(北朝鮮の独裁者・金正日に例えた悪口)』と呼んで、彼が死ねば春がやってくると思っている人もいるそうだ。困ったことだが、これからもっと部数は減るよ」