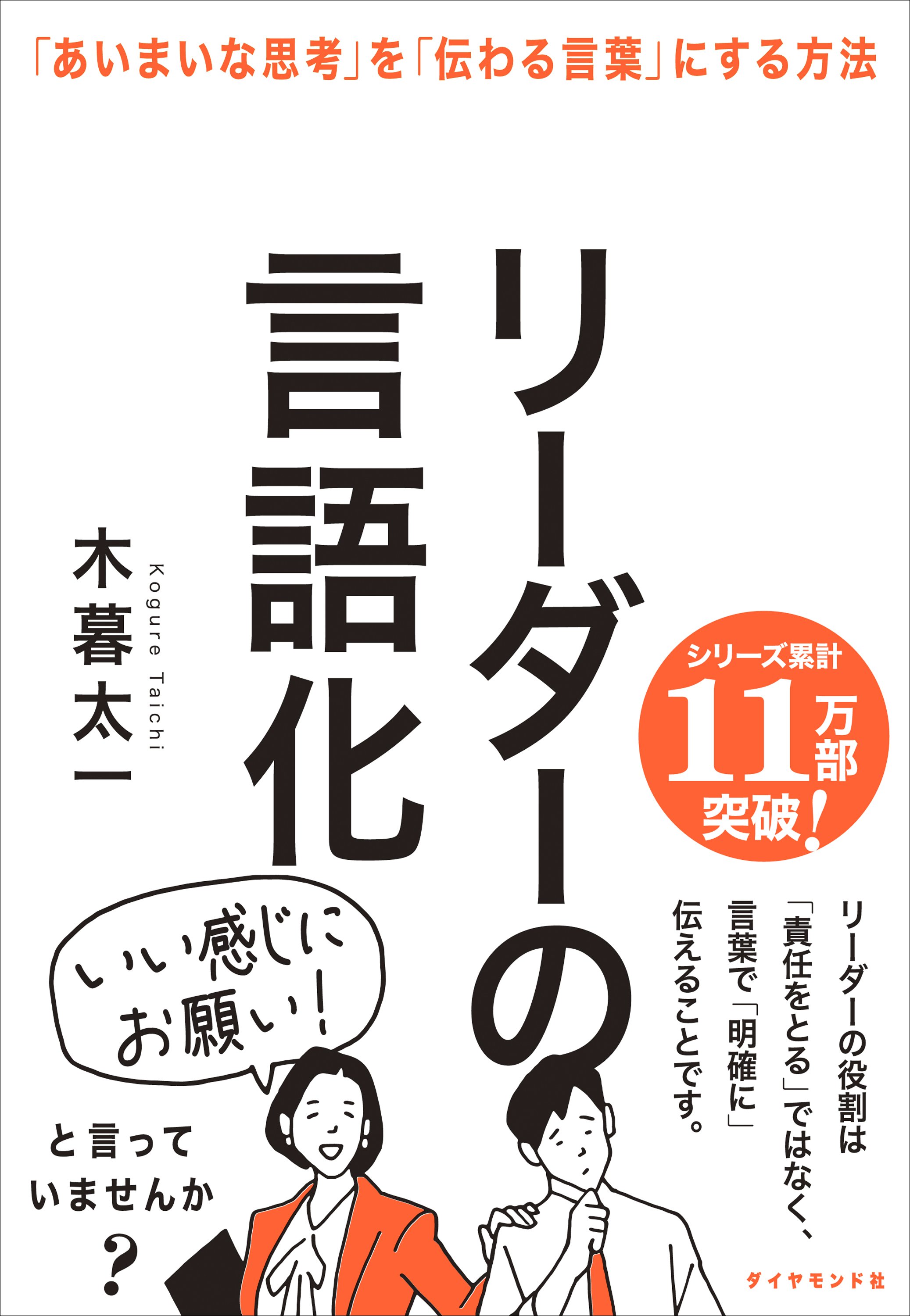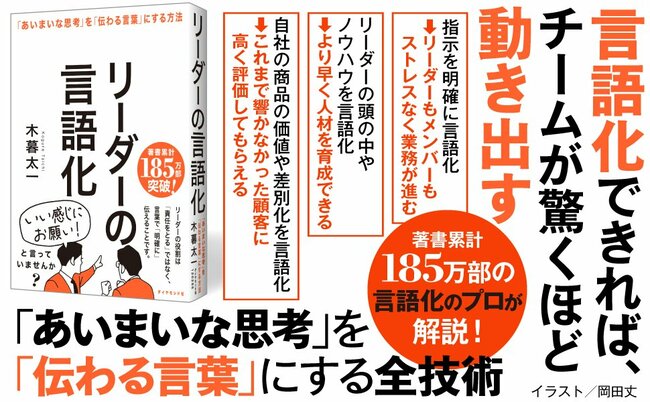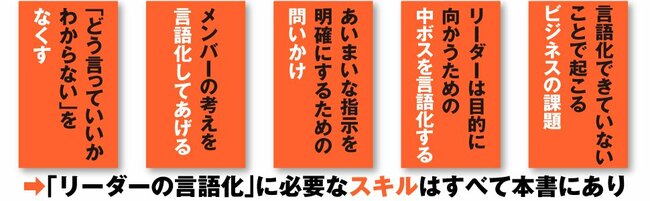意識して鵜呑みにしないことは難しい
とはいえ、AIが出してきた答えはすごいもっともらしいので、最初はその「穴」に気づきません。だからこそ、そのままAIの答えを受け入れてしまうわけです。
では、その穴に気づくためにどうすればいいのでしょうか?
一番いいのは、「人に説明する・教えること」です。
人に教えようとすると、自分が受け入れていた答えに不備があることに気づきます。というか、自分の中でしっかり理屈が通っていなければ人に教えることができません。
表面的には納得していても、誰かに教えることを意識して考え直すと「穴だらけ」ということに気づくんです。
ぼくは中学生のころから、友達に勉強を教えるために学校の授業を聞いていました。だから自分でもよく理解できたし、勉強ができるようになりました。
そして今では、「(書籍執筆を通じて)誰かに教えること」をイメージしながらいろんな勉強をしている。だからより吸収がいいし、理解も進むんだと思います。
「人に教えるつもりで、AIの回答を読むこと」が大事です。それができる人は、AIを使っていても自分の頭で考えることができます。そしてAIに「こういう場合には、当てはまらないと思うけど、どう?」と追加の質問を投げられます。
具体的にはこういうことです。
○ 情報を整理してまとめる作業が必要になる
○ 自分でうまく説明できない部分が明確になる
○ それは自分の中で筋道が通っていない証拠
○ または情報が不足している証拠
○ AIに追加の質問をする
○ 別の角度から情報を確認する
○ 特定のケースについて深掘りする
この過程で、あなたは自分の頭を使っています。単にAIの答えを受け取るだけでなく、AIと対話しながら、自分の理解を深めているのです。
ぼくは19歳のころから本を出版し、これまで67冊出してきました。今でも年に数冊の本を出します。でも、「人に教える」という意味合いのアウトプットは書籍執筆だけではありません。
たとえば
・SNSやブログで学んだことをまとめてみる
・音声メディア、YouTubeで語ってみる
・読書ノートをつける
などができますね。
うまくまとめられなくてもかまいません。大事なのは、自分で相手に説明しようとしたときによくわからないポイントを「自分で気づくこと」です。
些細なことでも構いません。「当てはまらないケースがあるのでは?」と問いかけてみてください。
それを習慣にしていくことで、AIを使う側の人材でい続けられます。