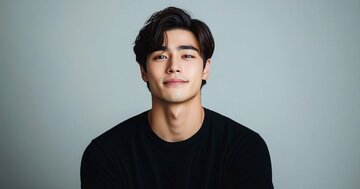「構想力・イノベーション講座」(運営Aoba-BBT)の人気講師で、シンガポールを拠点に活躍する戦略コンサルタント坂田幸樹氏の最新刊『戦略のデザイン ゼロから「勝ち筋」を導き出す10の問い』(ダイヤモンド社)は、新規事業の立案や自社の課題解決に役立つ戦略の立て方をわかりやすく解説する入門書。企業とユーザーが共同で価値を生み出していく「場づくり」が重視される現在、どうすれば価値ある戦略をつくることができるのか? 本連載では、同書の内容をベースに坂田氏の書き下ろしの記事をお届けする。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
現場の「不」を集めても、生産性は上がらない
ChatGPTやClaude、Gemini――今、多くの企業が生産性向上を掲げて、生成AIの導入を進めています。しかし現場からは、「かえって手間が増えた」「誰も使っていない」という声が後を絶ちません。
なぜ全社導入までしたのに、成果が出ないのか。実は、問題はAIの性能ではなく、あなたの会社の仕組みそのものにあります。
多くの企業は、現場の「困りごと」を潰せば効率化できると信じています。生成AI導入の現場では、「不便」「手間」「わかりにくい」といった現場の「不」を拾い上げ、次々と機能追加していくケースが少なくありません。
しかし、足し算を続けるほどシステムは複雑化し、部分最適に陥って全体最適からはむしろ遠ざかります。目の前の「不」の対処に集中するあまり、組織全体のつながりを見失ってしまうのです。
ERP導入の失敗のメカニズムが、再び繰り返されている
このような誤りは、実は昔から繰り返されています。
2000年前後、日本企業の多くがERP(統合基幹業務システム)を導入しました。当時も「現場の声を反映する」ことが善とされ、あらゆる要望を取り込みました。
その結果どうなったか。現場のあらゆる「不」が反映されたERPは、巨大なカスタマイズの塊となり、誰も使いこなせない複雑な仕組みが残りました。期待した生産性の向上につながらなかったケースも少なくありません。
生成AI導入のつまずきは、まさにこの構図の再来です。
「何を足すか」ではなく「何をひくか」を決めよ
欧米企業はERP導入時、「業務をシステムに合わせる」と決め、人員配置や役割までも大胆に変えました。彼らが行ったのは「改善」ではなく、「削ぎ落とし」と表現できるでしょう。
生産性を上げるとは、「何を自動化するか」ではなく、「何をやめるか」を組織全体の設計として決めることです。
経営とは、生成AIに仕事を任せることではなく、人と仕組みを変える決断を下すことにほかなりません。
「不」を埋めることが、必ずしも正解ではない
ニーズを把握する核心は、「不」をすべて解消することではありません。本当に大切なのは、「何を残し、何を削ぎ落とすか」を見極める、全体を見渡した意思決定です。
もちろん、ユーザの声に耳を傾けることが戦略づくりの出発点となることは、前回触れた通りです。しかし、現場の「不」を一つひとつ拾い上げるだけでは、戦略の方向性にまとまりがなくなり、本来目指すべき未来像から遠ざかってしまいます。
視野を広げ、未来に向かって仕組みを変える力は、『戦略のデザイン』のレッスン1で、具体的な「問い」と「型」として整理しています。型を使いながら考えれば、「戦略を立てる力」は誰でも鍛えられます。
『戦略のデザイン』では、こうした「構造を変える思考法」を10のレッスンで体系化しています。生成AIをツール導入で終わらせたくない方こそ、一度手に取って読んでみてください。
IGPIグループ共同経営者、IGPIシンガポール取締役CEO、JBIC IG Partners取締役。早稲田大学政治経済学部卒、IEビジネススクール経営学修士(MBA)。ITストラテジスト。
大学卒業後、キャップジェミニ・アーンスト・アンド・ヤング(現フォーティエンスコンサルティング)に入社。日本コカ・コーラを経て、創業期のリヴァンプ入社。アパレル企業、ファストフードチェーン、システム会社などへのハンズオン支援(事業計画立案・実行、M&A、資金調達など)に従事。
その後、支援先のシステム会社にリヴァンプから転籍して代表取締役に就任。
退任後、経営共創基盤(IGPI)に入社。2013年にIGPIシンガポールを立ち上げるためシンガポールに拠点を移す。現在は3拠点、8国籍のチームで日本企業や現地企業、政府機関向けのプロジェクトに従事。
単著に『戦略のデザイン ゼロから「勝ち筋」を導き出す10の問い』『超速で成果を出す アジャイル仕事術』、共著に『構想力が劇的に高まる アーキテクト思考』(共にダイヤモンド社)がある。