しかし、未修者コースは、法学部にいながらしっかり法律を勉強していなかった、という意味での未修者ばかりになりました。これはひとえに、法曹養成制度の制度設計の失敗によります。
司法試験合格に要する時間と費用を膨大なものにしたうえに、合格率を低いままに抑えたため、実務法曹をめざすことがとてつもなくコストとリスクが大きい選択となり、優秀な人材にとって、自分の人生を賭けるようなチョイスではなくしてしまったのです。
試験のハードルを上げても
弁護士の質は上がらない
このような失敗に至った理由はどこにあるのでしょうか。
それは、司法制度改革審議会が掲げた理念と、実際に作られた制度が、まったく不整合であったことにあります。むしろ理念の実現とは正反対の方向に事態を進行させるような制度が設計されたのです。
そのような制度設計の失敗の原因は、多数あるでしょうが、根本的な点を1つ挙げるとすれば、それはペーパーテストによって優れた実務家を選別できるという幻想に囚われたことにあります。
このような幻想が存在したために、法科大学院という教育のプロセスにいくら手を掛けようとも、最終的には司法試験というペーパーテストで厳格に選別しなければならないという固定観念から逃れられなかったのです。
この幻想の根源はどこにあるのか。
私は、かつての合格者450人時代の旧司法試験にあると思います。
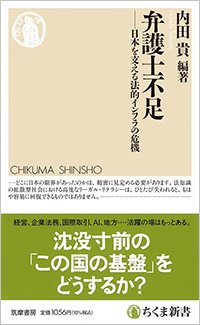 『弁護士不足――日本を支える法的インフラの危機』(内田 貴編著、筑摩書房)
『弁護士不足――日本を支える法的インフラの危機』(内田 貴編著、筑摩書房)
この時代、2〜3万人の受験生の中から450〜500人程度の合格者が選ばれ、実際、優れた法曹が選抜されていました。このため、この時代の法曹たちの間に、「自分たちは困難な試験を突破したから優れているのだ」という意識を生み出したように思います。
それは幻想だ、と私は思います。
確かに彼らは優れていました。しかし、彼らが優れていたのは、試験が難しかったからではなく、優れた人材が司法試験に集まっていたからです。彼らは優れているから試験で選抜されたのではなく、優れた母集団の中で選抜がおこなわれたから優れていたのです。
これは、言い換えると、近接する順位で不合格となった人たちと入れ替わったとしても、やはり同等に優れた人たちが選ばれていた可能性は高い、ということです。







