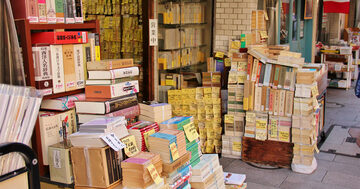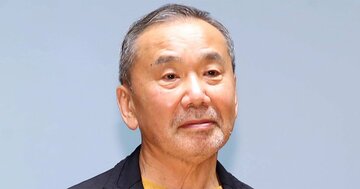気に入った原稿を得ると
声に出して読みあげた
樗陰の実務を覗き見れば、そこに、現代に息づく編集の流れがはっきりと見てとれます。
ひとつは、文芸の編集。田山花袋、正宗白鳥、谷崎潤一郎、室生犀星、宮本百合子、宇野千代、芥川龍之介など、明治、大正を代表する錚々たる作家たちの原稿を樗陰は雑誌に掲載します。
編集者は、社内で企画会議を通した企画を正式に作家へ依頼します。小説の場合、企画書といっても、著者名とおおよそのタイトル、おおざっぱな内容の方向性くらいでしょう。
実際には、「著者名 仮タイトル 長編or短編集」くらいしか書けないことも多いはずです。まして樗陰のころ、企画書をつくっていたのか、定かではありません。
ただ、同僚の編集者たちに、「誰々に小説を書いてもらいたい」という合意は取っていたでしょう。そうでないと、雑誌の目次(台割)すらつくれませんからね。
「〇〇先生、次々号に掲載したいので、〇月〇日締め切りで、(400字詰め原稿用紙に)20枚書いてください」
こうした依頼がおこなわれていたはずです。
樗陰は、依頼した原稿があがってきて、気にいると、朗々と読み上げることしばしばだったそうです。
同僚たちにも、その良さをわかってほしい。すぐに理解できない後輩がいると、原稿片手に何度も何度も説得するように語ったと言います。言われる本人は迷惑だったでしょうが、一流の読み手である樗陰の気概を直にシャワーのように浴びながら、「中央公論」編集部が運営されていたのは間違いありません。
作家に対しても、まっすぐ情熱を注ぎます。正宗白鳥は、「滝田君と私」で、「熱烈なる文学愛好者であった氏は、私の面前で推賞するのみならず、諸方へ行ってその傑作たる所以を宣伝した」と書いています。
ところが、気にいらないと、作家に書き直しを要求することになります。なかには、それが原因で関係が切れてしまったこともあったようです。