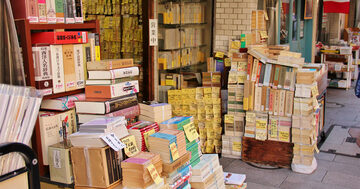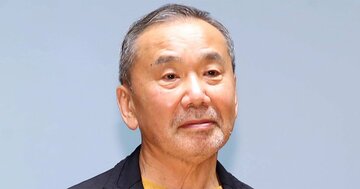「それだけに、出来ばえには筆記者の能力が物をいうわけであるが、その点樗陰は名筆記者であって、ただ先方のいうことをおとなしく写すだけでなく、往々相手の意見の内容にまで立ち入って、批判を加えたり、発展させたりした」(前掲書)
原稿に書き手の血を
通わせる樗陰の技
これはなかなか衝撃ある指摘です。というのは、私の感覚では、筆記者はあくまで語り手が語ったことをまとめるのであり、語り手が言外に話したかったことを推測(あるいはときに忖度)して書くのは許されない。批判を加えたり、発展させるなんて、越権行為ではないか。こう感じるのを否定できません。
よほど、語り手と編集者の間に信頼関係が築けてなければ成り立たないでしょう。
 『出版という仕事』(三島邦弘 ちくまプリマー新書、筑摩書房)
『出版という仕事』(三島邦弘 ちくまプリマー新書、筑摩書房)
現在では、編集者が場をセッティングし、論者が語る。それをライターさんがまとめる。こうした分業体制が取られることが多いです。編集者自らが筆記者まですることは、主流ではないと思われます。
蛇足ですが、私が営む出版社では、語り下ろしでつくるときは、私をふくめ編集者たちがまとめるのが主です。その点では、樗陰流と言えるかもしれません。むろん、語られたこと以上の何かを付け加えるなんてことはしませんが。
おそらく樗陰のころも、編集者がまとめた原稿を語り手、つまり筆者に確認はとっていたでしょう。現代でも必ずそれはおこないます。その際、語り手が大幅に手を入れることがあります。そのプロセスをしっかり踏むことによって、文章が語り手のものになっていく。語り手の血が通い、「書き手」となる。こう実感しています。
語りであれ、自ら書くのであれ、テキストに書き手の「血を通わせる」ようにするのも、編集者の重要なしごとなのです。