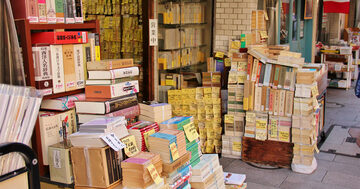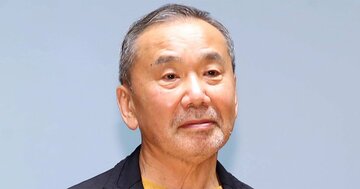それもこれも、樗陰が文字通り、全身全霊、いい作品を世に出そうとする「熱」の結果です。
谷崎潤一郎、宮本百合子…
数多の大作家が知る樗陰の“熱”
熱――。
滝田樗陰のこれぞ、おもしろマグマと言っていいでしょう。
筆の遅かった谷崎潤一郎は、1日に4、5枚書くのがせいぜいだった。ところが樗陰がいると、谷崎が走り書きした原稿を樗陰が横で受け取り、清書する、そうするうちに筆が進み、谷崎は20枚ちかく書けたこともあったそうです。また、「土間に立ったまま、いそがしそうに二言三言いうだけで、五分か十分で帰るのだが、それが一種の気合をおびていて、確実なききめがあった」と谷崎は述懐します。
「貧しき人々の群」を樗陰に見出だされた宮本百合子(当時、中条百合子)は、こう書き記す。
「氏が雑誌につき、計画について話す調子には、いつも見えざる焔があった。(中略)聞いているうちに聴手は聴手で、又、聴手自身の仕事に、一種の張合や熱中を感じて来る」
室生犀星は、
「妙なことは何時でも滝田氏に会うごとに最初に会った時の昂奮に似たものを感じ、それが永い間つづいたのは、我ながら不思議に思っている。つまり私にとっては只ならぬ圧迫をしかも私は好意をもって感じていたのである」
とふりかえる。
一種の気合、焔、張合、熱中、昂奮、圧迫……表現はさまざまだが、確実なのは、樗陰は、書き手に火をつける人であった。樗陰自身のなかにある「焔」が書き手に移ることもあれば、書き手にもともとある火種と呼応するかたちで燃え上がることもあったのでしょう。
おもしろマグマは、このように、作家と編集者のあいだで、相互に影響を与えながら生まれ、育っていくのです。
ゆえに、依頼こそ、おもしろマグマが書き手、作家のあいだにたちあがるための欠かせぬプロセスと言えます。この瞬間に熾るマグマの種火が、その後、書き手が苦労して書きつづけるときの支えになる。