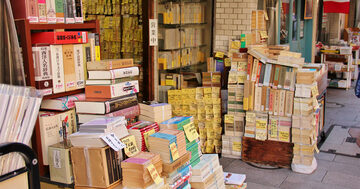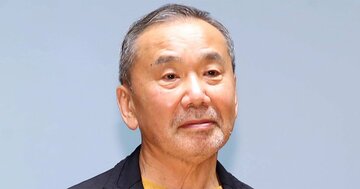ときにくじけそうになったとき、書き手は、あのときの焔を思い出し、再び、弱まっていた焔を燃やす。角度を変えて言えば、依頼時のマグマが書き手、編集者双方に共有されていないと、一冊をつくるという長期の行為を乗り切れない。私自身の経験からも、そういうことが実際にあるのを断言できます。
論壇の分野における
樗陰が残した功績
ビジネス書、新書などでは、「語り下ろし」と言われるスタイルで本づくりがしばしばおこなわれます。『バカの壁』はじめ、養老孟司先生の「壁」シリーズも一例ですね。
再び樗陰を例に見ていきましょう。
先に紹介したように、樗陰は熱をもって作家に依頼する人でありました。その熱に促されるように、作家たちは筆を走らせました。
あえてそうした作家たちの作品をジャンル分けすれば、文芸・文学作品ということになります。漱石、谷崎など現在も読み継がれる大家の作品のみならず、美文調の作品から自然主義派、大衆文学まで、樗陰が編集者として携わり近代文学に残した遺産は、量、質ともにそうとうなものがあります。
一方、樗陰が残した功績のもうひとつに、ジャーナリスティック、論壇の分野における働きがあります。先に、「樗陰の実務を覗き見れば、そこに、現代に息づく編集の流れがはっきりと見」ることができると述べましたが、そのもうひとつの編集の流れです。
その代表例が、吉野作造の「民本論」です。
「大正から昭和へかけて、奔流のように日本を襲った民主主義・社会主義の風潮は、吉野作造の倦まずたゆまぬデモクラシーの主張によって、その下ごしらえがされたといってよく、その背後にあって、吉野をたえず激励し、鞭撻したのも、滝田樗陰であった」(杉森、前掲書)
吉野は「大正デモクラシー」の父と教科書で記述されていたのを私も記憶していますが、その功績が樗陰の筆記によるものとは知りませんでした。
小説、随筆は作家が自分の筆で書き進めるのが当たり前なのに対し、論壇の文章は論者に語ってもらい、それを編集者がまとめて記事にする。樗陰のころは、この口述筆記が基本だったのです。