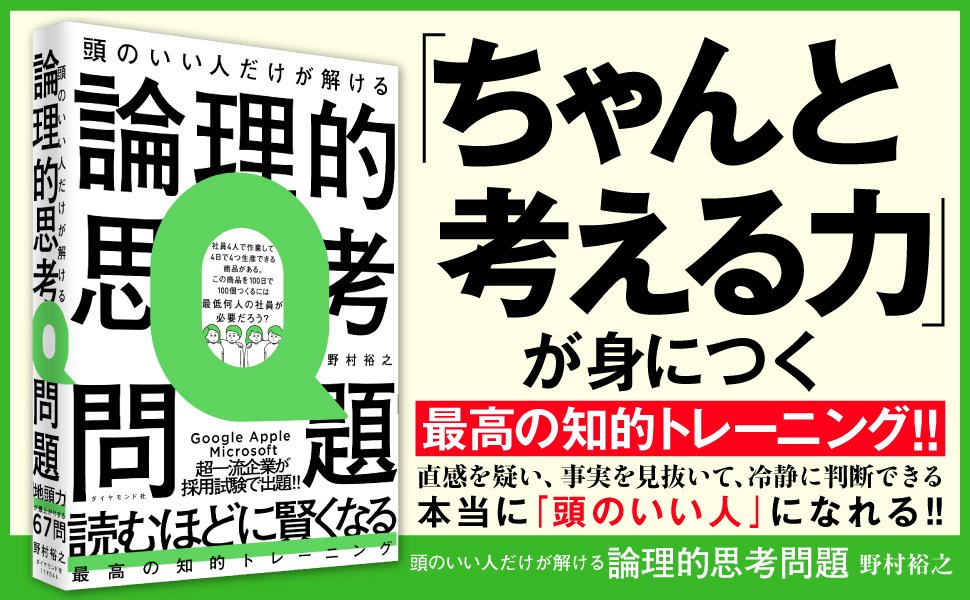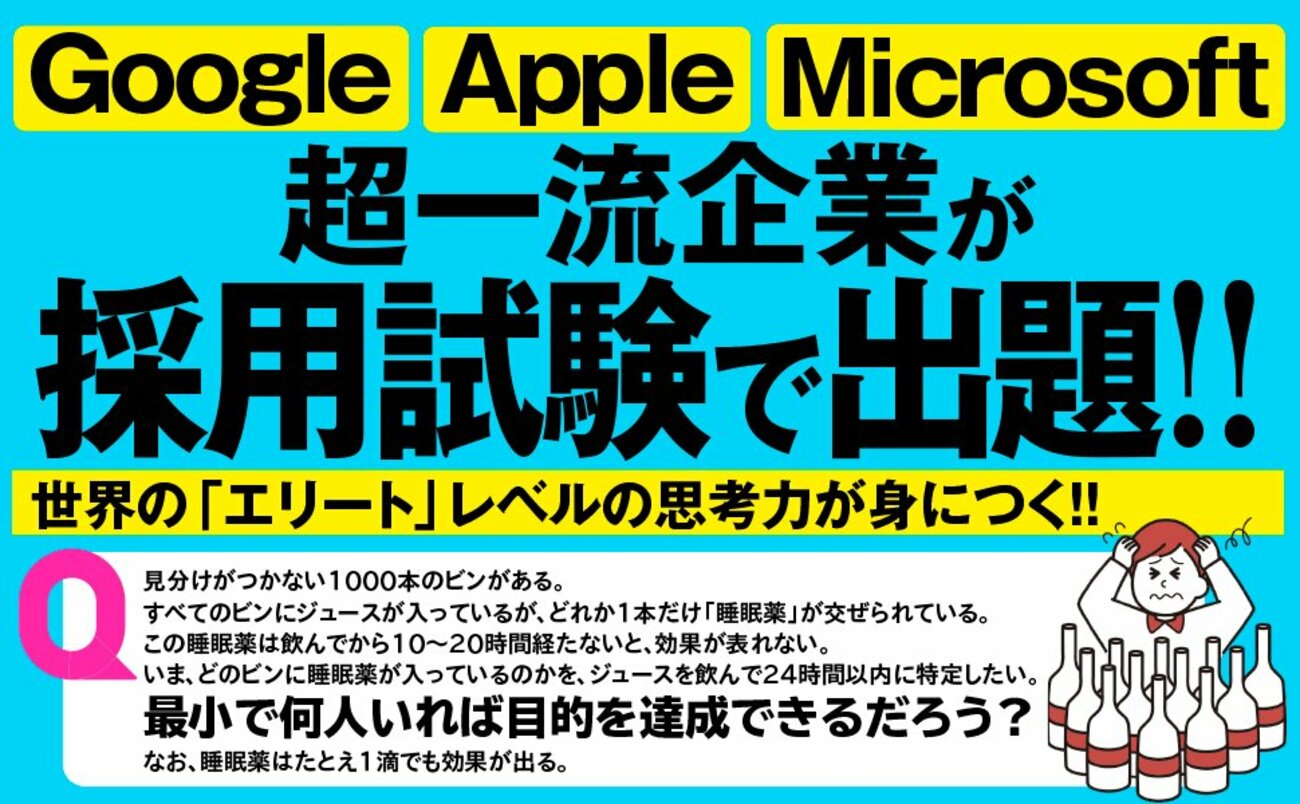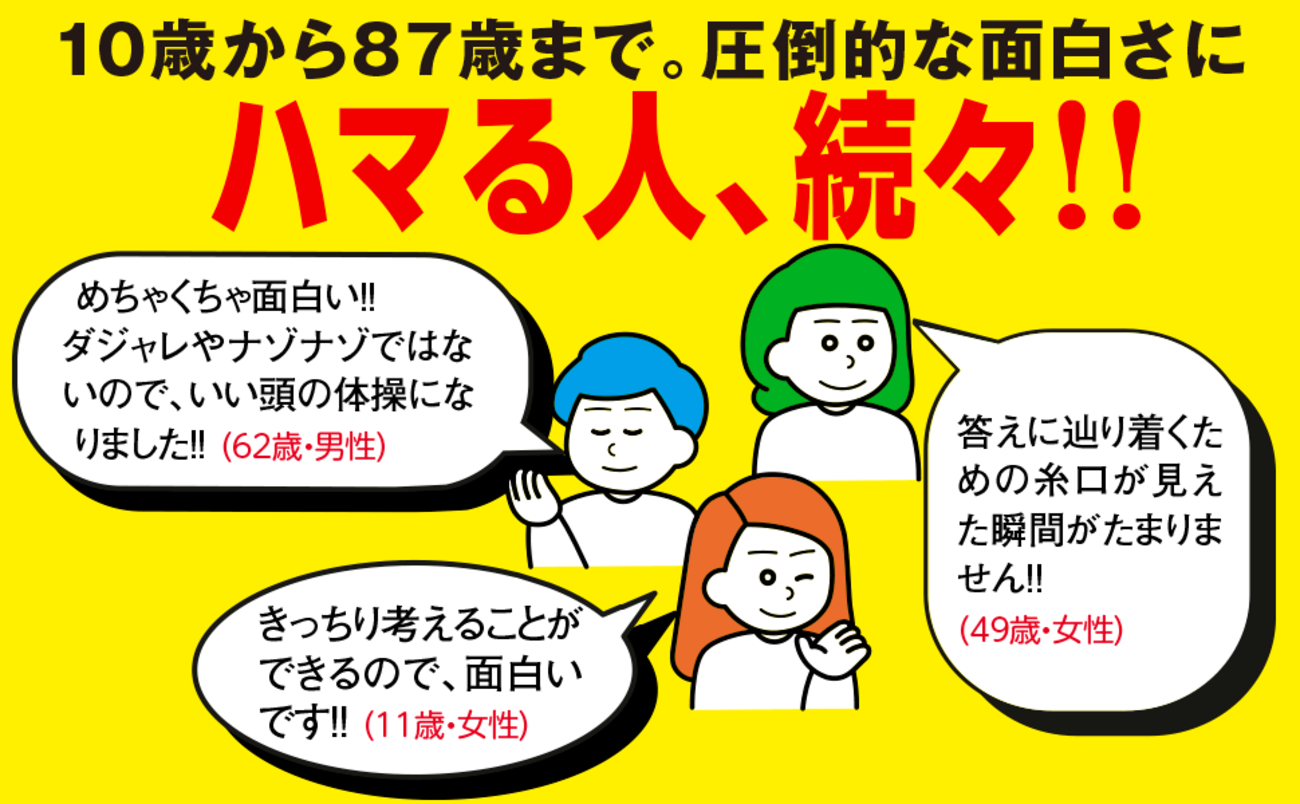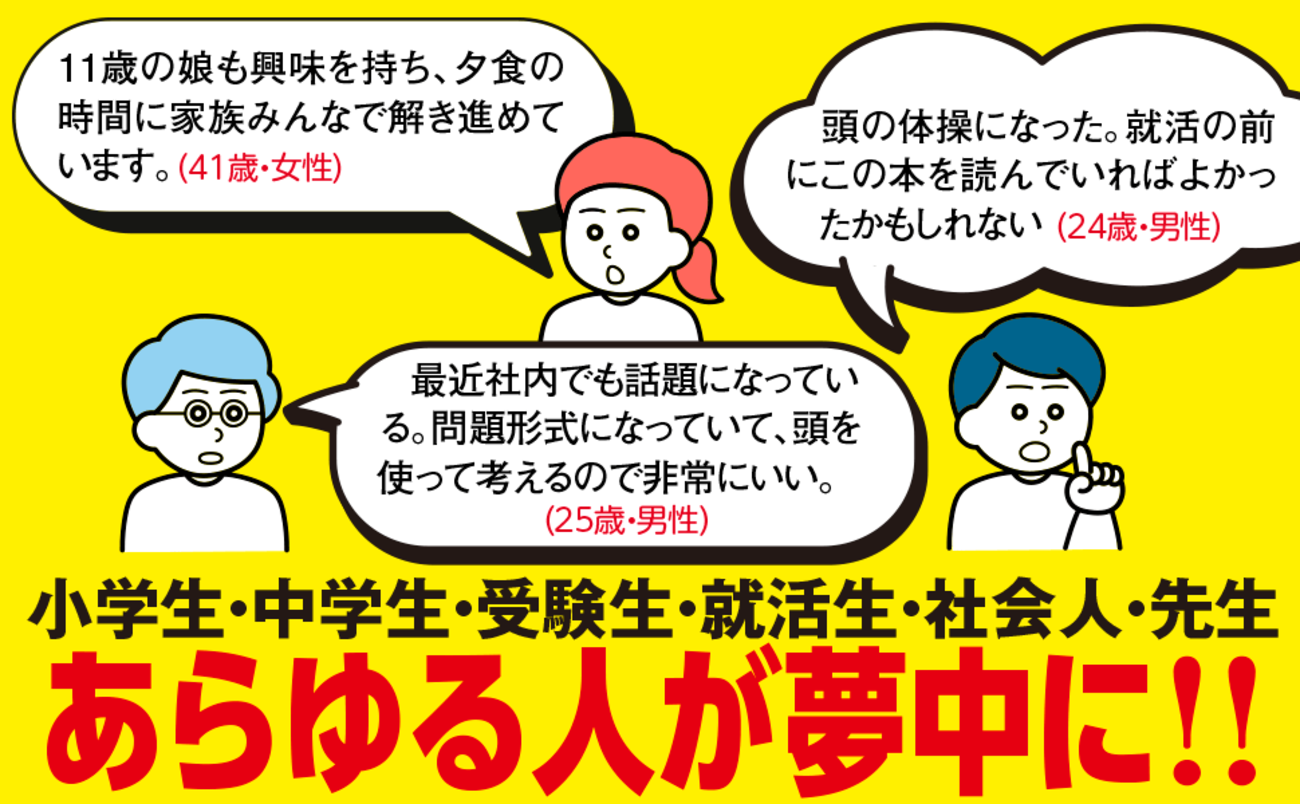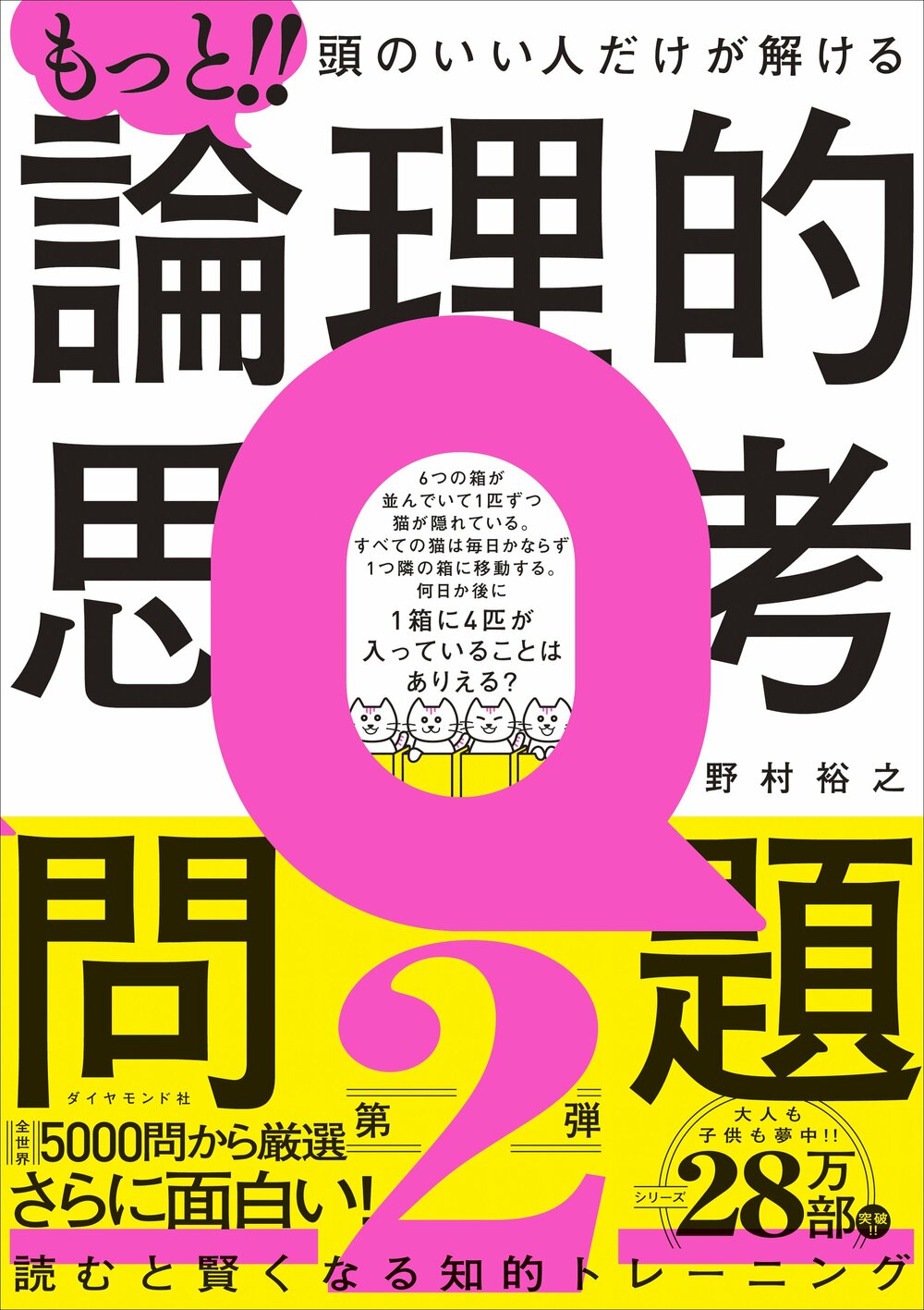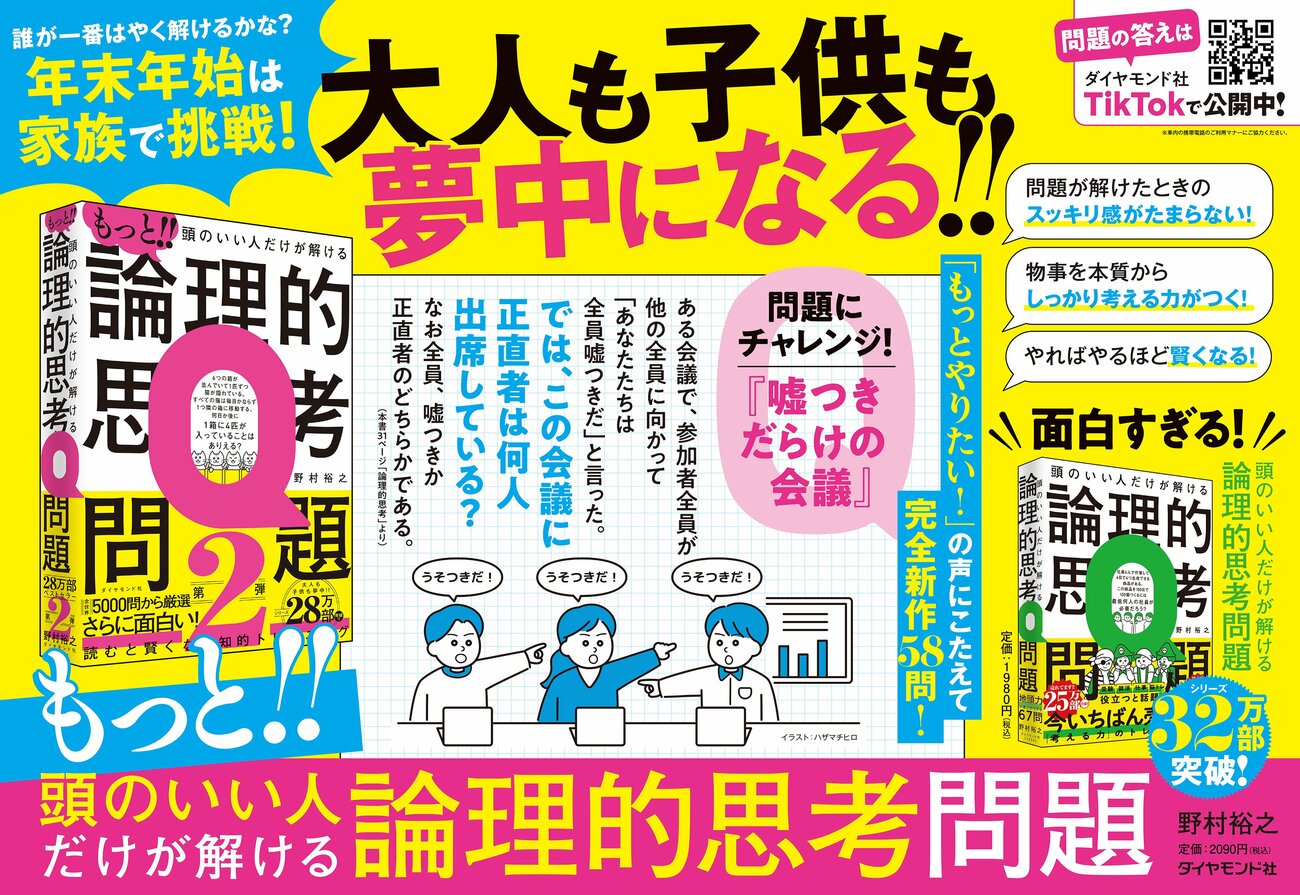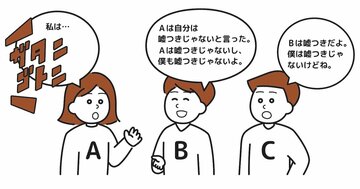たった1つだけ「わかっている」こと
さっそく問題を考察してみましょう。
とは言ってもわからないことだらけですが、1つだけ、確定している事実があります。
それは、「質問できるのは3回だけ」ということ。
「正解に辿り着くには3回の質問が必要になる」ことが示唆されています。
1回の質問単位で考えるのではなく、最後の3回目の質問ですべての真実が明らかになるように、そのためには「何を明らかにしなければならないのか」を逆算して考える必要がありそうです。
「意味のわからない言葉」と、どう向き合う?
ここで問題になるのが3人の神の返答です。
単純に「はい」「いいえ」で答えてくれるわけではないので、逆算して考えるのが困難になっています。
ただ、考えようはあります。
「ダー」と「ヤー」、それぞれの意味はわかりませんが、それは「はい」か「いいえ」のどちらかの意味をかならず示しています。
その内訳を知るのは難しそうですが、何かを聞いたらどちらかの言葉でかならず答えてくれることは確定しています。
つまり1回の質問で、
2つの可能性を1つに絞ることは可能なはず。
質問した相手が真神か偽神だった場合、つねに一定して真実か嘘をついてくれるため有効な回答が入手できます。
よって、信用できる情報は真神か偽神からしか得られないという事実にもとづいて行動する必要があります。
3回の質問で「するべきこと」
必要なステップが少しずつ見えてきました。
……が、ここで大きな壁となるのが、「乱神」です。
乱神は気まぐれで真実を言ったり嘘をついたりします。
よって原理的に「乱神から有効な答えを得る」ことは不可能です。
3回目の質問をした相手が乱神だった場合、すべてが終わります。
ならば最初にすべきは、
「絶対に乱神ではない1人を特定する」ことです。
その上で、「少なくとも1人の神の正体」を特定する。
そして最後に「残り2人の内訳」を特定する。
これが、今回の問題を突破する戦略になりそうです。
流れをまとめると、
2回目の質問:相手が真神か偽神かを特定する
3回目の質問:残りの2人を特定する
となります。
嘘つきに「真実」を語らせる方法
では、1回目の質問から考えていきましょう。
ここでの目的は、
「絶対に乱神ではない神」を特定することです。
2回目、3回目の質問を「真神か偽神」に対しておこない、意味のある回答を得るために、1回目の質問で「絶対に乱神でない神」を特定しなければなりません。
ですが、回答が嘘なのか真実なのかわからない相手に対して、どのように質問すればいいのでしょう。
ここで登場するのが、「二重質問」という方法です。
たとえば、次のような質問のことです。
この質問をすることで、相手が正直者であっても嘘つきであっても、有効な回答を得られます。
例を挙げましょう。
真神なら、『はい』と答えます。
そして偽神の場合、まずふつうに『2+2は4か?』と聞かれたら『いいえ』と答えます。
ですがこの質問では「~と聞かれたら『はい』と答えますか?」と聞かれているので、この問いにも嘘をついて、質問全体に対しては『はい』と答えます。
これとは逆に、「もし『2+2は4か?』と聞かれたら、あなたは『いいえ』と答えますか?」という質問でも、真神と偽神は2人とも「いいえ」という返答します。
つまり二重質問をすることで、
正直者だけでなく、嘘つきも真実を答えてしまうのです。
嘘つきに嘘を2回つかせることで、真実を言わせる方法ですね。
正直者に聞いたら「1×1=1」に。
嘘つきに聞いたら「(-1)×(-1)=1」になるようなイメージの聞き方です。
二重質問の威力
今回の問題でも、二重質問の性質を使って質問を考えてみます。
まず1回目に質問する相手ですが、3人の神の正体がわからない以上、誰でもかまいません。
3人の神を仮にA,B,Cとして、Aに、このように質問してみます。
Aが真実を言う真神であっても、嘘を言う偽神であっても、
・『Bは乱神』という仮説が正しくない場合→『ヤー』と言う
という結果になります。
Aの返答が『ダー』なら、仮説は正しく、Bは乱神だとわかります。
Aの返答が『ヤー』なら、仮説は間違っていて、Bは乱神ではないと判明します。
言葉の意味がわからなくても問題ない?
「『ダー』『ヤー』の意味がわからないのに、信じていいの?」
そう思われたかもしれません。
ちょっとこれだけでは理解しづらいと思うので、実際にどうなるか、仮にAが真神であった場合でシミュレーションしてみましょう。
いつも真実を語る真神であるAに、「もし『Bは乱神ですか?』と聞かれたら、あなたは『ダー』と答えますか?」と聞いた場合、
『Bは乱神?』→ダー(=はい)
「~と聞いたらダーと答える?」→ダー(=はい)
結果:Aは『ダー』(=はい)と答える
『Bは乱神?』→ヤー(=はい)
「~と聞いたらダーと答える?」→ダー(=いいえ)
結果:Aは『ダー』(=いいえ)と答える
『Bは乱神?』→ヤー(=いいえ)
「~と聞いたらダーと答える?」→ヤー(=いいえ)
結果:Aは『ヤー』(=いいえ)と答える
『Bは乱神?』→ダー(=いいえ)
「~と聞いたらダーと答える?」→ヤー(=はい)
結果:Aは『ヤー』(=はい)と答える
このように、『ダー』『ヤー』の意味が「はい」「いいえ」のどちらであっても、
・『Bは乱神』という仮説が正しくない場合→『ヤー』と言う
これが成立しています。
そして二重質問となっているため、たとえAが嘘つきな偽神であっても、返答の結果は上記と同じになります。
・Aの返答が『ヤー』ならBは乱神ではない
ことがわかるのです。
2回目の質問を誰にするか
さて、2回目の質問は「少なくとも乱神ではない神」にする必要がありましたね。
1回目の質問へのAの返答をもとに考えれば、これは容易です。
ただ、このとき気をつけなくてはいけないのが、2回目の質問はAにはしてはいけないということです。
1回目の質問でAの返答が『ダー』ならBが、返答が『ヤー』ならB以外が乱神であるとわかりましたが、
返答をしたA自身が乱神である場合もありえるからです。
その「乱神であるかもしれないA」に2回目の質問をするのは避けたいところ。
=Bが乱神の可能性があり、少なくともCは乱神ではない
→2回目の質問はCに聞く
=少なくともBは乱神ではない(ただしAが乱神の可能性がある)
→2回目の質問はBに聞く
このようにすれば、2回目の質問は確実に「乱神ではない神」にできます。
2回目の質問では何を聞く?
さて、では2回目の質問です。
確実に乱神ではないとわかった相手に、その正体を問いましょう。
ということで、こう質問します。
先ほどの二重質問の性質から、
・「あなたは真神」という仮説が間違っている(つまり真神ではなく偽神)なら、答えは『ヤー』
と、相手の返答によって、その神の正体がわかります。
最後の仕上げ
これで、1人の神の正体がわかりました。
こうなれば、最後の3回目の質問は簡単です。
正体を特定した神に対して、他の2人の神のうち1人の正体を聞けばOK。
ただし、『ダー』と『ヤー』の意味はわからないままなので、ここまでと同じ二重質問で聞きます。
仮にBが真神と特定できたとしたら、Bに対して、
と聞きます。
この3回目の質問にBが『ダー』と答えた場合、『Aは乱神(仮説)』は正しい。
つまりAは乱神で、残ったCは偽神だとわかります。
反対に、Bがこの3回目の質問に『ヤー』と答えた場合、『Aは乱神(仮説)』は間違っている。
つまり乱神はCで、Aは偽神だとわかります。
これで、3回の質問ですべての神の正体を特定できました。
3人の神をA,B,Cとする。1回目の質問はAに対して、「もし『Bは乱神ですか?』と聞かれたら、あなたは『ダー』と答えますか?」と聞く。その答えが『ダー』ならCに、『ヤー』ならBに、2回目の質問として「もし『あなたは真神ですか?』と聞かれたら、あなたは『ダー』と答えますか?」と聞く。その答えが『ダー』なら、その神は真神、『ヤー』なら偽神である。そして2回目と同じ神に、3回目の質問として「もし『Aは乱神ですか?』と聞かれたら、あなたは『ダー』と答えますか?」と聞くことで、残り2人の正体も特定できる。
「思考」のまとめ
不可能に思える難題でしたが、二重質問を駆使することで真実を導けました。
何より面白いのが、『ダー』『ヤー』のどちらが『はい』でどちらが『いいえ』を意味するのかは、最後までわからないままという点。それなのに正解がわかってしまうなんて、魔法のようです。謎があると解きたくなってしまうけど、すべて解かなくても解ける謎もある。そう教えてくれる問題でした。
ちなみにこれは、アメリカの哲学者/論理学者であるジョージ・ブーロスが1996年に発表し、「解答不可能」とまで噂された極悪難易度の問題です。
そしてこの問題には、こんな名が冠されています。
“The Hardest Logic Puzzle”(世界一難しい論理パズル)
その名のとおり、発表以降あらゆる人間を打ちのめし、20年以上経ったいまもこの名称で怖れられています。
・最後までわからなくても問題のない「謎」もある
・謎を謎のままにして、本当に大切なことに向き合う勇気も必要
(本稿は、『もっと!! 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』から抜粋した内容です。書籍では同様の「読むほどに賢くなる問題」を多数紹介しています)