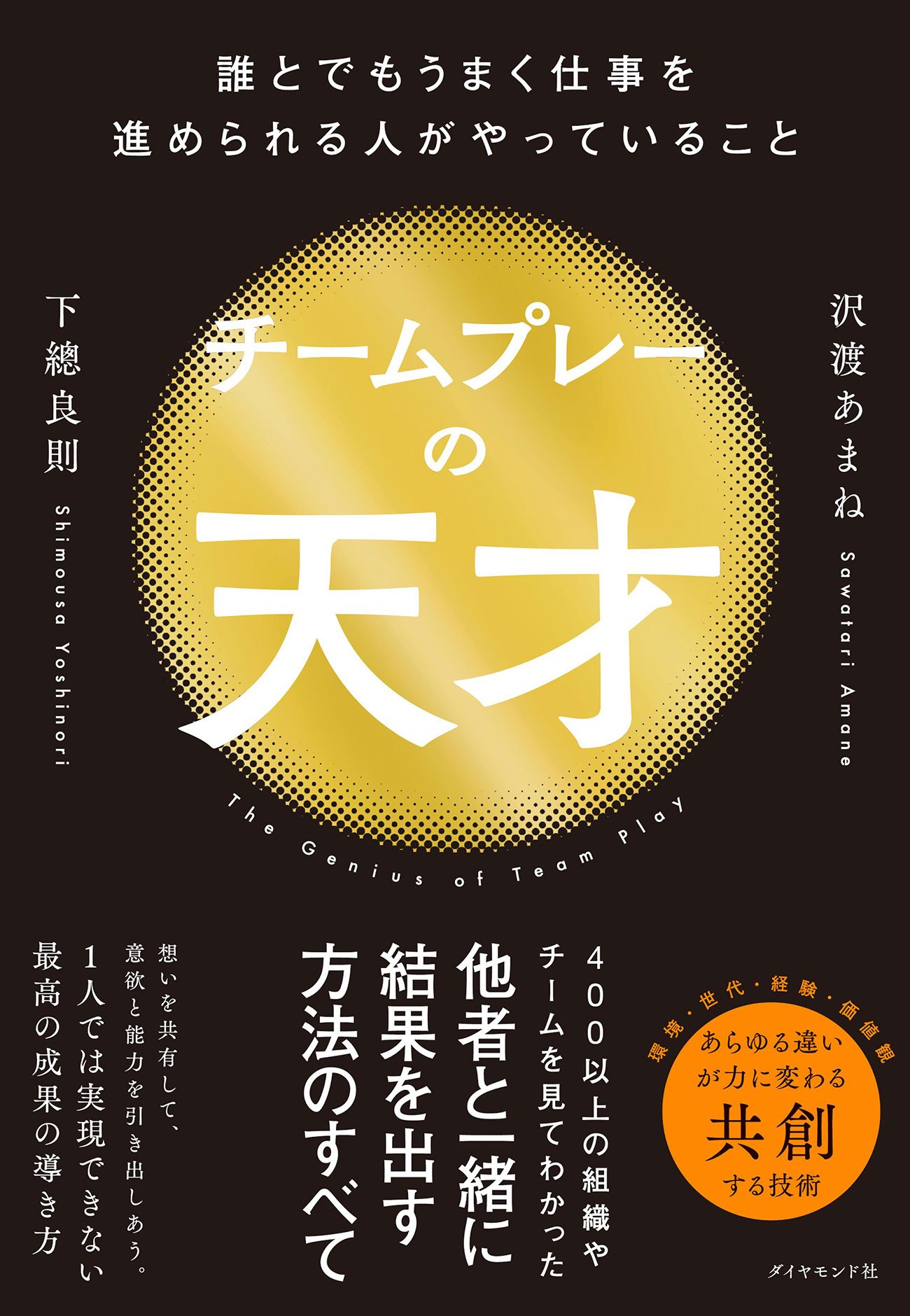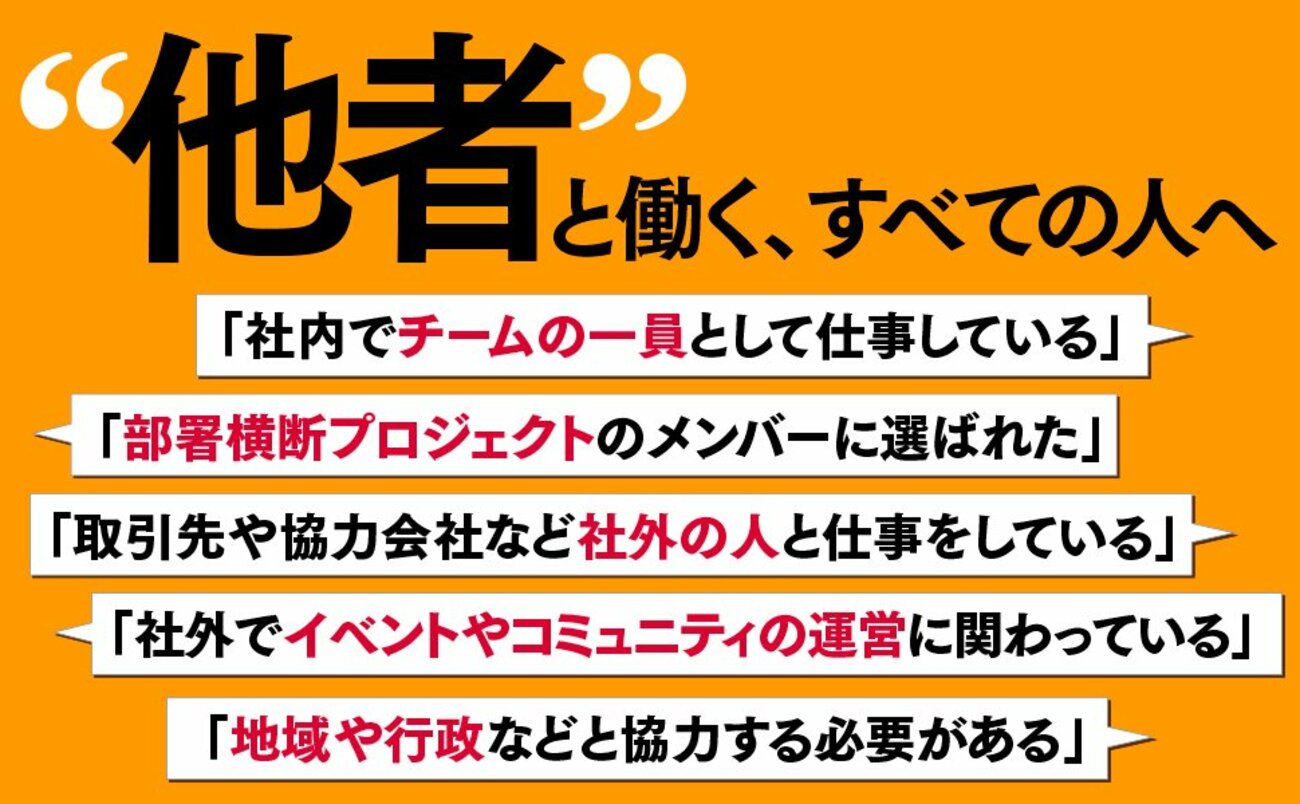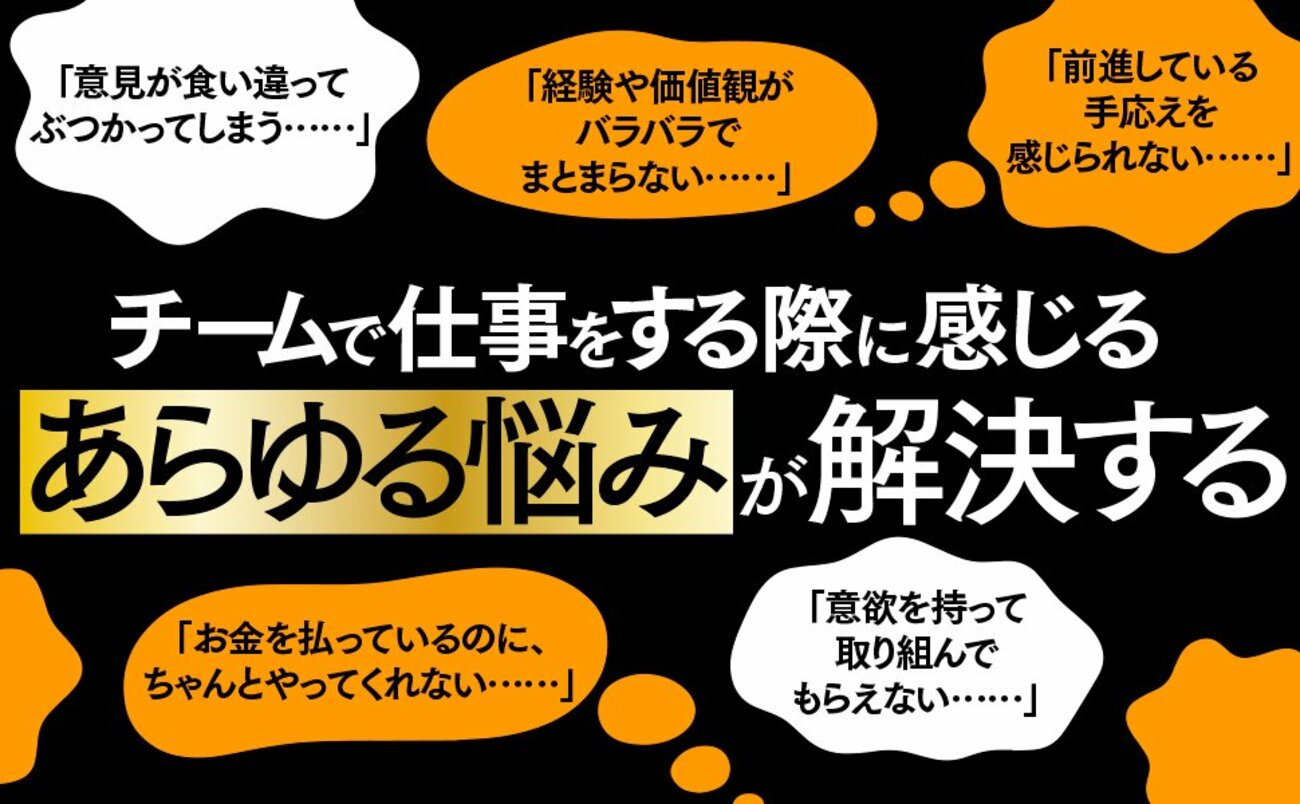チームのメンバーがどこか他人事で、熱量が上がらない――。そんなとき、チームに“自然と好かれる人”は、メンバー一人ひとりがそのプロジェクトを「自分ごと」にできるような問いを投げかけ、チームの目的と個人のテーマが重なるポイントを探していきます。この“接点づくり”を丁寧に行うことで、メンバーの「やらされ感」がなくなり、チームに一体感がもたらされます。
では、どのような問いを投げかけると良いのか? 400以上のチームを支援してきた組織開発の専門家が、「誰とでもうまく仕事を進められる人」がやっていることをまとめた書籍『チームプレーの天才』(沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊)から、そのコツを紹介します。(構成/ダイヤモンド社・石井一穂)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
チームの「やらされ感」をなくす方法
チームでプロジェクトを行う際に難しいのが、すでに決められたビジョンを「与えられる」パターンです。
ともすれば、メンバーがビジョンを自分ごと化しにくく、他人事感ややらされ感が増長され、熱量の低下、活動そのものの自己目的化や形骸化が起こります。
そうならないためには、チームと(関わる)個の接点を見いだしましょう。
接点とは、チームの命題や関心(ビジョンもその一つ)と、個人の生きるテーマなどが重なり合う部分を指します。
メンバーに投げかけたい「問い」
そのビジョンやテーマ、あるいは活動に対して次のような問いをチームに投げかけ、メンバーと一緒に考えます。
「なぜ自分(メンバー)が関わるのか」
「どこに面白味ややりがいを見つけられそうか」
「どのようなスタンスで向き合うか」
「そのチームの活動を通じて、どう自分が成長できそうか(あるいはどんな利益が得られそうか)」
チームやプロジェクトが発足するキックオフミーティングなどでメンバー同士の相互理解も兼ねて、個人ワークとグループワークを組み合わせた形式で行うのもいいでしょう。
チームやプロジェクトのメンバーのみならず、関係する人たち、たとえば他部署や社外のビジネスパートナーなどと一緒に行うのもありです。
ワークを通じてお互いの強みや、そのチームやテーマへの関わり方を知ることができますし、それにより、誰にどんなシーンで何を期待できそうかがわかるようになります。
接点を見いだすのに便利な「フレームワーク」
チーム(組織)と個人の接合部分を見いだす際に役立つフレームワーク(枠組み)の一つが「Will/Must/Can」です。
それぞれ和訳すると、「やりたいこと・ありたい姿」「しなければならないこと」「できること」です。
その活動に対してポジティブな面が思いつかないときは、各々の立場でその活動に対する「Will/Must/Can」を言葉にしてみましょう。
大川陽介さん(株式会社ローンディール)の著書『WILL 「キャリアの羅針盤」の見つけ方』に掲載されている「6Packモデル」も参考になります。
同書では「Will/Must/Can」の洗い出し方についても詳しく解説されていますので、ぜひ読んでみてください。
すぐに答えを出そうとしないで
とはいえ、普段から主体的に仕事に向き合っていたり、キャリアのことを考えていたりする人はさておき、そうでない人たちにいきなり「あなたのWillは?」「Canは?」と問うてもポカンとされることが多々あります。
「仕事とは指示どおりの作業をこなすことである」と考えている人は、いきなり「思いを持て」「思いを語れ」と言われても戸惑ってしまうでしょう。なぜなら、そのような生き方、働き方をしたことがないのですから。
グループワークなどをやってみても、うまくいかない。本人たちもなかなかピンとこないようであれば、場やタイミングを改めましょう。
すぐに答えを出そうとせず、まずはチームでの活動や体験を増やしてみてください。
徐々に自分の思いを言葉にできるようになっていくことでしょう。
(本稿は、書籍『チームプレーの天才』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。書籍では、他者との仕事をラクにする具体的な93の技術を紹介しています)