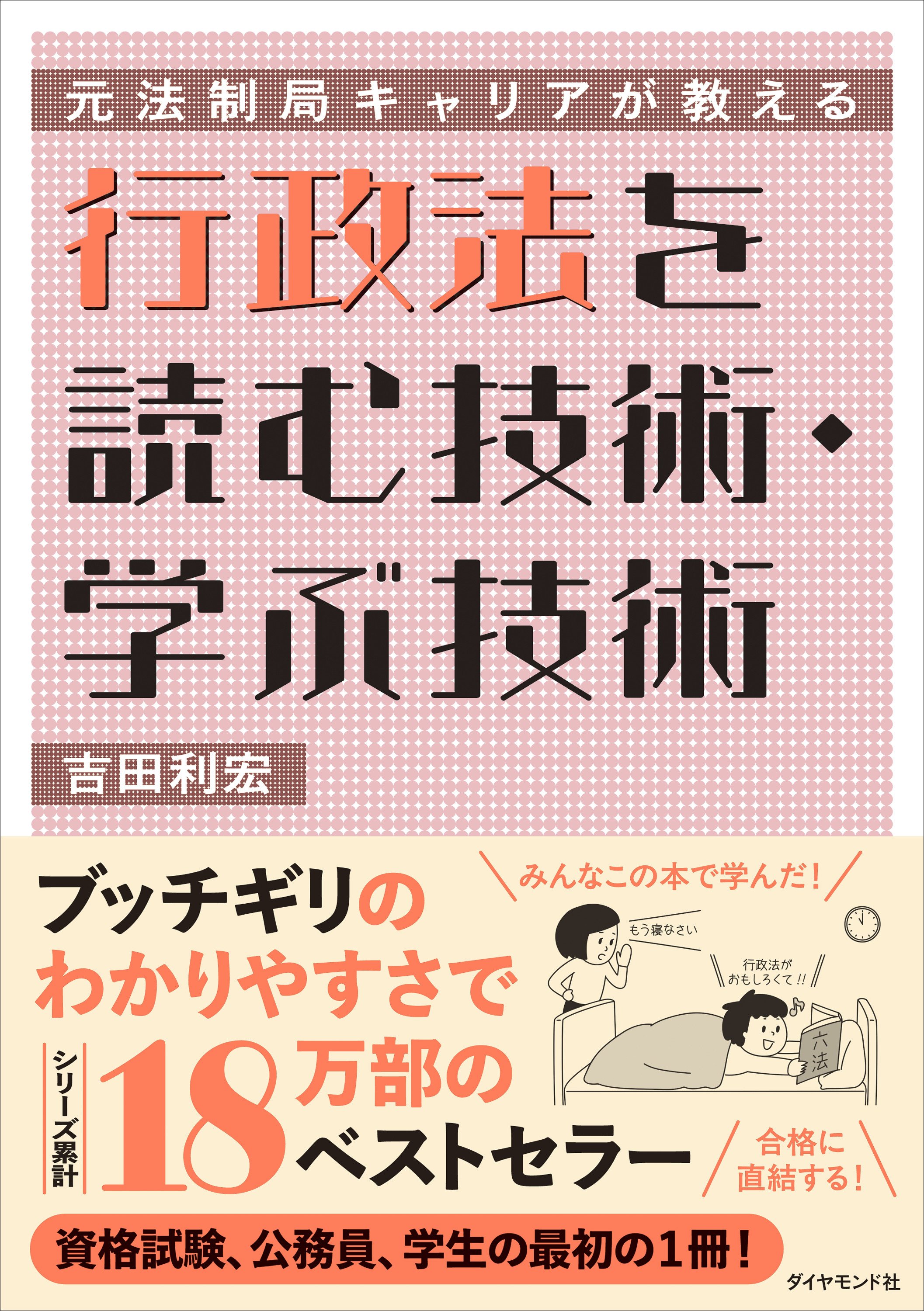累計18万部を超え、法律学習の入門書として絶大な支持を集めるベストセラーシリーズ。その最新刊『元法制局キャリアが教える 行政法を読む技術・学ぶ技術』が発売されました。著者の吉田利宏さんは、衆議院法制局で、15年にわたり法律や修正案の作成に携わった法律のスペシャリスト。試験対策から実務まで、行政法の要点を短時間で学べる1冊です。この記事では、本書を活用した「行政法を学ぶ3つのコツ」について、吉田さんに教えてもらいました。
 イラスト:草田みかん
イラスト:草田みかん
あなたも行政法をスラスラ読めるようになる
「行政法って難しい……」そんなあなたに朗報です。
そう言って『行政法を読む技術・学ぶ技術』(以下、本書)をおすすめしたいところですが、それでもやっぱり難しい。
行政法の難しさは、ことがらの「とっつきにくさ」にあります。民法のように日常生活で頻繁に起こることではないし、憲法のように「うっとりするような理念」が語られているわけでもありません。行政法の条文はイメージしにくく、それが「とっつきにくさ」につながっているのでしょう。
ただ、とっつきにくかったものが好きになるという経験を私たちはしているはずです。
たとえば、初めて飲んだビールはきっと今ほどおいしくはなかったはずです。自分にとっては、納豆、ワサビ漬けなども年齢を重ねるごとにおいしくなってきた食べ物です。慣れといえばそこまでですが、行政法もだんだんと理解できるようになりますし、好きにさえなります。
行政法に早く慣れるためにはどうするか、それにはちょっとしたコツがあります。そのコツを3つばかりお話ししましょう。
行政法を学ぶコツ1:
まずは、行政法の考え方を大づかみする
行政法には、行政法特有の考え方や言葉遣いがあるので、それを押さえることが行政法をマスターするコツです。
本書では、序章と第1章で「行政法の考え方」を解説しています。まずは「行政法の考え方」を読んでみてください。
そして、第2章以下を読んだあと、もう一度、「行政法の考え方」を読み直してください。また、第2章以下で分からないことが出てきたら、「行政法の考え方」を参照しつつ読み進めてみてください。
行政法を学ぶコツ2:
「手続きの順序」をイメージしながら学ぶ
第2章からは、行政不服審査法、行政事件訴訟法など、行政法を一つひとつ学んでいきますが、具体的な行政法をスムーズに理解するために有効な方法があります。
それは手続きの順序をイメージして学ぶことです。
たとえば、行政事件訴訟法であれば、訴える場面で必要な条文、裁判を進めるなかで必要な条文、判決に関する条文と並びます。場面展開を思い浮かべつつ、学んでいきましょう。本書では、手続きの流れをイメージしやすいように、図解を交えてわかりやすく解説しています。
行政法を学ぶコツ3:
行政法の「性格」を理解する
3つ目のコツは、それぞれの法律の性格を踏まえて学習することです。
たとえば、国家賠償法はできるだけ被害を受けた国民を救済しようとしている法律です。ですから、その条文の解釈は「優しさ」にあふれています。
また、行政事件訴訟法での取消訴訟は「行政処分からの脱出装置」であることを理解した上でないと、判例の意味などが入ってきません。
通常の基本書では「分かってるもの」として省略されがちな、こうした記述を手厚くしたのも本書の特徴といえるでしょう。
最初、苦く感じたビールがおいしくなるように、段々と行政法もうまく理解できるようになります。