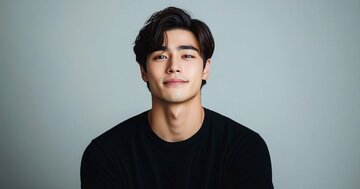AIが「使えるかどうか」は、人間側の「使い方」で決まります。
そう語るのは、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修をしてきた石井力重氏だ。そのノウハウをAIで誰でも実践できる方法をまとめた書籍『AIを使って考えるための全技術』が発売。全680ページ、2700円のいわゆる“鈍器本”ながら、「AIと、こうやって対話すればいいのか!」「値段の100倍の価値はある!」との声もあり話題になっている。思考・発想のベストセラー『考具』著者の加藤昌治氏も全面監修として協力し、「これを使えば誰でも“考える”ことの天才になれる」と太鼓判を押した同書から、AIの便利な使い方を紹介しよう。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
AIを使って“検証手段”を考える「聞き方」
AIを仕事に活用できるシーンは多々ありますが、業務の効率化や自動化だけに使うのは少々もったいない。新しいアイデアを考えるといった、「頭を使う作業」にもAIは活用できます。
ただし、適当な聞き方をしても、質の良い回答は得られません。ロクでもない回答が返ってきてしまうときには、人間側の質問(プロンプト)が適切でないことがほとんどなのです。
たとえば、アイデアを検証する方法を考えたいときにおすすめなのが、技法その37「実証実験の手順」です。
こちらが、そのプロンプトです。
〈商品アイデアを記入〉
このアイデアが、実際に機能するかどうかを確認するための、プロトタイピング作業手順を作成してください。ステップごとに注意すべき点と、達成すべき要件も示してください。
〈仕組みやサービスのアイデアを記入〉
このアイデアが、実際に機能するかどうかを確認するための、実証実験の手順を作成してください。ステップごとに注意すべき点と、達成すべき要件も示してください。
※対象が仕組みやサービスなどの「コト」である場合はプロンプト②を使ってください
新しい商品や製品を世に出す前には、デザインなどは仮であったとしても、必ず「試作品」や「プロトタイプ」を作って、それが実際に機能するのか、効果を発揮できるのかを測定、検証します。
サービスといった「コト」の場合も同じです。仮設店舗を運営したり、一部地域で実験的に導入したりして、限定したユーザーに実際にサービスを利用してもらい、検証作業を行います。
ただ、当然ですが、「実証実験」は簡単なことではありません。案件によって必要な準備や段取りは異なりますし、悩むポイントがいくつもあります。
そこで活躍するのが、この技法です。名称のとおり、AIに実証実験の準備と手順を示してもらいます。かなり詳しく現実的な線を教えてくれます。
「農家が挑戦する新規事業」の実証実験を考えてみよう
では、実践してみましょう。
自分や自社が経験したことのない商品に挑戦する場合、まずは実証実験としてサンプル、プロトタイプを作って検討しておくと安心です。ここでは、「温泉水を使用したみかんジュース」という企画を例に、プロトタイピングの手順を考えてみましょう。
「商品」ですので、ここでは「モノ」のプロンプトを使います。
〈温泉水を使用したみかんジュース。大分県の温泉水を活用した、新しいタイプのみかんジュースを開発。温泉水のミネラルが加わることで、他では味わえない特別な味を実現します。みかんジュース100%がキツい、という方は、付属する温泉水ボトル(飲用)で割ってください。みたいな感じだと商品を何種類も用意しなくてよくなるし、自分で調合した方が好きな濃さが作れて、いいのかもしれません。自分の見つけた「おいしい割り方」なんかは、SNSに書かれて、認知度を上げることにつながりそうです(新しいもの好きは、面白いことが好きですからね)〉
このアイデアが、実際に機能するかどうかを確認するための、プロトタイピング作業手順を作成してください。ステップごとに注意すべき点と、達成すべき要件も示してください。
AIでアイデアを出力し、それに対する素直な感想をプロンプトの自由記述部分にメモ書きしています。「てにをは」を含めて、日本語としては変ですが気にせずに。
同じスレッドで、日をおかずに連続作業する際は、AIがアイデアを弾き出した状態のままのスレッドに続けて、技法「実証実験の手順」のプロンプトを入力してかまいません。