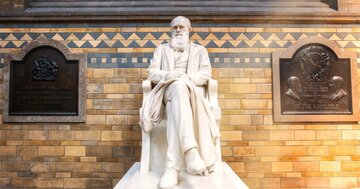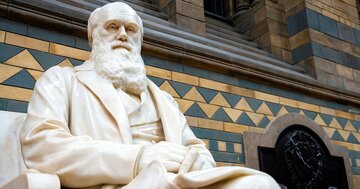だから、カブトガニやシーラカンスなど、大昔からほとんど変化していない生物が存在するのだ。
それは、彼らの生息環境が安定しているので、異なる変異が有利になる状況が生まれなかったからだ。それらの生物を「生きた化石」などと呼ぶのも、生物は「進化・進歩」して当然という考えの表れなのかもしれない。
ものには目的があると思うのは、人間だからなのだろう。ヒトは目的をもって物事を行なうので、たんにそのときの周囲の状況に適合しているだけで、状況が変われば変わるということは、あまり良くないことのように思っている。
目的といった主体的な概念は、ヒトにしかないのだろうが、ヒトは、自分にとってそれがあまりに当然であるがゆえに、すべての事柄にも当てはめてしまうのだろう。
進歩していく社会が
進化理論を捻じ曲げた
 『美しく残酷なヒトの本性 遺伝子、言語、自意識の謎に迫る』(長谷川眞理子、PHP研究所)
『美しく残酷なヒトの本性 遺伝子、言語、自意識の謎に迫る』(長谷川眞理子、PHP研究所)
先に述べた、進化とは進歩であるという考えも、ヒトの生き方と密接に関連しているのだと思う。
近代の人びとは、時代とともに技術が改良され、社会制度も良くなるような改革が行なわれてきた光景を目の当たりにして生きてきた。それが染みついているので、生物は皆、もっと良くなろうという目的をもって生きており、だんだんと進歩してきたと思ってしまう。
ダーウィンが最初に科学的な進化理論を提出したのは、19世紀の半ばだった。まさに社会の進歩を皆が実感していた時代である。ダーウィン自身は、生物の進化をそのような進歩の過程だとは考えていなかった。
ところが、多くの人びとは、進化が世の中の進歩を説明する理論だと誤解して受け入れたのではないか。だから、スペンサーの「社会進化論」があれほど流行したのだ。しかし、それは皆、間違いなのである。