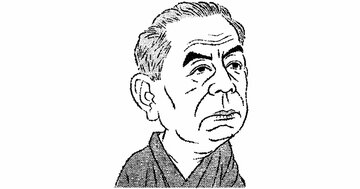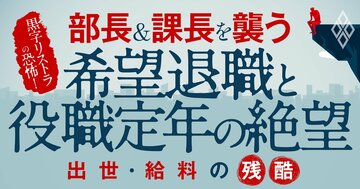「少年時代の僕を、何が活字へ引きつけていたかというと、それは活字のみの持つ非現実性であった。活字がえがき出してくれる、日常の世界とはまったく違った、何かしらはるかな、異国的な夢幻の国への深いあこがれであった」
乱歩と探偵小説の出合い
活字をみるたびに新たな世界を発見した乱歩。文芸雑誌に翻訳されていた、コナン・ドイルによるシャーロック・ホームズシリーズの一つ『金縁の鼻眼鏡』にもこのときに触れている。
しかし、現実世界はより過酷なものとなる。乱歩は高等小学校や中学ではいじめに悩まされた。学校からどんどん足が遠のいていき「空想生活が現実の生活より楽しかった」とまで言っている。
早稲田大学の政治経済学部に入学したのちは、生活苦からアルバイト三昧の日々を送った。というのも、乱歩が中学を卒業する年に、もともと役人だった父が辞職してまで設立した会社が倒産。乱歩は学費を自分で稼がなければならなかったのである。
「青春の交友もほとんどしないままに陰気に早稲田大学を卒業した」
そう振り返る乱歩だったが、いくつか掛け持ちしたうちの一つが、図書館の貸し出し係のアルバイトだった。バイト先の図書館で本を読むのが唯一の娯楽だったという。乱歩は欧米ミステリーを乱読。西洋の暗号に関心を持ち、暗合史なども研究している。
乱歩にとって青春時代とは、本を読むことにほかならなかった。そして、このときの読書体験が、ミステリー作家・江戸川乱歩を誕生させる。
働くのが嫌になり次々と会社から逃亡
大学を卒業した時点では、乱歩は作家になる気などさらさらなかった。
学生時代の貧乏生活があまりにつらかったために、実業家になって金を稼ごうと考えたようだ。知人の紹介で大阪の貿易商社に住み込みで働くことになった。
だが、乱歩はその職場をわずか1年で脱走してしまう。寝ても覚めても職場の人と顔を合わせなければならない住み込みの仕事が、相当なストレスだったようだ。
「私には少年時代から思索癖というようなものがあって、独りぼっちでボンヤリと考えている時間が必要だった。食事や眠りと同じように必要だった」