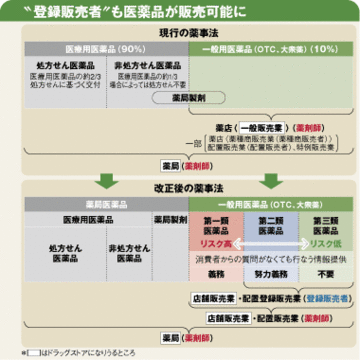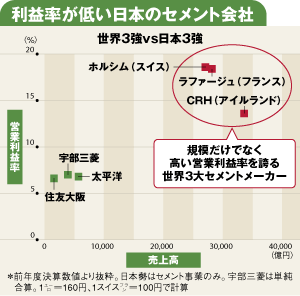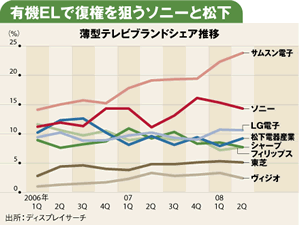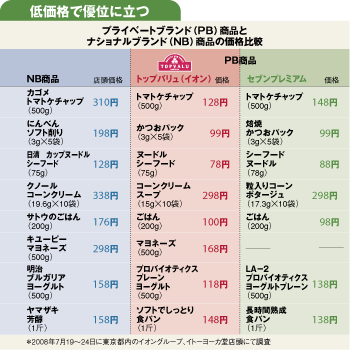金融商品取引法の完全施行、慎重姿勢に転じた銀行融資……。過熱してきた不動産市場に、地殻変動の足音が忍び寄る。生き残りを賭ける新興不動産会社の独自の手法を探った。
「この不動産を20億円で買い取るつもりはないか」――。ある不動産業者に持ち込まれてきた都心のオフィス物件。一等地からややはずれているとはいえ、「少し前だったら、50億円でも買い手が付いたのに」(不動産業者)という代物だ。
この不動産の1年間の賃料収入は2億円。50億円でも単純計算で利回り4%が確保できる。それがいったいなぜ、5分の2という“破格”の値段で買い取りの打診がされるようになったのか。
じつはこの物件は、建築基準法上の要件を満たしていないのだ。過熱相場では目をつぶってきた金融機関が、いまや建物の遵法性を厳しく見るようになった。問題のある物件には融資が付かなくなっている。
これまでは50億円の不動産であれば、20億円は出資金を投じ、残りの30億円は銀行借り入れで賄っていた。もはや、この不動産にはローンが付かないため、「フルエクイティ(すべて出資金)で買い取ってくれる業者を探している」というのだ。
銀座東芝ビルが1600億円、虎ノ門パストラルが2300億円――。連日のように世間をにぎわす高額の不動産取引など、不動産業界はいまだバブルさながらの様相を呈している。なかには、ティファニー銀座本店ビルのように坪単価が1億8000万円を超えた事例もある。
だが、こうした派手な取引は、「Aクラス」と呼ばれる立地などが一流の物件に限ってのこと。華やかな不動産取引の陰で、表通りを一本裏に入ると、すでに地殻変動のマグマがうごめいている。
ある不動産仲介会社によると、「売り圧力のほうが強く、主導権は買いサイドに移っている」という。すでに昨年末から、Bクラス、Cクラス級の物件は、取引が停滞したり、売り手の希望する価格では売却できなくなっているというのだ。ある不動産業者も「今では、10億円未満の物件だと入札をしても誰も飛びつかなくなった」と話す。
そのダメ押しとなるのが、2007年9月末に完全施行された金融商品取引法だ。当局はここ最近、金融機関の不動産向け融資に厳しい目を向けてきたが、金商法で不動産ファンドそのものを締め付ける道具が揃った。