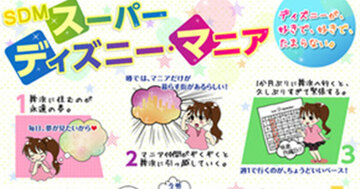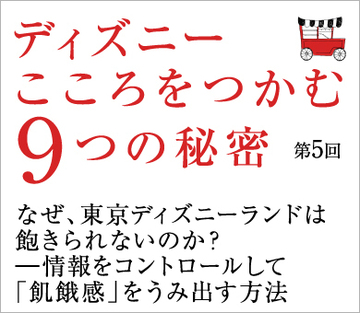それは、関係者自らがUSJを「映画の専門店」と捉え、その考えから抜け出せていなかったことだ。そうしたコンセプトのパークに集まるお客の中心は、本格的な映画の世界を堪能したい「大人たち」だった。本来ならばテーマパークの最大のボリュームゾーンであるにもかかわらず、映画に興味のない子どもの意見に左右されやすいファミリー層は、十分に取り込めずにいた。
映画の専門店からセレクトショップへ
背水の陣を敷いた「三段ロケット作戦」
USJは映画にこだわらないと、東の横綱・東京ディニーランドと差別化できない――。そんな意見も根強かったが、森岡氏は違うと思った。「人がエンタメに使う年間費用は収入全体の1割に過ぎないうえに、東京と大阪の間には交通費という『3万円の川』が流れている。双方はそもそも市場のパイを食い合わない」(森岡氏)。大切なのはゲストを元気にすることであり、フォーマットにこだわる必要はない。映画の専門店から脱皮し、世界最高のエンタテインメントを集めたセレクトショップへと脱皮させる必要があると感じた。
また、「映画の専門店」という自負のもとで、技術志向に囚われ過ぎていたことも課題だった。「たとえば、アトラクションの海賊船に素晴らしい技術と大きなおカネをかけて、映画さながらの超リアルな塗装を施しても、それはお客様の目に『海賊船が古くて汚い』というマイナスイメージに映ることもある」(森岡氏)。こうした事例が散見された。
みんな、一生懸命頑張っている。でもうまく行かないのは、過去の前例に囚われるあまり、技術者のこだわりが、一般消費者の感覚とずれ始めているせいだ。「与えられた経営資源を、技術志向から消費者価値の向上へとシフトさせることで、事業効率だって上げられるはず」(森岡氏)と思った。
こうした課題をベースに考えながら、森岡氏は2010年7月、社運を賭けた大冒険を提案する。リスクを伴うが飛躍が望める「3段ロケット構想」だ。一段目のロケットは子連れファミリー層を取り込むこと。二段目のロケットはそこで生み出したキャッシュをテコに、遠方からゲストを集客できる「ものすごい何か」をつくり、関西依存の集客体制から脱却すること。そして三段目のロケットは、科学的な経営管理法に基づいてパークを効率的に運営するノウハウを、色々な場所に展開して行くこと。
「ハリポタ」構想はこのときでき上がった。その試作モデルを、研修で赴いたフロリダのユニバーサル・オーランド・リゾートで目にし、クオリティの高さに感動した森岡氏は、これを二段目のロケットである「ものすごい何か」に位置づけ、USJにも導入しようと決意したのだ。しかし、そのためにはキャッシュが要る。それを、一段目のロケットである子連れファミリー層の取り込みによって稼ごうと考えた。