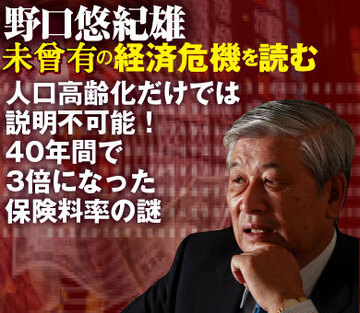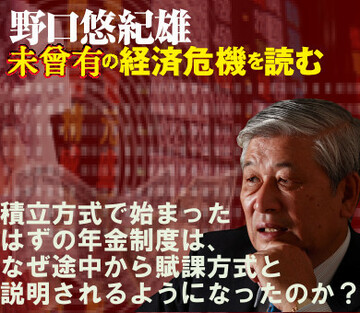11月末に為替レートが円高に動いたことから、為替介入や金融緩和などの必要性が論じられた。
しかし、名目の円ドルレートだけを見ていると、判断を誤る危険がある。以下では、為替レートの評価にあたっていかなる指標を見るべきかを論じることにしよう。
実質実効レートは、
格別の円高にはなっていない
日本経済全体の海外との関係を一般的に考えるのであれば、本来見るべき指標は、実質実効レートである。これは、日本の貿易相手国との為替レートを貿易額で加重平均し、さらに各国間の物価上昇率の違いを調整した指標であり、日本銀行によって算出されている(【図表1】参照)。
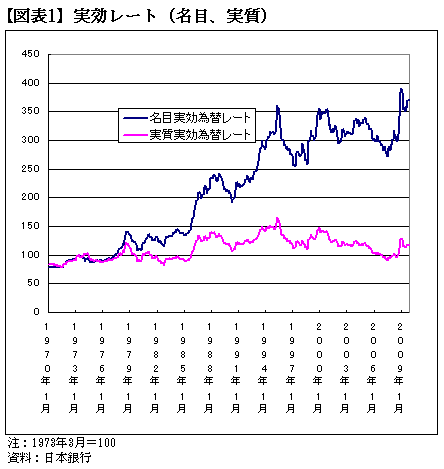
これを見ると、つぎの諸点が指摘される(実質実効レートは、1973年3月を100とする指数で示されている。数が大きいほうが円高であることを示す)。
(1)この1年間程度の短期的な動きを見ると、実質実効レートは、2009年初に128.9であったものが、11月には118.4になっている。つまり、変化は円安方向へのものだ。この間に、円ドルレートは円高方向に動いたが、他国通貨との間で円安が進展したため、実効レートは円安方向に動いたのである。円ドルレートだけを見ていると、こうした全体的な動きを見誤ることになる。ごく短期のみを問題として10月と11月を比較すれば、変化は円高方向だ。しかし、これがどの程度持続的なものかは、わからない。
(2)数年間程度の中期を見ると、07年7月の91.3をボトムとして、円高方向に動いてきたことは事実である。これは、世界的金融危機によって、円キャリー取引(円資金を短期で借り、ドルなどの高金利国通貨に転換して、長期で運用する取引)の「まき戻し」が生じたことが、大きな要因となっている。
(3)ただし、より長期な趨勢は、95年の円高ピークから円安に向かう動きだ。その動きが07年7月をボトムとして終了し、それ以降円高方向に転じたわけだ。円高の進行は急速なものであったために、注目を集めることになったのである。