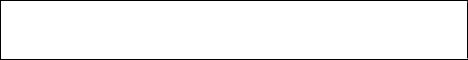“衝撃的”な事実が白日の下にさらされたのは、3月12日に開催された厚生労働省薬事・食品審議会のある会議でのことだった。
今回の新型インフルエンザの流行に際して、輸入されたワクチンは計4950万人分(2回接種換算)。グラクソ・スミスクライン(GSK)製3700万人分と、ノバルティス ファーマ製1250万人分で、合計1126億円だった。このうち、2月8日~3月9日の輸入ワクチンの推定接種者数(出荷ベース)は、GSK製550人、ノバルティス製1938人で、合わせてわずか2500人に満たなかったというのだ。輸入分のじつに99%以上が余った計算になる。
現在、政府と両社とのあいだで契約の一部解約に関する協議が行われており、製品引き渡し期限の3月末までには結論が出る模様である。他国の実績から、3割程度は解約が可能になると見られる。
この解約騒動に乗じて、「輸入ワクチンに頼らずにすむよう国産体制を強化すべきだ」という論調が勢力を増している。
しかし、問題を履き違えてはいけない。必要なワクチン量を政府が輸入も含めて確保したことには合理性がある。ただ、事前準備もなくあわてて確保に走ったため、入荷が2月にずれ込み、大量在庫につながった。主要国の多くが、一定量を輸入できるよう事前購入契約を結び、新型インフルの流行に間に合わせたにもかかわらず、日本はその準備を怠ったのだ。
背景には、一部の厚労官僚や国立感染症研究所などにはびこる“国産至上主義”がある。
仮に新型インフルワクチンをすべて国産で賄うため、国産メーカーに補助金を投入して製造設備を増強しても、設備をほかのワクチン製造へ転用することは難しく、メーカーの投資回収はきわめて難しいとされる。その累積コストを国が丸抱えもできまい。
危機管理上、どのような新型インフルワクチンの確保体制を築くか──。この点の再考こそが大量在庫の教訓とすべきものである。
(「週刊ダイヤモンド」編集部 柴田むつみ)