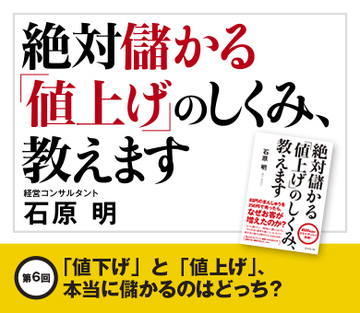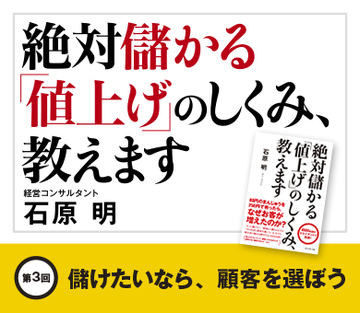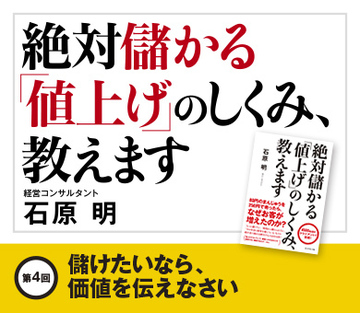高家賃、高原価率、低回転率の「三重苦」
あの男性客が帰ったら、今日はもう午前2時の閉店を待たずに店じまいしてしまおうか。いや、でも常連の出版社の編集長が、1時頃ひょっこり一杯やりに顔を出してくれるかもしれないし……やっぱり、もう少しがんばるか。
洋介がそう思ったその瞬間、店のドアが開いた。
いつもの編集長ではなかった。と入ってきたのは、女性だった。
四十代半ばだろうか、でも若く見える。肩につかないくらいのふわりとしたショートボブ。しなやかな素材のグリーンのワンピースの上に、クリーム色のジャケットを羽織っている。オーストリッチの質の良いトートバックからは、ぶあつい書類がはみ出して見える。そして、黒いキャリーバッグを引いている。
かっこいい女性だな。
それが洋介の第一印象だった。荷物が多いのは、旅行帰りだろうか。
「良かったわ。開いている店があって。ここら辺、この時間どこも開いてないんだもの」
そう言いながら女性は、迷いなくカウンターの真ん中に座った。
「いらっしゃいませ。ご旅行帰りですか?」
洋介がおしぼりを渡し、笑顔を向けると、女性はまっすぐ洋介の目をじっと見つめ、すぐに微笑み返した。
「出張の帰りよ。帰りにオフィスに寄ったら遅くなっちゃった。今日は昼から何も食べてないの。何か食べようかしら」
そう言いながら、女性は店内をぐるりと見回し、また洋介と目を合わせた。
洋介からメニューを受け取ると、真剣な表情で端から端まで目を通している。何をそんなに真剣に見ているのだろう……。
「この店って、前からあった?」
「はい。2年になります」
「そう。気づかなかったわ。引っ越してきて3ヵ月になるんだけど、いつもは隣の道を通るから」
「お近くなんですか」
「そこのタワーマンションよ。でもこの辺り、遅くまで開いてる店が全然なくて困るのよね」
「そうですね、11時過ぎるともう、ウチぐらいですねえ」
「何時までやってるの? この店」
「午前2時です」
「朝は?」
「8時です。モーニングで利用される方が多いので」
「2時に閉めて、8時オープン? いったい、いつ寝てるのよ」
ふふふっと笑う女性に、洋介も合わせるように笑みを返した。
そうなのだ。寝る暇もなく、毎日毎日働いて、それでも……。
「この辺りなら家賃も高いでしょ。それだけでも大変よね。どうしてこの場所に店出したの?」
洋介の心を見透かしたような突然の問いかけに、洋介は一瞬ひるんだ。
どうして、って……。
「まあ、この場所にしては安くいい条件で借りられたんですよ。あとは、東京タワーの近くが気に入って……」
「ひょっとして地方出身?」
「北海道の旭川です。知ってますか? 旭山動物園のある……」
「ああ、それで東京タワーに憧れちゃったんだ」
ズバッと、自分の中にあったこだわりを一言で片付けられてしまった気がして、洋介はなんだかガッカリした。東京タワーに憧れた田舎モン。そうだよ、それが俺だよ、だから何だよ……。
それでも洋介は、ちょっと気を悪くした自分を相手に悟られぬよう、あえてとびっきりの「営業スマイル」で返した。
「まあそんなとこですね」
笑うと、八重歯とえくぼが出る。童顔を隠すためにヒゲを生やしているが、笑うと「かわいい」とよく言われる。
しかし女性は、そんな洋介のスマイルにまったく構わない様子で、今度はメニューを開いて言った。
「メニューもいろいろ種類があるのねえ。オムライスにハンバーグ、パスタもいろいろ、ナポリタン、カルボナーラ、魚介のトマトソース……。えっ? ピザ? パンケーキもあるの? それから、マーボー丼? 親子丼? 五目あんかけうどん!? そんなものまで!」
「え、ええ。常連さんの希望聞いてたら、いろいろと増えまして」
「常連?」
「近くのオフィスの方で、打ち合わせに使っていただいたり、深夜まで仕事して帰りに寄られる方が多いんです」
「……そう」
女性は、メニューから目を離し、奥の席に一人座っている男性客をチラっと見た。
「ご注文はどうなさいますか」
不意に思い出したように、女性が洋介の顔を見る。
「ああそうだったわ。何か食べたいのよね」
「スープカレーが当店の名物ですが……」
そう言うと、女性は目をまるくして、よく通る声で言った。
「カレー!? こんな夜中にそんなもの食べたら胃がもたれちゃうわよ!」
思ったことをズバッと言うタイプの人だな。お腹空いてるって言ったのは自分なのに。いつも思うが、女性というのはまったく矛盾したことを平気で言う。
「そうですよね……。あとは軽めのものでしたら……」
そう言って洋介がまたメニューを開こうとする。すると女性は、またきっぱりした口調で言った。
「待って。やっぱりそのカレーいただくわ。だって、すっごくお腹が空いてるんだもの、いいわよね、今日だけは」
ニコッと洋介に笑いかけた。今度は屈託のない、優しい笑顔だった。洋介はなんだか少しホッとした。
「ありがとうございます」
「それにね」
女性は、その笑顔のまま、カウンターごしの洋介にぐっと顔を近づけて、こう言った。
「お店の名物だったら、自信持ってちゃーんとお客さんに勧めなきゃダメよ」
な、なんだよ、急に。
名物ならちゃんと勧めろ、と指摘されたからなのか、急に女性の笑顔が真正面に近づいたせいなのか。一瞬ドキッとしてたじろいだ洋介を、まっすぐ見据えながら、彼の動揺などまったく気づかない様子で、そのままよく通る声で女性は続けた。
「この店、経営かなり厳しいでしょう?」
「えっ?」
あまりのストレートな言葉に、洋介は接客中ということを忘れるほどうろたえた。
なんなんだろう、この女性。
なんでさっきから、店の中をじろじろ見たり、メニューをくまなく読んだり……。
それでも洋介は、うろたえている自分を見せまいと必死に取り繕った。
「まあ、けっこう家賃高いっすからね」
へらへらと笑って話題をごまかそうとしたが、女性には通じなかった。
「確かに、それもあるけど。あと、このメニューも問題よね」
「メニューですか?」
「こんなに品数増やしちゃったら、たまにしか出ないメニューのために仕入れて結局無駄になって捨てる食材も相当あるんじゃないの? そういうの、『在庫ロス』っていうんだけど。たぶん原価率50パーセントぐらいになってるんじゃないかしら。そもそもあなた、原価率ちゃんと計算してる?」
「原価率って、値段の中に含まれる食材の仕入れ価格の割合ですよね?」
「そうよ。通常の飲食店の原価率はだいたい30パーセント前後ね。ものすごく簡単にいうと、売上から原価を引いた金額が『粗利』になるでしょう? そして粗利から家賃などの経費を引いた額が『利益』、つまり『儲け』になる。
儲けるためには、売上を上げるか、原価や経費を抑えるというのが基本的な考え方よ」
「ああ、でも、僕、原価率を低くして儲けるとか、そういう考え方あんまり好きじゃないんですよね。だって、お客さんのためにならないじゃないですか」
初めてささやかな抵抗をしてみたつもりの洋介だったが、それに対して、女性は逆に優しい口調で、かみくだくように言った。
「あのね、原価率が高いことが悪いっていうわけではないのよ。原価率が高くても、そこにちゃんと戦略があるなら全然問題ないわ」
「戦略? ですか?」