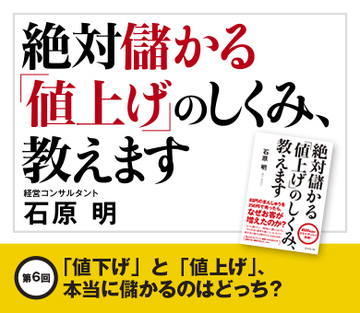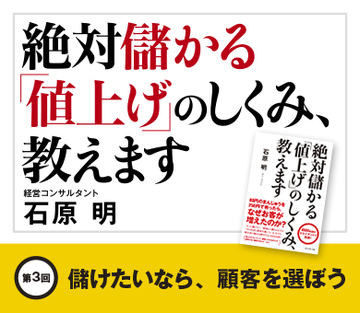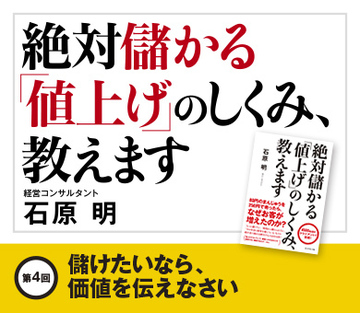儲かっている会社の共通点、それは努力で儲けているのではなく、「儲かる仕組み」があります。
「儲けるなんて、簡単よ」これが口癖の敏腕経営コンサルタントの遠山桜子、45歳。彼女がふとしたきっかけで知り合った、つぶれかかったカフェの店長に「儲ける仕組み」とは何かを、具体的な事例とともに解説するというストーリー。今回、3回連続のこの本の中身をそのまま紹介します!
儲からないカフェ
東京・港区芝。
深夜ともなれば静まりかえるオフィス街の一角に、その店はあった。
店の名前は「カフェ・ボトム」。
前芝洋介がこの店を始めて2年が過ぎた。
2年半ほど前のある日、古い喫茶店が「居抜き」で安く借りられる、というので見に来たのが最初だった。店にほとんど手を入れずに設備類が使えるなら、ありがたい。
最寄りの地下鉄駅の出口から地上に出た途端、洋介の目に飛び込んできたのは「東京タワー」だった。
洋介は、まるで巨人を足元から見上げる子どものように、あごを上げ、口をぽかんと開けて東京タワーを眺めた。
「でけぇな……東京タワー」
北海道の高校を出て、専門学校に進学するために上京してきてから、その時でちょうど10年が過ぎていた。上京したての頃、一度だけ東京タワーの展望台にのぼったことはあったが、こんなふうに日常生活の中に巨大にそびえ立つ姿を間近で見たのは初めてだったかもしれない。
憧れだった「東京」。
そのシンボルともいえる存在。東京タワーを眺めながら毎日を過ごせたら、何か自分が変われるかもしれない。そんな気がした。
この手に、おさめてやる。
そして洋介は、この東京タワーのふもとの町でカフェを始めることを決意した。妻の亜弓も賛成してくれた。専門学校時代からのつきあいだった亜弓には、たくさん心配をかけてきた。学校を卒業してからも決まった職につかずフリーター生活。コンビニ、居酒屋、運送屋、女の子のいる店のフロア係、時給のいいところを転々とした。大きな声では言えないが、知人に声をかけられるままに不動産ブローカーのようなこともしていた。しかし、これがけっこう儲かった。
いわゆる「できちゃった婚」で25歳のときに亜弓と入籍し、娘の果菜が生まれた。羽振りが良いときは調子に乗って遊んだりもしたが、それも長くは続かなかった。
(果菜ももうすぐ小学生になる。そろそろ身を落ち着けて、ちゃんと働こう。)
そう考えていたとき、不動産ブローカーの頃に知り合った業者からこの店の情報を仕入れたのだ。
「カフェ、か。それもいいかもしれないな」
取り立てて飲食店の経営に興味があったかというと、そうでもない。ただ、洋介は「人が好き」だった。フリーターのときも、不動産の仕事のときも、いろいろな人と会って話すのが面白かった。そして、計算しているわけではないのに、ふっと懐に入ってあっという間に仲良くなってしまうような才能が、洋介にはあった。
もうひとつ、洋介には「カレーをつくる」という趣味がある。
趣味というよりも、もはや「研究」に近い。妻の亜弓も大絶賛してくれる、スープカレー。北海道の高校生だった頃からつくり続けている。試行錯誤を重ねて絶妙なブレンドに仕上げ、スパイスを効かせた、さらっとしたスープ。大きな肉や野菜がごろごろと入って、そのスープと調和しているのが特徴だ。今でこそ、スープカレーは北海道の名物みたいに言われているが、
「俺は、流行るより前からつくっている」
と、洋介は自負している。
この自慢のスープカレーを目玉にしたカフェなら、当たるに違いない。
そもそも東京で、スープカレーの店をほとんど見たことがない。若者の街、下北沢に集中して何軒かあるぐらいだろうか。でも、スープカレーは若者だけではなく、幅広い世代の人にもっと受け入れてもらえるはずの食べ物である。そう、こういうオフィス街でも、ランチに出せばきっと流行る……!
洋介は、成功を確信した。そして、そこからの決断と行動はすばやかった。妻の亜弓はパートを辞め、一緒に店を切り盛りすることになった。
心機一転、家族で力をあわせてここでがんばろう。すべてが新しく、希望に満ちた未来がそこに続いているように思えた。
あれから2年。
何をどう間違えて、こうなってしまったのだろう。
午前0時。ダウンライトの薄暗い店内にいるのは、奥のテーブルでコーヒー一杯で1時間半は粘っている男性客一人と、カウンターの中にいる洋介一人。
レジの横のすき間にぐしゃっと押し込んだ「請求書」の束に目をやり、洋介はため息をつく。月末の支払いを思うと、また頭が痛い。
こんなにがんばっているのに、どうして儲からないんだろう。
果菜は、元気にしているだろうか。亜弓は、まだ怒っているだろうか……。
亜弓は、半年前に果菜を連れて実家に戻ってしまった。一人になった洋介は、ついに暮らしていたアパートも引き払い、店の奥の部屋で寝泊まりしているような有り様である。
洋介は小さくため息をついた。