なぜ佃製作所は医療分野に挑んだのか
本の帯にあるとおり、佃製作所は今回、「人体」に向かいます。ロケットの燃料供給バルブ技術を、人工心臓弁に活かそうというのです。「ガウディ計画」と名付けました。
まったくもって無謀です。開発期間の長さや万一のときの補償問題も大変ですが、開発の中心となるべき医師は象牙の塔の派閥争いに忙しいですし、それを越えても役所の壁が立ちはだかって、と事業リスクが高すぎて目が回りそうです。
社長の佃航平本人もそれに戸惑います。思いもかけぬ競合の出現で、本業のロケットバルブの受注も危ういのに……。そしていったんはその共同開発を断ります。経営的にムリだと。
今回、登場人物たちはみんな迷っています。佃航平は経営とは何かに迷い、心臓人工弁の開発者である一村(いちむら)医師は医療とはどうあるべきかに迷い、そして多くの社員が自分たちは何のために、誰の下で働くのか、に悩みます。
強い信念を持っていたはずの「神の手」一村医師すら、ある日呟(つぶや)きます。「医学ってのは、いったい何なんだろうな」
しかしそれに対して、秘書の中野綾は真っ直ぐに答えます。「病気で困っている人を救うものなんじゃないですか」「人の命が目の前にあったら、それをなんとか救おうとする。それが医者じゃないですか」「医者が医者たるのは患者に向き合ったときだと思います」
一村はそれで目が覚めます。自分の心の狭さに気がつくのです。自分の研究を守りたいとしていたこと自体が、それに反する行為でした。彼は覚悟を決めて、仇敵に向かい合います。患者(特に子どもたち)の命を少しでも早く、少しでも多く、救うために。
そして、佃航平も気がつきます。経営とは算盤を超えて、夢でありミッション(使命)なのだと。
ミッションは机上にはない。現場にある
まったくの私見ながら、『ガウディ計画』での本当の主人公は佃航平ではなく、若き開発担当者 立花洋介です。まじめさが取り柄で口数が少なく、当然台詞(せりふ)も大して無いのですけれど……。
彼は途中、人工弁の開発に行き詰まり、上司に訴えます。開発者である一村医師の下に行くために、福井に出張させてくれと。
「実際に見てきたいんです」「我々が開発しているものが果たしてなんであるのか」
福井出張は認められ、そして同僚とふたり、一村医師の心臓手術に立ち会います。それは、男の子の命が救われた瞬間でもありました。そのとき立花たちは、その「進むべき道」を確信するのです。
その「想い」こそが、この物語の最後の扉を開く力となります。どうしても開きそうになかった役所の厚く重い扉が、立花の熱い想いによって開かれるのです。
読み終わって思います。ああ、こんな仕事をしたい。こんな想いで働きたい。ただ一度の人生だから。
そんな夢やミッションが、ロケット部品の世界だけでなく、医療の世界にも確かにありました。だからこそ、佃製作所は、そして『下町ロケット』の舞台は、そこへと移っていったのでしょう。作者の思惑を超えて。
と思っていたら、前作『下町ロケット』の最後には、佃航平のこんな台詞があるじゃないですか。
「人工心臓、か……」「おもしろいじゃないか」
う~っむ、参った。池井戸潤の神算鬼謀、恐るべし。
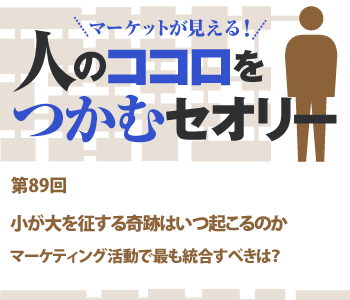


![半沢直樹シリーズ最新作!池井戸潤『銀翼のイカロス』[試読版]【序章】ラストチャンス(第1回)](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/0/4/360wm/img_0468e854bc9f4dd7cb89e7f9585db8cb228135.jpg)