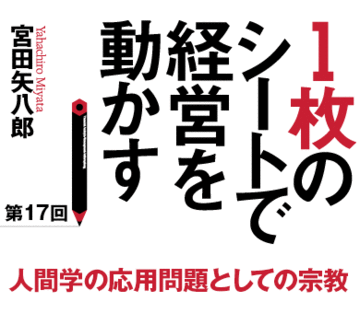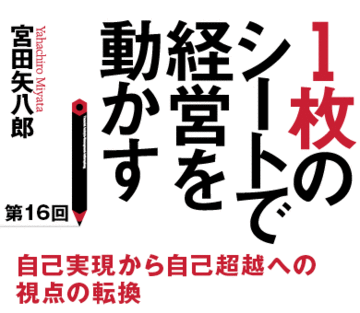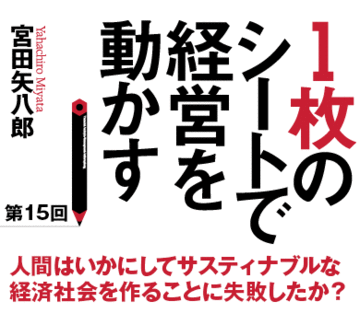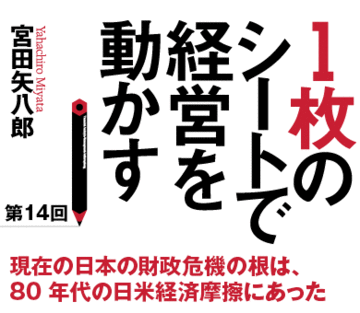仏教の核心は釈迦の解脱です。ここでその思索と実践のプロセスに迫りたいと思います。それによって、本連載がテーマとしてきた自己超越という現象が、どのようにして人間にもたらされるのかを具体的なプロセスとして跡付けてみたいと思います。同時に、次回のテーマですが、ここで明らかになった事実をキリスト教と比較すれば、キリスト教の本質が浮き彫りにされると予測します。
このような狙いを念頭に置いて整理するのですが、私の理解によれば、釈迦の解脱は次の五つのステップによって達成されました。表の右側にはその内容とこれを説明するキーワードを示しています。
これら5ステップを理解するためのキーワードの解説を以下で行います。
【考】
●四苦八苦:生老病死が四苦、これに愛別離苦、怨憎会苦、求不得苦、五蘊盛苦(五蘊とは、色=形あるもの、受=感受作用、想=表象作用、行=意志・形成作用、識=識別作用という肉体・感覚(=色、受、想、行)と認識(=識))の集合体としての人間。これら構成5要素への執着が苦しみの元)を加えて八苦。釈迦の求道がここから始まることを肝に銘じたい(注1)。
●十二支縁起:無明(根源的無知)→行(潜在的形成力)→識(意識・心)→名色(心と体・世界)→六入処(眼耳鼻舌身意の六根。これが機能すれば、色声香味蝕法という境を得る)→触(接触)→受(感受作用)→愛(愛執)→取(執着)→有(業と報の存在)→生→老死。
苦の連鎖を断ち切るために生老病死という苦しみをもたらす因縁果のプロセスを逆に遡って行くと、究極原因たる無明に至る。
無明の裏側は光明、真理、智慧であり、既出の言葉を使えば涅槃です。光明、真理、智慧、涅槃は結果の世界であり、人間の手が届く究極のプロセスはひとつ手前の「行」です。
【断】
この項だけ、十二支縁起に関連させて【考】の中に挿入して説明します。
●行・潜在的形成力:「行」は非常に重要な概念で、釈迦の言葉の最初期の記録『ブッダの言葉 スッタニパータ』では「潜在的形成力」とあります(例えば、730,731等)。その次のステップに「識(意識、心)」があることを考えれば、これは要するに本能レベルの力で、生存への盲目的意志――その結果が食欲、性欲、睡眠欲等――とでも称すべきものです。
とりわけ、人間にとって最も身近で大きな苦しみは「倫理無縁の性欲」――色欲、色情――に振り回されることで、『真理のことば ダンマパダ』では第24章で「愛執」(愛欲、渇愛、欲情とも表現されている)なる一章を設け、色欲、色情を断ち切ることを繰り返し述べています。
一方で考えられることは、色欲は十二支縁起後段の「触→受→愛→取」の中で生じる本能的欲求とこれへの執着と整理すべきかもしれないということです。しかし、十二支縁起が単純な一本線のプロセスではなく、多層併行のプロセスとも考えられ、そう見れば文脈的には、「行」の中に色欲をもって来ても間違いではないでしょう。
そこで、「行」の本質ですが、本能レベルの欲求のそのもうひとつ奥にある、自己の生存のためにすべてを正当化し、自分を優先する盲目的な生存本能、これが「行」の本体です。この、生の根源にあって、自己の生存を最優先しようとする生への盲目的な意志、これは哲学や洞察で解消できるものではなく、断滅すなわち解体的死滅をもたらすものが必要です(注2)。
とは言いながら、どのようにしてこれに解体的死滅をもたらすかに関しては、初期の釈迦の言葉にも明瞭ではなく――例えば『感興のことば ウダーナヴァルガ』から引用すれば、「人々は自我観念に頼り(中略)それを(身に刺さった)矢であるとはみなさない」(第27章7)、「賢者は、自分の身をよくととのえて、すべての悪い生存領域を捨て去る」(第23章24)。ちなみに「悪い生存領域」とは修羅・畜生・餓鬼・地獄をいう――、突然の飛躍のような悟りと解脱の体験告白へと展開します。これをどう解したら良いのでしょうか?(注3)
恐らく釈迦自身も「直観智」(『感興のことば ウダーナヴァルガ』第33章47)としか言いようのない、理解を超えたところで得られた解脱の境地を味わい、その後に、それを迎えさせたであろうはずの経験と洞察を可能な限り示したのだと思われます。
そこで、【考】に戻ります。
●四諦:「諦」とは真理の意味で、苦・集・滅・道の四つの真理を四諦と言います。苦諦とは人生の真相は苦であること。集諦(じったい)とは苦の原因は「渇愛」、すなわち執着であること。滅諦とは苦の根源たる「渇愛」から離れ、これを滅し、捨て、解脱すること。道諦とは解脱への実践道たる八正道(後述)を踏むべきこと。これは十二支縁起の逆観の、別の説き方でもあります(『感興のことば ウダーナヴァルガ』第26章18)。
【定】
●禅定:身体化の方法論です。腰立の姿勢で呼吸を数えつつ(数息観)複式呼吸をする。意識の暴走、空回りを抑え、精神集中によって意識と身体の融合・一致をもたらす――「定」――。後述する八正道のひとつです。
●止観:いずれも坐禅の具体的内容であり方法論です。「止」とは意識の暴走を止め思考作用を伴わない精神の集中状態――正念――に至ること。「観」とは変転極まりない世界(=色)とこれに振り回される意識(=名)とを、「身は不浄、受は苦、心は無常、法は無我」(四念処)と洞察することにより切り離し、世界と人間を感情を交えないでありのままに見る智慧、「名色分離智」――正知――を体得すること4)。
止観は天台智顗(538~597。中国は南北朝時代の人で天台宗の大成者。『天台小止観』、『摩訶止観』等の著作がある)によるもので、意味としては禅と同じで、したがって概念自体は初期仏教にあった。例えば、原始仏教の経典たる『大念処経』(長部22)。
●自己不在:バラモン教(ウパニシャド哲学)から釈迦が離れたのは、我(=自己:アートマン)の実在を言うバラモンの「梵我一如」の哲学に対して「自己不在」と見極めたことによります。
第8回 自己の実相で述べましたが、西洋哲学が遂に到達できず誤解して来たように――例えば「我、思う。ゆえに我、在り」とデカルト――、究極実在の可能性のある意識は、意識という機能を有しても本来、独立・自存する存在――実在――ではない。十二支縁起におけるその一つ手前の「行」に依拠して、欲望に支配される自己が実在すると錯覚するが、注4に述べるように「行」を捨断すれば実在するのは涅槃の世界で、そこには、我ならぬ「不生のもの」があるだけ――釈迦の涅槃体験――と悟りました。ここで釈迦は「自己不在」の真理に到達しました。
【道】
●三毒六煩悩:貪(貪り)・瞋(怒り)・痴(迷妄)が三毒、これに慢(傲慢)・疑(不信)・悪見(誤った思想)を加えたものが六煩悩。十二支縁起の「触→受→愛→取」のプロセスで常軌を逸し苦に支配される人間の姿が出て来ます。これらの煩悩が苦を生みます。これが六道(天、人間、修羅、畜生、餓鬼、地獄)輪廻と呼ばれる人間の苦しみの姿となります。
次の八正道と併置したのは、この煩悩が苦を生み、苦を増し加えるからで、八正道の実践は逆にこれを滅尽することによって悟りと解脱への道を準備するからです。
●八正道:既述の道諦の内容が八正道で、解脱を導く実践道です(『感興のことば ウダーナヴァルガ』第27章34)。正見(正しく見る、智慧の眼)、正思(正しい思索)、正語(柔和な、正しい言葉)、正業(誤った行いの捨断)、正命(あらゆる邪な生活からの離脱、捨断)、正精進(怠惰を排し精励努力する)、正念(心の不亡失)、正定(心の集中状態)です。
【脱】
●解脱:このように見て来れば、解脱の要点は「行(潜在的形成力)」と「識」の切り離しにあり、繰り返しになりますが、その中心は盲目的な生存本能と化した自我の根切り――キリスト教的な表現かもしれませんが――をどう行うかとなります。忌避でもなく抑制でもなく、心における捨断であり死滅です。ここが解脱成否の分岐点となります。
前提なき探求者たる釈迦にとって、解脱が何であるかはそれがもたらす結果によって評価されます。心の中に相争うものが一切なくなり、平和と静寂がもたらされた。同時に、これが人への温和な態度として表に出てくる。この驚くべき「境涯の変化」を釈迦は涅槃と表現しました。彼はここで探求の重荷を降ろしたのです。
●涅槃:涅槃を知ることが自己超越であり自己超越の世界に入ることです。この自己超越の世界は実在するもので、釈迦はこれを知ることによって輪廻から逃れたと述べています(例えば、『ブッダのことば スッタニパータ』436、730)。別の個所を引用すれば「不生なるものが有るからこそ、生じたものの出離を常に語るべきであろう。作られざるもの(=無為)を観じるならば作られたもの(=有為)から離脱する」(『感興のことば ウダーナヴァルガ』第26章21)。縁起や輪廻の根底にある実在とそれを知る境涯とを忘れてはいけません。
このように眺めてくると、仏教がどのような特徴を持っているかわかります。第一に苦しみを生み出す「人間・世界」構造の徹底した思索と洞察、第二に苦しみから離脱するための人間の条件の徹底した整備――意識と身体の結合法としての禅定と八正道――、第三に苦しみの根源たる欲望――その最深部にある盲目的な生存本能に支配された自我――の捨断、第四にその結果としての自己超越、釈迦の言葉では涅槃の体得です。
注目すべきは、第三と第四のプロセスは神秘とも言うべきもので、その前後は言語表現できても、その核心は体得、体験するしかないのです。そこは手を取って教えられるようなものではありません。しかし、その手前の極限までは頭と身体と心のすべてを動員して肉迫するのです。その探求プロセスの広さ・深さは他の宗教・文化の比ではないように思われます。
そのようなわけで、繰り返しになりますが、恐らく釈迦自身も6年間の修行・探求の中のどれが端的に自らを解脱・悟りに導いたのかは明瞭ではなかったのです。ただ、解脱の結果たる静かな喜びと充足、解放があった――冷暖自知――。それ故に、後世のために、解脱に導いてくれたであろう自らの探求のすべてを言葉として残したのです。
灼熱の
猛暑の中の
解脱かな
結論です。このようにして仏教が悟り、あるいは解脱と言われる「境涯の変化」を修行の大きな到達点としていることは間違いないでしょう。これが仏教における自己超越で、釈迦はこれを人に教え導くことにその後の45年の生涯を、費やしたのです。
1.釈迦の求道の出発点にあったのはバラモン教の伝統――輪廻転生の思想――であり、ウパニシャドの哲学――梵我一如――でした。「生存の燃える大車輪」(『真理のことば ダンマパダ』146)から逃れて人間問題の究極の解決を得るにはどうするか?
釈迦の修行は当時の伝統に則りまず坐禅に行ったが、坐禅至上主義の限界を悟り、次に苦行の6年間を過ごしたが、苦行もまた悟りの道でないとしてこれを捨て、よく知られている乳粥の供養を受けた後、49日間の禅定瞑想の中で解脱を得た。
2.人間苦をもたらすものの要約が三毒六煩悩です。これを仔細に眺めれば、ひとまずは「貪」の究極が色欲、「瞋」・「痴」・「慢」・「疑」・「悪見」の究極にあるものが自我と捉えられますが、本文でも検討したように、よくよく見つめれば自我こそが人間と宇宙の究極の問題であるとわかります。「貪」の放縦があるのはこれを許す自我あってこそだからです。自我とは「行(潜在的形成力)」と絡み合った「識」のことで、これが「誤れる自己意識」へと変態し、これを悪の根源として明るみに出して、その断滅を図るというのが仏教の修行の核心のようです。そこに、「行」と「識」の切り離しという仏教のメインテーマがあります。
3.悟り、救いの内実は「境涯の変化」にあり、これと真理に関する認識とは別物です。仏教はその体得のための宗教で、そのための修行体系に特徴があり、キリスト教的な真理の認識には、人間知性の及ばぬものとして距離を置いています――釈迦の「無記」――。
4.参考までに、止観と解脱の関係を図解します。