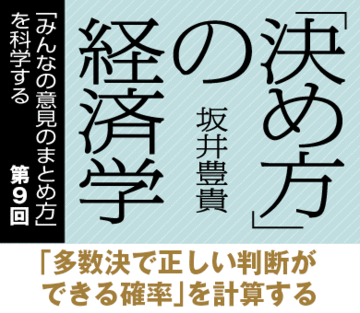皆で何か1つの結論を出すとき、私たちはよく多数決を使う。ときには自分の意見とは違う結果を受け入れないといけない。しかし、なぜそのようなことが許されるのだろうか。多数決や選挙といった「決め方」の意味を経済学的に鮮やかに解説した名著『「決め方」の経済学――「みんなの意見のまとめ方」を科学する』の一部を抜粋し、多数決の正しい使い方について考える。(『「決め方」の経済学』から一部を特別に公開しています。初出:2016年8月1日)
なぜ少数派は
多数決に従わないといけないのか
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
安部公房の短編小説『闖入者』では、一人暮らしの男のアパートの部屋に深夜、9人の見知らぬ家族が押しかけてくる(注1)。そいつらはその部屋を自分たちのものだと主張する。
侵入された男が当惑するなか、侵入者のリーダー格である蝶ネクタイの紳士は会議を始めると宣言、「この部屋がわれわれのものであるかないか」と議題を切り出す。「むろん俺たちの部屋さ」との声が周囲から上がり、ほかの侵入者たちはそれに「異議なし!」と応答。
侵入された男は「これは何の真似だ、下らない」と文句を言うが、蝶ネクタイの紳士に「君は民主主義の原理である多数決を下らないと言うのか」と言葉を返される。
この多数決は暴力的だ。他人の住居に不法侵入のうえ、多数決を持ちだして、そこを乗っ取ろうとしている。まともじゃないが、まともじゃない連中なだけに、そいつらが多数派だと、抵抗するのは容易ではない。
実際この小説では多数決のあと、侵入された男は、侵入者たちに早く出ていけと要求するものの、彼らに取り押さえられ殴られて気を失う。
この侵入者たちほどあからさまでないにせよ、多数決の結果を実行するのに、暴力はつきものだ。法律を破ると、ときに警察に捕まったり、刑務所に収監されたりするが、あれが可能なのは、警官や刑務官の暴力が抵抗者より強いからだ(武術や武器や兵器が質量ともに勝る)。
そこまで明白な暴力ではなくとも、多数決の結果に従わないと会社をクビになるとか、地域で村八分にされるとかは十分に暴力的であろう。『闖入者』の多数決の暴力性がわかりやすいのは、たんにその暴力性を包み隠していないからだ。
多数決の根本的な問いに、「多数決の少数派は、なぜ多数派の意見に従わねばならないのか」がある。従わないと罰されるから従うというのは、従うべき、とは違う。それは罰する暴力に、やむなく服従しているだけだ。では多数決は、どんなときに暴力以上の価値を伴うのだろうか。
多数決が
暴力以上の価値を伴うとき
陪審定理(第9回を参照)はその問いに1つの答えを与える。一揃いの前提条件が成り立つとき、多数派の意見のほうが皆にとって正しい確率が高い。
陪審では皆に共通の目標がある。被告が罪を犯したなら有罪、そうでないなら無罪と判断することだ。だから多数決で少数派になった陪審員も、多数派の意見のほうが正しい確率が高いのだから、それを皆の結論とすることは彼の目標にかなう。多数派に従うということにはならない。
自分の意見が誤っている確率が高いと判明した以上、それに拘泥するのは彼の目標に反してしまう。
投票者たちに共通の目標があるからこそ、皆でどちらが正しいのかを問える。陪審ではない多数決でも、それがあるなら、陪審定理の理屈はそのまま適用できる。
例えば、立法や政治についての多数決だと、その対象が「私たちに必要か」と人々が公共的に問える、いわゆる共通善に関するものなら、陪審定理の理屈を適用できる。人々の利害対立が鋭く各自がバラバラの方向へ「私にとって必要なのか」と問う多数決へは、適用できない。