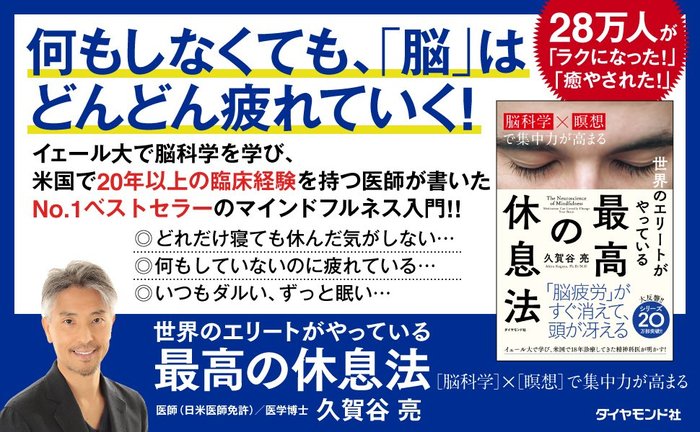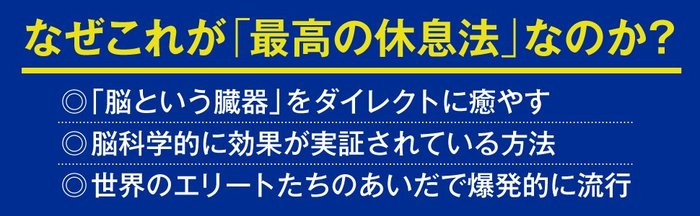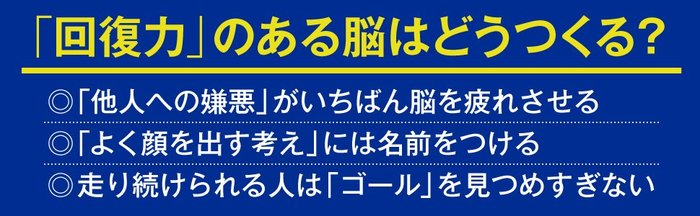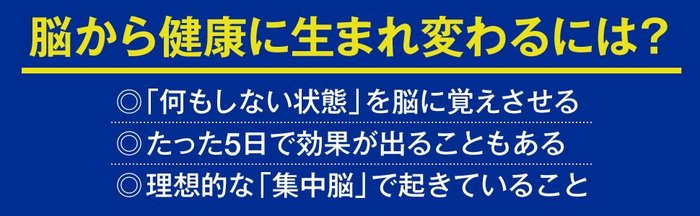「それでまた、どうしてこの老いぼれのところに戻ってきたんじゃ?」
私の苦い回想を見透かしたかのように、ヨーダが尋ねた。
「それは……」
早い話が私は「敗北」したのだ。
世界から集まった一流の若手研究者たちのあいだで、私は結果を出せなかった。
先端脳科学研究室は、神経がすり減るような激しい競争環境だった。
ある日、やっとの思いで苦しみながら申請したグラント(研究助成金)の審査に落ちたとわかった瞬間、あろうことか私は研究室でパニック発作を起こしてしまった。涙、嗚咽、過呼吸が続き、たまらず私はその場を逃げ出した。
それ以来、張り詰めていた緊張の糸が切れた私は、研究室にも顔を出さなくなり、下宿にひきこもった。食事も喉を通らず、廃人同然になっていた。
「(このまま日本に帰ったほうがいいのかな……)」
何度そう考えたことだろう。だが、決してそうするわけにはいかない理由が私にはあった。「ほら見たことか」と言わんばかりの父の表情が脳裏をよぎる。そう、絶対に帰るわけにはいかないのだ。
(次回に続く)