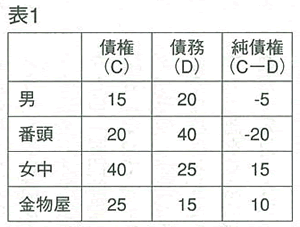「はてなの茶碗」あるいは「茶金」という題名で知られている古典落語がある(*1)。
昔、京都に茶道具を商う金兵衛という人がいた。人呼んで茶金というこの人は、京都では知らないものはいないという優れた目利きで、一見しただけで道具の素性がわかる。茶道具の鑑定を頼まれても、それがよほど優れたものでなければ見向きもしない。茶金が興味を持って見れば十両、さらに手にとって細かく見るならば、その茶道具にはすぐさま百両という値が付いたという。
ある日、この茶金が清水寺に詣で、音羽の滝の脇にある茶店に入って茶をすすったあと、使った湯のみ茶碗を持ち上げて上下左右から返す返す眺めたあげく、はてなと首を傾げてから台に置き、脇に茶代を置いて立ち去った。それを見ていたのが茶店の主人と、その場にたまたま居合わせた、行燈用の油を売り歩く商人。茶金が舐めまわすように見るとは、数百両の価値がある掘り出し物に違いないとみた油売りは、全財産の三両を出して、しぶる親父から半ば強奪するように茶碗を買い上げた。
これでひと財産できると、油売りはこの茶碗を持ち意気揚々と茶金の店に乗り込んだ。ところが、これは清水焼でも一番安物の茶碗で、茶道具としてはまったく何の価値もないと茶金は言うではないか。返す返す眺めたのはこの茶碗が漏ったからだ。ぽたりぽたりと茶が漏るので割れているのかと調べたが、いくら注意して見ても細かな傷さえ見つからない。不思議なことがあるものだと思って、はてなと首をかしげたのだと言うのである。
驚いた油売りは、手に取るだけで百両の値段が付くという、誰もが知っている鑑定の名人が、人前でむやみやたらに首などひねるものではないと怒るが、もう取り返しはつかない。ただし、全財産をかけて勝負をするほど自分の鑑定能力を買ってくれたのを嬉しく思った茶金が、油売りに三両を貸して、その借金のかたに茶碗を預かるということで話がついた。
しばらくして、このような面白いことがあったと、とある貴族に茶金が話をしたのがきっかけで、その不思議な茶碗を見たいと、時の帝が茶金を召しだした。御所で茶を注いでもやはり漏る。実に不思議な茶碗であると帝もたいそう面白がられ、この茶碗を「はてなの茶碗」と命名して、畏れ多くも自筆で箱書をされたものだから、たちまち千両の値段がついて茶碗は売れてしまった。茶金から半分の五百両を受け取った油売りは、もっと大儲けをしようと、今度は大きな水がめの漏るのを買ってきて、噺が落ちる。
*1:参考「はてなの茶碗」『特選!!米朝落語全集 第五集』(EMI MUSIC JAPAN 1989年)