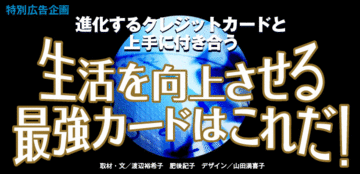広告企画
東日本大震災の発生によって、内陸部の断層における直下型地震の発生確率が高まったとされる。首都直下型地震が発生すれば、人口集中による複合災害が発生し、大きな被害は確実。・・・

世界最大やアジア最大の展示会・見本市が数多く開催される香港。中国や欧米など世界中から出展者やバイヤーが集まり、海外向けの販売や海外からの調達が効率よくできる。日本から飛行機で4時間と近いのも魅力だ。
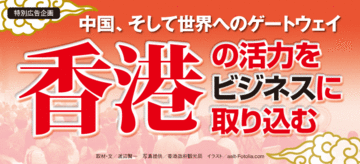
ろうそく、白熱灯、蛍光灯に続く第4世代照明の普及が加速している。その主役はLEDだ。節電意識の高まりから、一気に需要が拡大した。野村證券グローバル・リサーチ本部の横山恭一郎氏に市場の動向を聞く。
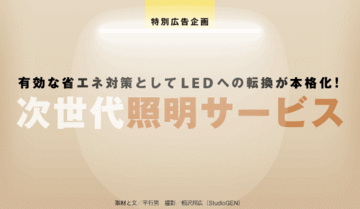
倉庫業は、時代の経営環境の変化に合わせて、その役割を多様化させてきた。顧客企業のロジスティクスを一括して受託する3PL(3rd Party Logistics)企業へと成長。必要に応じて、他業種の事業をも展開し、顧客のニーズに常に応えている業態である。
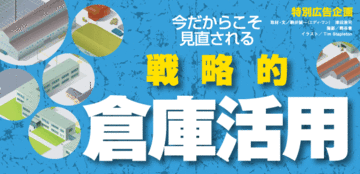
長引く景気低迷のなかで、企業の人材育成がなかなか進んでいない。人材育成の重要な手段である「研修・セミナー」を含むOFF-JTに焦点を当て、現状と今後を探る。

「演劇には、もともと老いや死をどのように受け入れていくかというシミュレーション的なところがある」。混迷の時代、生と死の予行練習を舞台で表現し続ける平田オリザ氏に、理想の葬儀のかたち、生と死に対する思いを聞いた。
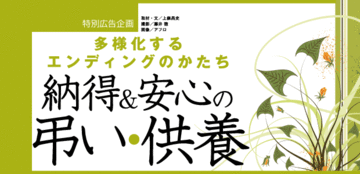
大卒予定者の就職難が伝えられる一方、求職・求人のミスマッチが指摘されているなか、就職に成果を上げている大学も少なからず存在する。国も大学の優れたキャリア形成支援には財政サポートなどを行っている。

コスト削減の意識を定着させ長期的に効果を生み続けるために、企業にはどのような考え方、アプローチが求められるだろうか。ローランド・ベルガー日本法人会長で早稲田大学ビジネススクール教授の遠藤功氏に聞いた。

「IT力」が社会人に欠かせない基礎的な素養となりつつあるなか、経済産業省と情報処理推進機構(IPA)は、「ITパスポート試験」を2009年から実施している。その概要についてIPAに聞いた。
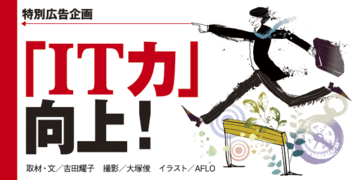
ノーベル賞の常連といえるほど、日本の科学技術の水準は高い。その知を育む理工系大学は有為な人材を社会に送り続けている。理科離れがいわれる子どもたちが日本の科学技術継承者となるにはどんなサポートが必要か。サイエンスコミュニケーターの内田麻理香さんに聞いた。
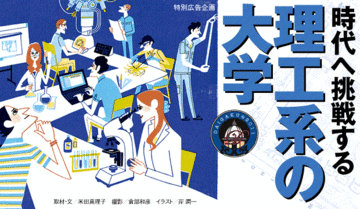
マンションの資産価値を維持・向上していくには、大規模修繕工事が必要だ。しかし、自分たちの共有資産を他人まかせにしているだけで本当にいいのだろうか。大規模修繕にまつわる大事なポイントを紹介する。
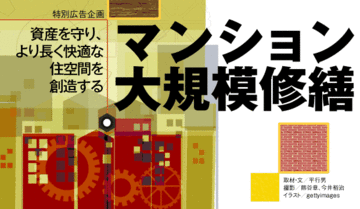
個人利用が広がるスマートデバイスだが、ビジネスで活用するには相応のセキュリティ対策が必要。小型なので盗難・紛失に伴う情報漏えいの危険性もある。企業に求められるセキュリティ対策とは?
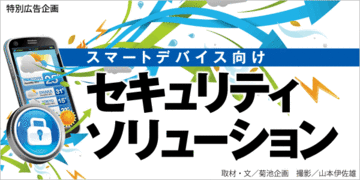
東日本大震災後に広まった自粛ムードにより海外・国内とも旅行者数が落ち込み、観光産業は大きな打撃を受けた。しかし手控えの反動もあり、夏休みを前に回復の兆しがうかがえる。夏秋の最新旅事情を紹介しよう。
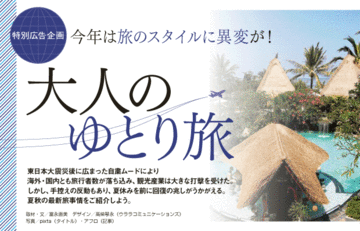
日本人の平均寿命は、男性79.59歳、女性86.44歳(2009年)。健康で生活できる期間も延びており、セカンドライフに対するライフプランの構築はもはや必要不可欠といえる。そのなかでも、シニア時代を安心・安全に過ごすための住まいが重要になる。
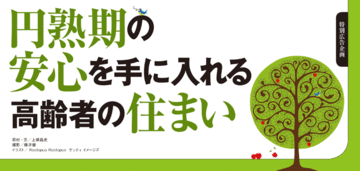
循環型社会構築に必要なのは「人と人のつながり、場の形成だ」と説くのは、立教大学・見山謙一郎特任准教授。ネットワークを結びながら発展する環境対策「日本型モデル」へのアプローチを聞いた。

受験生の大学選びの基準が変わりつつある。偏差値だけではなく、その大学らしい特色、つまりブランドに注目し始めているのだ。各大学も多様な取り組みで応えている。

東日本大震災後、BCP(事業継続計画)見直しや節電対策が急務になるなか、ネットワークを介してITリソース(ハード、ソフト)を利用できるクラウドの有用性が注目されている。その背景を探る。
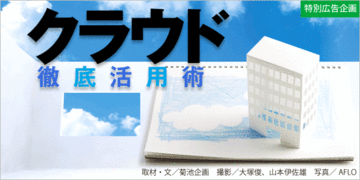
日本のさまざまな組織が今、リスクマネジメントの再考を求められている。複雑化する社会は、その一方で脆さも内包している。そんな現実を直視し、新しいリスクマネジメントを構築する必要がある。

『サービスの達人たち』などを執筆、サービスを提供する人びとを長年にわたって取材してきたノンフィクション作家・野地秩嘉に聞く上質なサービスとは何か?
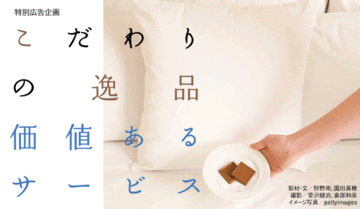
自分に合ったカード選びは、ビジネスシーンだけでなく、ライフスタイルも充実させるはず。自分の消費パターンをまずは分析し、おカネの有効な使い方をいま一度、確認しよう。