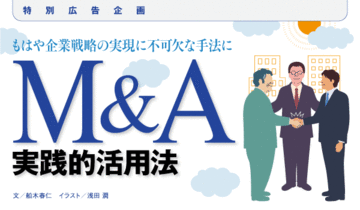広告企画
厳しい財政事情を背景に、このところ公的な医療・介護保険は見直しが繰り返されている。そうした制度の変化に着目し、今年は新しいタイプの保障や契約形態の保険商品が続々と発売されている。新しい保険のトレンドは「生きるための保険」が充実してきている、ということ。「生きるための保険」とは何なのか。従来と何が違うのか。保険の最新トレンドに迫った。
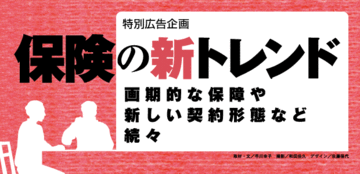
今オフィスに、「コスト削減」「IT普及に伴う働き方の変容」という二つの大きな変化が起きようとしている。この二つの変化を併せて考えていくと、オフィスの効率化を実現するための選択肢が見えてくるはずだ。

グローバル化の進展を受けて、人事制度の再構築を迫られている企業は多い。一方、以前に増してストレスを感じている社員のメンタル面でのケアも重要な課題。これらの課題の解決策について、慶應義塾大学総合政策学部の花田光世教授に聞いた。
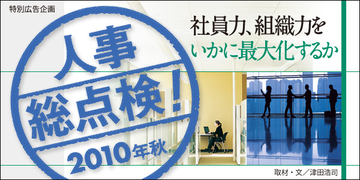
長期優良住宅とエコ住宅の推進。中古・リフォーム市場の拡大。次々と打ち出される国の住宅政策は、今後日本を「ストック型社会」に導くものだ。北野大・明治大学教授に、自身の住宅遍歴や専門の環境化学的見地から話を聞いた。
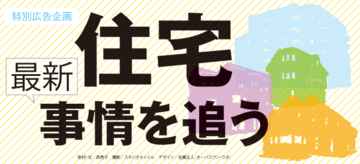
10月31日に羽田空港が国際化し、首都圏の空港事情が大きく変わる。出発到着の時間帯が拡大、就航エアラインも増加。より効率的で快適なビジネストラベルを実現するための最新情報を紹介しよう。

健康への影響により注視を浴びるたばこ産業。だがそうした状況下で、社会からの要請にも対応を果たしながら業績を伸ばしているのがフィリップ モリス ジャパンだ。独自の発想で人材育成に取り組む同社は、トップランナーの育成に、いかなる姿勢で臨んでいるのだろうか。
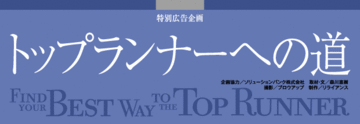
景気の浮沈に関係なく、一定ボリュームの新卒採用と中途採用を維持してきた三井物産。長い歴史を紡いできた同社の、独自の人材観とは? 金融界から農業ビジネスへと転身して国際的な成果を上げている工藤仁氏の体験を基に検証してみよう。
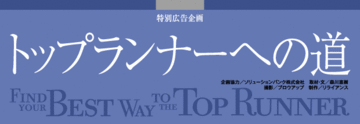
10月31日、羽田に国際定期便が就航する。先駆けて新国際線旅客ターミナルがオープン。成田や関空からも新顔のエアラインが就航するなど、新たな時代を迎えたエアポートの最新事情を紹介。
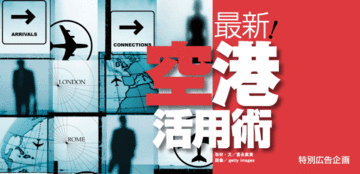
マカオを訪れる観光客は年々増加している。それに合わせ巨大リゾートホテルやアミューズメント施設も続々誕生し、華やかな話題が引きをきらない。いまやマカオは東洋きっての魅力ある旅のデスティネーションだ。

近頃、「優良な有料老人ホームに入居することはステータスである」という話を聞く。元気なうちは、自由で活動的な生活を楽しみ、介護が必要になったときは医療と介護のセーフティネットに身を任せる。自立型有料老人ホーム(介護付き)には、自立した高齢者にとっての理想の生活がある。
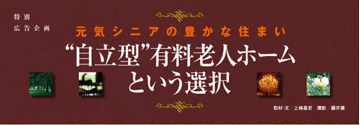
今春施行となった改正省エネ法は、低炭素社会実現に向け、「企業への規制」色を濃くしている。企業はこの事態を、どう乗り越えていくべきか。電力の話題を中心に、住環境計画研究所の中上英俊所長に聞いた。

ビジネス環境の変化はますます加速している。そんな時代に求められるのが、環境変化や経営状況を正しくとらえるための手段。そこで注目を集めているのがBI(Business Intelligence)やBA(Business Analytics)だ。

集中投資が危ういのは誰でも想定できるがリーマンショックで身に染みた教訓は「分散投資でも報われないことがある」ということだった。 しかし分散のしかた次第では、急落に強く利回りも狙うことも可能になる。
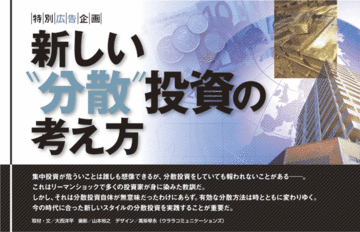
海外に市場を求める企業の動きが加速し、国内工場の役割が変わってきている。一方で、環境・エネルギーや航空機など、新たな産業集積に向けた動きも出始めてきた。各地域では、時代と企業のニーズを先取りした戦略のもと、新たなビジネスステージとして魅力のある事業用地を整備し誘致活動を展開している。
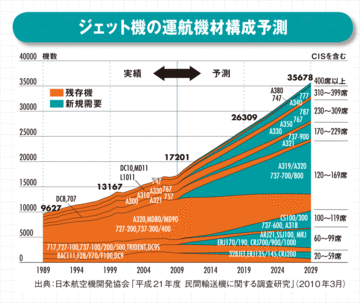
グローバル化と情報化の進展、そして環境意識の高まりと消費市場の成熟。難しいかじ取りが求められる経営環境のなかで、ロジスティクスをどう位置づけるのか、その戦略的アプローチが企業の優勝劣敗の鍵を握る。

高い就職率を維持している大学が確かに存在する。それらは、入学後の早い時期から、社会に出て生きるという実践的なカリキュラムが組み、ビジネススキルの習得やカウンセリングなどに独自の工夫を凝らしている。そんな、「就職力のある大学」の特色と社会に役立つ人材を輩出する取り組みの実際を探っていこう。
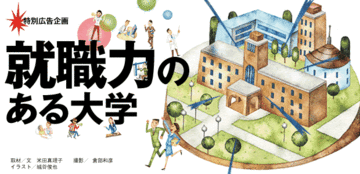
高齢社会となり、また価値観の多様化が見られるなかで、葬儀のあり方も変化している。死に関して無自覚になったといわれる現代人にとって、葬儀とはどうあるべきか? 今あらためて、現代のとむらいや供養のかたちを考えてみたい。
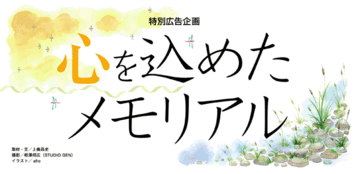
知的財産の価値が企業のみならず、国の発展に大きく関与することは前世紀末から言われ続けてきた。だが、欧米など知財先進国との格差はいっこうに縮まっていない。背景には「知財」そのものよりも、これを「活用」する仕組みの不備があるという。はたして、真の問題点は何なのか。知財マネジメント研究の第一人者である妹尾堅一郎氏に聞いた。
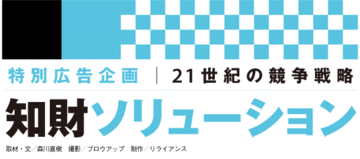
企業の規模を問わず、グローバルな成長市場・分野へのM&Aが目立つようになってきた。それは業界再編への対応というのではなく、まさに生き残りや新たな成長ポテンシャルの確保を狙いとしたものだ。