記事検索
「数学」の検索結果:2381-2400/2844件
英国は中国へ熱烈なラブコールを送り続けている。表面的なプライドを捨ててでも中国とのパイプを太くしたがっている。ドイツもそうだ。

第4回
米国では、日本の生活保護制度はどのように見られるのだろうか? 筆者が米国で2015年2月に行った、生活保護基準に関する学会発表の様子からレポートする。
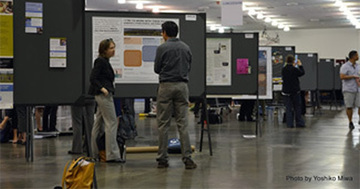
第22回
能力的にも、人間性にも何の問題もないのに、「自分が評価される」局面になった途端、何もできなくなる人がいる。特に新しい環境に変わる新年度は、ちょっとしたストレスが引き金となって、鬱や社会不安障害と呼ばれる症状にまで発展してしまうケースが多いから要注意だ。
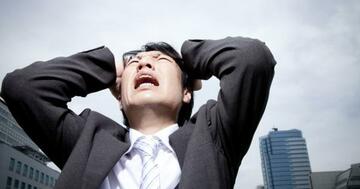
第26回
時代が転換するとき、必要とされる能力も、それを養う教育も変わる。2030年を想定した教育モデルとはどのようなものか。教育・入試改革に心血を注ぐ筆者が、フランスの専門家たちとの意見交換で考えたこととは。

第11回
日本をさらに発展させるために、統計研修所ができること
ベストセラー『統計学が最強の学問である』の西内啓氏が、統計学をテーマにゲストと対談するシリーズ連載。今回のゲストは日本の公的統計の要である、総務省統計研修所長の須江雅彦氏。日本が社会変化に十分適応できていないのは、人々のデータ分析力と理解力が不足していたからだと語ります。
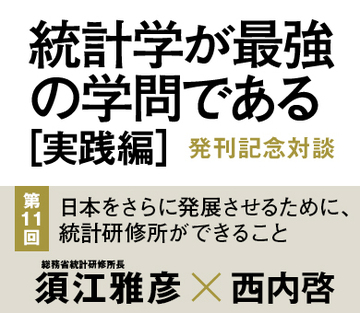
第10回
統計職員の意識を変えたベストセラー
ベストセラー『統計学が最強の学問である』の著者・西内啓氏が、統計学をテーマにさまざまなゲストと対談するシリーズ連載。今回のゲストは、日本の公的統計の要である、総務省統計研修所長の須江雅彦氏です。省庁としては初の試みであるオンラインコースを始めるにいたった背景などを伺います。
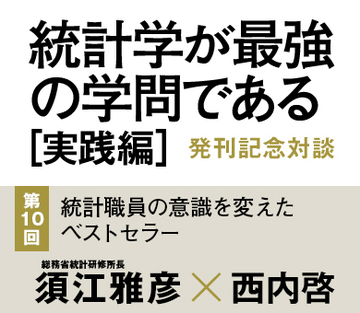
第1回
世間でも注目を集める「データアナリティクス」や「ビッグデータ」という概念は、営業・マーケティング・リスクマネジメントなど事業を取り巻くさまざまな領域での活用を急激に進めている。実は、こうした動きは人事の領域においても例外ではない。

第9回
「心理統計」の学者と「生物統計」の学者が対談したら
シリーズ38万部突破の『統計学が最強の学問である』の著者・西内啓氏が、さまざまなゲストと統計学をめぐる対談を繰り広げる連載企画。新たなゲストは、気鋭の統計学者・岡田謙介氏です。「生物統計」と「心理統計」、バックグランドが異なる2人の学者の希少な対談をお楽しみください。
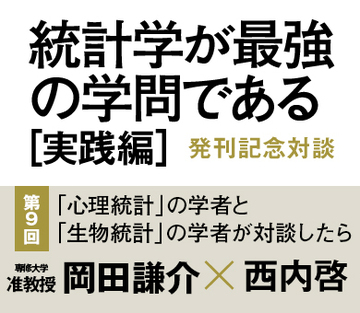
第8回
「頻度論」の学者と「ベイズ論」の学者が対談したら
シリーズ38万部突破の『統計学が最強の学問である』の著者・西内啓氏が、さまざまなゲストと統計学をめぐる対談を繰り広げる連載企画。新たなゲストは、気鋭の統計学者・岡田謙介氏です。統計学を二分する「頻度論」と「ベイズ論」。双方を得意とする学者による希少な対談をお楽しみください。
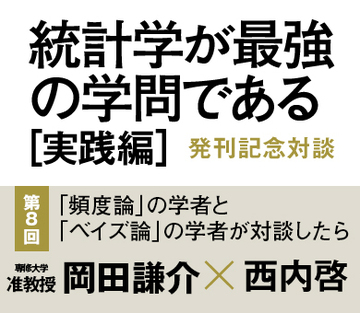
第1回
Seminar No.1 『進撃の巨人』はなぜ売れたのか?
いま、金融の専門家たちに絶賛され、静かに話題になりつつある本がある。ゴールドマン・サックスなどで長年活躍してきた松村嘉浩氏による、『なぜ今、私たちは未来をこれほど不安に感じるのか?』だ。人類が歴史的転換点にいることを「小説形式」で明らかにする同書の前半部分を一挙に公開する。
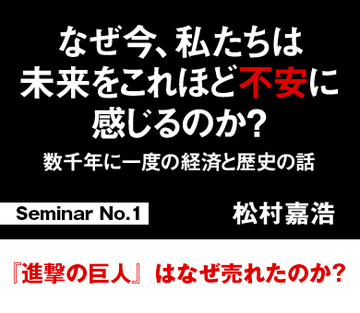
第15回
筆者がローカル小学校に子どもを通わせているというと、よく驚かれる。確かに両親ともに日本人で、子どもをローカルに通っている家庭はとても珍しいからだ。今回は、「子どもの学校選び」「教育」について、グローバルな視点から語ろう。

第6回
“思い込み”の政策が「ゆとり世代」のような不平等をつくり出す
シリーズ38万部を突破したベストセラー『統計学が最強の学問である』著者・西内啓氏が、さまざまなゲストと統計学をめぐる対談を繰り広げるシリーズ連載。今回のゲストは、教育分野における「エビデンスベースト」の重要性を説き、注目を浴びる気鋭の経済学者・中室牧子氏にお話を伺います。
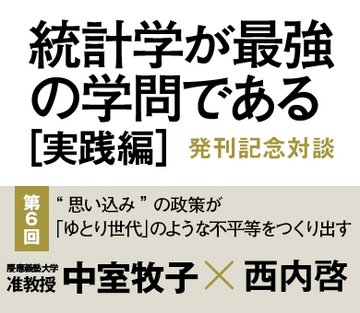
第100回
安倍政権が、小中学校の「道徳の時間」を「特別の教科:道徳」(仮称)に格上げして必修化する検討を加速させている。だがこの施策は、学校でのいじめ問題を深刻化させる懸念をはらんでいる。

第5回
「35人学級問題」をめぐる財務省と文科省のエビデンス無き議論
シリーズ38万部を突破したベストセラー『統計学が最強の学問である』著者・西内啓氏が、さまざまなゲストと統計学をめぐる対談を繰り広げるシリーズ連載。今回のゲストは、教育分野における「エビデンスベースト」の重要性を説き、注目を浴びる気鋭の経済学者・中室牧子氏にお話を伺います。
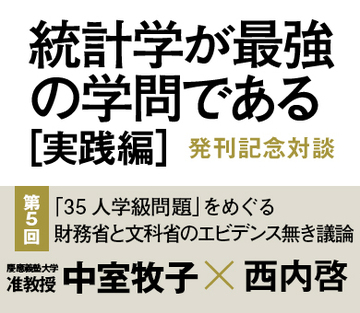
第1回
私がゴールドマン・サックスの面接試験に落ちた理由
そろそろ就職活動のシーズンを迎えます。数字に「超」きびしい外資系投資銀行の採用面接の裏側を教えます! 2月19日発売『ビジネスエリートの「これはすごい!」を集めた 外資系投資銀行のエクセル仕事術』の著者・熊野整による連載第1回。
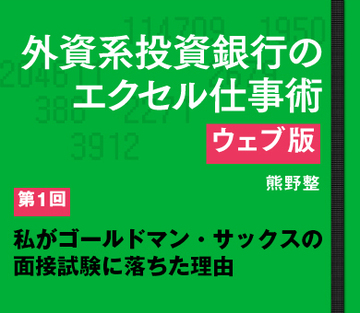
第6回
公務員試験の基礎知識(1)一次試験っていったい何やるの?
公務員講座など資格試験の専門家にして弁護士の豊泉裕隆が、公務員への就職・転職を目指す人のために、役立つ情報を提供する連載の第6回。今回からは、公務員試験合格に向けた具体的なアプローチ法を説明します。
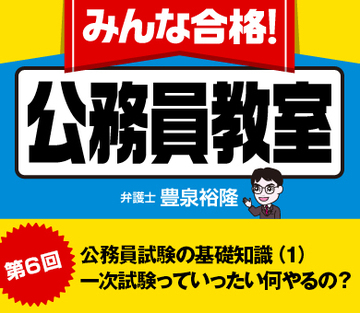
第365回
人生を左右する最も大事な時期は、大学進学者の場合、大学1、2年生の頃ではないか。もちろん仮説に過ぎないし、個人差もあろうが、筆者自身、当時の自分を振り返るにつけ、最近そう思うようになった。その理由を読者諸氏にお伝えしたい。
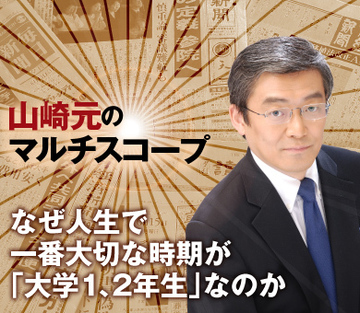
第6回
起業家になるには、海賊のようなスピリットと海軍特殊部隊が持つスキルの両方が必要だ〜MIT式スタートアップに学ぶ〜
毎年900もの新会社を生み出すMIT式スタートアップの教科書『ビジネス・クリエーション!』の著者・ビル・オーレット氏と新進気鋭の起業家たちをお迎えし、「起業家のためのゼロからうみだすビジネス・クリエーション術」セミナーを開催しました。その様子を3回に分けてお伝えします。
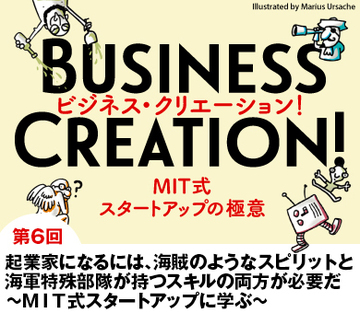
第5回
従来のWebマスターが取り組んできた企業ブランディングの整合性のための仕事と、商品データ分析基盤とを横断的に束ねることは難しい。そんななか、解決策として企業内に「CMOオフィス的な組織」を作る動きが出てきた。

第23回
国難ともいえる事態を前に、己が使命を自覚する人はいつの世もいます。ご承知の通り、今年のNHK大河ドラマ「花燃ゆ」は松陰の妹、杉文が主人公。松陰の生き様に、大きな影響を受けた私としては、今年の大河ドラマは興味深く拝見しています。
