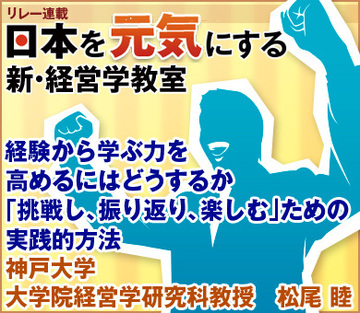松尾 睦
第5回
部下の強みを引き出す3つのアプローチ
いま人材育成の現場で最もよく使われているキーワードが「経験学習」だ。なぜ、マネジャーは部下の「経験から学ぶ力」を高めることが必要なのか。どうすれば部下の成長を効果的に支援できるのか。日本における経験学習研究の第一人者・松尾睦氏の最新刊『部下の強みを引き出す 経験学習リーダーシップ』より、内容の一部を公開する。

第4回
部下の中に眠っている「潜在的な強み」を探る方法
いま人材育成の現場で最もよく使われているキーワードが「経験学習」だ。なぜ、マネジャーは部下の「経験から学ぶ力」を高めることが必要なのか。どうすれば部下の成長を効果的に支援できるのか。日本における経験学習研究の第一人者・松尾睦氏の最新刊『部下の強みを引き出す 経験学習リーダーシップ』より、内容の一部を公開する。

第3回
「育て上手のマネジャー」と「平均的マネジャー」はどこが違うか?
いま人材育成の現場で最もよく使われているキーワードが「経験学習」だ。なぜ、マネジャーは部下の「経験から学ぶ力」を高めることが必要なのか。どうすれば部下の成長を効果的に支援できるのか。日本における経験学習研究の第一人者・松尾睦氏の最新刊『部下の強みを引き出す 経験学習リーダーシップ』より、内容の一部を公開する。

第2回
弱みに目を向けるだけでは、部下は成長できない
いま人材育成の現場で最もよく使われているキーワードが「経験学習」だ。なぜ、マネジャーは部下の「経験から学ぶ力」を高めることが必要なのか。どうすれば部下の成長を効果的に支援できるのか。日本における経験学習研究の第一人者・松尾睦氏の最新刊『部下の強みを引き出す 経験学習リーダーシップ』より、内容の一部を公開する。

第1回
育て上手のマネジャーは部下をどのように指導しているのか
いま人材育成の現場で最もよく使われているキーワードが「経験学習」だ。なぜ、マネジャーは部下の「経験から学ぶ力」を高めることが必要なのか。どうすれば部下の成長を効果的に支援できるのか。日本における経験学習研究の第一人者・松尾睦氏の最新刊『部下の強みを引き出す 経験学習リーダーシップ』より、内容の一部を公開する。

第13回
優れたマネジャーになる・育てる(第3回) マネジャーを育成する仕組み作り――北海道大学大学院教授 松尾 睦
シリーズ2回目では、いかにすれば良質な経験を積むことができるかについて解説した。3回目の本稿では、マネジャーが経験から学ぶことをいかに支援すべきかについて、具体的なマネジメントのあり方を考えたい。
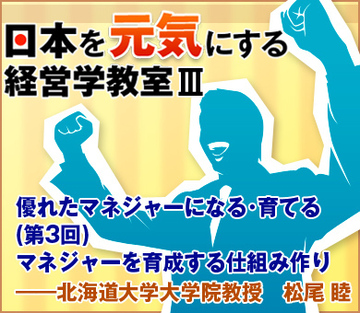
第12回
優れたマネジャーになる・育てる(第2回) 良質な経験の連鎖に入るカギは何か――北海道大学大学院教授 松尾 睦
1回目ではマネジャーが「連携」「変革」「育成」という3つの経験から、マネジャーとして必要な3つの能力を身につけていることを述べた。今回はいかにすれば「連携」「変革」「育成」の経験を積むことができるのかについて考える。
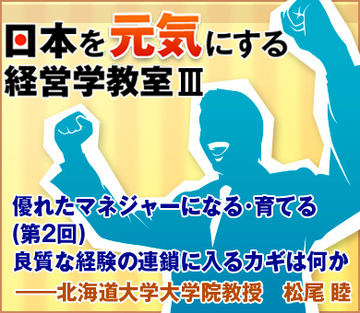
第11回
優れたマネジャーになる・育てる(第1回)「連携」「変革」「育成」の経験が人を伸ばす――北海道大学大学院教授 松尾 睦
バブル崩壊後、職場の空気は徐々に息苦しくなった。こうした状況の中で人が成長するメカニズムをしっかりと理解した上で、育成支援の仕組みを整備する必要がある。本稿では「優れたマネジャーをいかに育てるか」について考える。
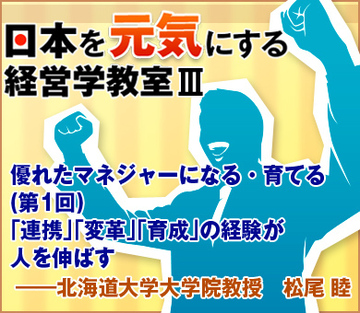
第48回
日本では、いまだ環境と地域社会との「共生」を図るサステナビリティ経営が、十分に展開されているとは言えない。日本企業が世界のサステナビリティの動きをリードするために、経営戦略の中に中長期的なサステナビリティの考えを導入し、実践するかを解説する。
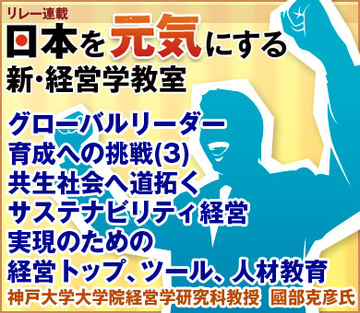
第45回
正直な取引で、「評判」の価値を高める、従業員と長期の雇用関係を結ぶなどの行為は、長期の利益に焦点を当てている。長期継続的関係のもとでは、協力関係が形成されやすい。では、どうやって協力関係を結ぶパートナーを選ぶのか。今回はそのことを考えてみよう。
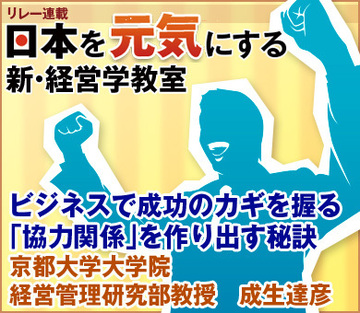
第44回
経験学習の重要性はわかったが、実際に、職場で経験学習を活性化させるためのツールがほしいという要望が強い。シリーズ最終回の本稿は、いままでの内容を踏まえて、人が育つ職場づくりための3つのツールについて紹介する。
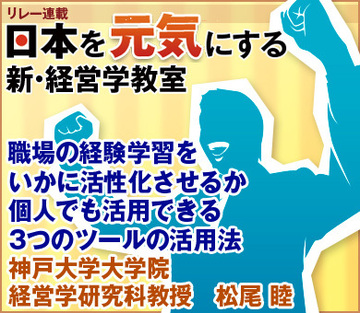
第43回
商人はよく「損して、得とれ」という。この言葉の意味は、最初は少し損したとしても、取引相手と長期にわたる協力関係を築き、そのもとで得る利益の方が、短期的な利益よりも大きいというものである。今回は、長期にわたる取引関係が、なぜ取引当事者間の協力を形成するか、についてゲームの理論を用いて検討する。
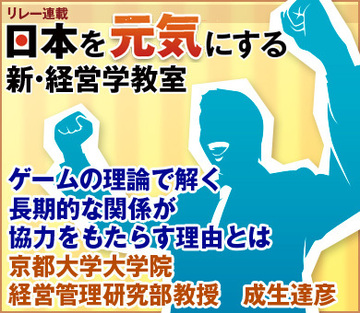
第42回
育て上手なマネジャーとそうでないマネジャーの指導方法には、どのような違いがあるのだろうか。若手の指導を任されている社員700名への質問紙調査データの分析をもとに、育て上手なマネジャーの特徴と、「育成力」を高める方法を提案する。
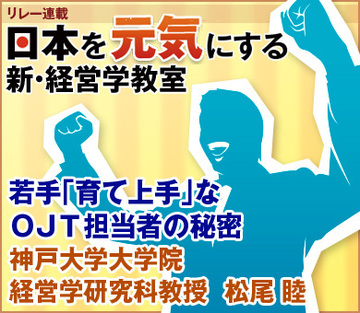
第41回
希少な資源を特定の用途に使うと他に振り向けることができなくなる。それによって諦めた利得が機会費用だ。この資源が生み出した価値と機会費用の差が利益。では、利益を生むにはどうしたらよいかを考えてみよう。
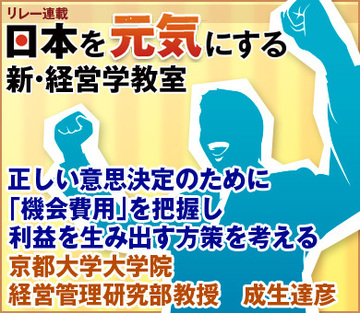
第40回
成長し続ける人は、挑戦し、振り返り、楽しみながら仕事をしている。これら3要素を自然な形で身につけ、高いレベルで維持させていくためにの原動力が、「思い」と「つながり」である。それは土から栄養を吸い上げる「根っこ」の役割を果たしている。
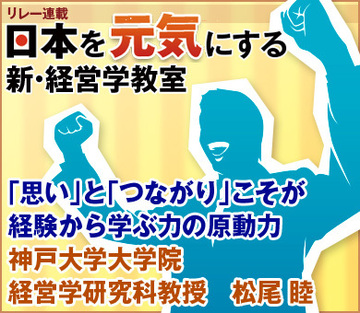
第39回
例年より2ヵ月遅れで就職活動が始まった。新卒者の採用に際しては、重要度が下がったとはいえ、応募者の「学歴」が、今でも採否を決める1つの要因となっている。なぜそうなのか、そのメカニズムを考えてみよう。
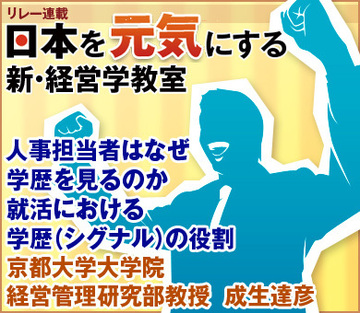
第38回
同じ経験をしても成長する人としない人がいる。その違いは、経験から学ぶ力の差によって生じる。第3回目の本稿では、学ぶ力を高めるために「挑戦する力」「振り返る力」「楽しむ力」に焦点を当てて、経験から学ぶための実践的方法について考えてみよう。