濱口桂一郎
60年前にもあった「ジョブ型雇用」議論、日本で見捨てられた当然すぎるワケ
近年、よく話題に上る、ジョブ型雇用。岸田文雄首相は、これまでのメンバーシップに基づく年功的な職能給からジョブ型の職務給に切り替えていくことで、労働生産性が上がり賃金も上がると主張しているが、実は60年前の池田勇人首相もまったく同じことを主張していたという。ジョブ型雇用が日本社会に浸透しないのは、なぜなのか?※本稿は、濱口桂一郎『賃金とは何か』(朝日新書)の一部を抜粋・編集したものです。

欧米の賃金なぜ30年で倍増?日本が「低賃金の国」に落ちぶれたのも納得だった
日本の賃金は上がっていないと、よく言われる。実際この30年で欧米では賃金が1.5倍から2.5倍程度まで上がっているのに対し、日本は横ばいのままだ。定期昇給のある日本で賃金が上がらず、定期昇給のない欧米で賃金が上がり続けているのは、一体なぜなのか?※本稿は、濱口桂一郎『賃金とは何か』(朝日新書)の一部を抜粋・編集したものです。
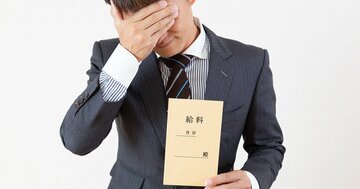
「ベースアップか定期昇給か」では日本の賃金問題が解決できない根本的な理由
基本給を底上げするベースアップ率が、今年の春闘では33年ぶりに5%を超える高水準となった。だが1970年代の高度成長期の20%や30%には遠く及ばない。その頃と比べれば、ベースアップ率より定期昇給率のほうが高い時期が続いているのが現実だ。これは経団連も求めていたことだが、それでも企業は苦しいという。そのわけは……。※本稿は、濱口桂一郎『賃金とは何か』(朝日新書)の一部を抜粋・編集したものです。

激務で死亡した「家政婦」が過労死認定されなかった理由、労働基準法がはらむ致命的欠陥
月換算で272時間のハード労働に従事し、直後に心筋梗塞で死亡した家政婦は、過労死認定されなかった。2022年に判決が下された過労死裁判で、東京地裁は、「家政婦は労働基準法や労災保険法の適用を受けない」と判断したが、家政婦の働き方の実態は、派遣労働者そのものだ。法による保護から家政婦がこぼれおちた歴史的経緯とは?本稿は、濱口桂一郎『家政婦の歴史』(文藝春秋)の一部を抜粋・編集したものです。
