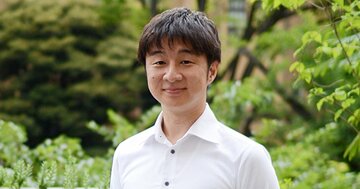西辻一真
農林水産省などによる新規就農の支援策は、就農希望者にとって追い風だが、農業を途中で諦めると多額の負債を抱えることになりかねない。新規就農者が新たに農業を始める際に、やるべき秘策や方向性について私の考えを述べる。

農林水産省は2022年度から新規就農者の支援制度を拡張する。就農から5年の間に最大で690万円を交付する現行制度を改め、初期投資に使うのを念頭に最大1000万円を補助する新制度を導入。支援金の増額は新規就農者にとって恩恵だが、農業経営を途中で諦めると多額の負債を抱えることになりかねない。本稿では、農業をビジネスとして成功させるのに必要な「農地」「投資額」「営農スタイル」の選び方をお伝えする。

ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が食料や肥料が高騰している。そうした中で、スーパーの「食品の値上げしません」という広告は本当に消費者の利益につながるのか。食料安全保障問題の解決策について私の考えを述べる。

ロシアがウクライナに軍事侵攻して2カ月が経過した。両国とも世界有数の小麦の輸出国だ。食料供給の多くを海外に依存している日本だが、今後の状況次第では、食料の輸入が困難になるかもしれない。食料安全保障のために、農業関係者がやるべき秘策や方向性について私の考えを述べる。

農家の後継者不足によって、作物が育てられなくなった土地が長期間放置される「耕作放棄問題」が深刻化している。また農水省によれば2020年度のカロリーベースの食料自給率は37%だった。米の大凶作に見舞われた1993年度や2018年度に並ぶ過去最低水準だといわれている。営農が困難な中山間地の耕作放棄地を再生するため、中山間地だからこそ可能になる収益性の高い作目・作付けをする、逆転の発想による「営農モデル」の確立について私の考えを述べる。

新型コロナウイルスの影響で「働き方」「人生設計」など自身の人生を見直し、さまざまな気持ちの変化が訪れた方も多いはずだ。その中で、都心の若者を中心に地方移住への関心が高まっている。しかし、日本の法律上、地方でいきなり農業をするにはさまざまな壁が存在する。持続可能な農業の将来像を示すとともに、問題解決の鍵となる「新規就農者向けのプログラム」や「都市部の農地活用」の可能性について私の考えを述べる。

地球温暖化や自然災害の増加、生産者の高齢化、地域コミュニティーの衰退、新型コロナウイルスの感染拡大など、日本の食料・農林水産業は多くの課題を抱えている。だが、農業はそうした問題の被害者であるばかりではない。地球に環境負荷を与える加害者の側面もあるのだ。本稿では持続可能な農業の将来像を示すとともに、多くの問題を解決する鍵となり得る農業界の「オープンイノベーション」や「協業」の可能性について私の考えを述べる。

絶えず利潤を求めてきた資本主義社会――。経済成長は、労働者からの搾取の上に成り立っている面があるが、自然からもさまざまな資源を奪っていることを見逃してはいけない。東日本大震災、コロナ禍といった危機が訪れる中で、人間に必要なこと、社会に必要なことを立ち止まって考えるべき時なのではないか。農業は、温室効果ガス排出量の4分の1を占めるなど環境負荷が大きいが、その半面、環境問題の解決の糸口となり得る。持続可能な社会にするには、エネルギー・輸送・農業のシステムを転換していくことが必要だ。人と自然のより良い関係をつくる農業の取り組みを追いながら、2050年の未来の農業の姿を大胆に予測する。