
小野圭司
高市政権は経済安全保障重視を掲げ「危機管理投資」を政策の柱にするが、高市首相の著書刊行と前後して、サプライチェーンの自国化や希少資源囲い込みなどの一国主義の流れやスタートアップ企業の技術の戦術や作戦などへの影響拡大という経済安保を巡る新たな変化が生じており、二つの変化への対応が課題だ。

オーストラリアが日本のフリゲート艦の採用を決め、日米間でも米艦艇の日本での補修体制の整備や関税合意では造船産業の対米投資が盛り込まれた。海洋進出を強める中国を意識した安全保障面での連携強化の一環だが、日本や衰退が目立つ米豪の造船産業にも新たな活路になる可能性がある。

トランプ政権との関税見直し交渉で防衛費増額などの日本の安全保障負担問題がくすぶるが、すでに日本の駐留米軍兵数や駐留経費負担は世界でトップだ。日米安保の負担は「金額として現れる」ものではなく、米艦艇の維持補修支援や防衛装備品の共同開発での貢献が重要になってきている。

ロシア経済は国防支出増による戦時経済と経済制裁を機にしたエネルギー・資源価格高騰の恩恵でグローバルサウス諸国への輸出を増やすなど予想以上の強さを維持してきた。停戦となれば反動不況やグローバルサウスへの“依存”が進む皮肉な状況に陥る可能性がある。

F2戦闘機の後継の次期戦闘機開発で日本と英国、イタリアがタッグを組む合弁会社設立が決まった。日本の防衛産業にとって米国以外の国との初めての共同開発だが、運用要求や巨額資金、開発・生産など分担は各国の利害・思惑がからむ。新たな経験やノウハウを得る機会だが手ごわいパートナーとのせめぎあいが待っている。

ウクライナ侵攻は膠着状態の消耗戦の様相だが、ロシアはプーチン大統領の檄の下で防衛産業は増産に躍起で最大メーカーのロステックは昨年1年で戦車は7倍、軽装車両は4.5倍の増産だ。ただ工作機械は7割を中国から輸入し半導体や砲弾も他国依存が強まるアキレス腱を抱える。

ウクライナ戦争の2年間、ロシアは欧米の制裁の抜け穴を活用しながら中国やインドとの連携強化で苦境を巧みに切り抜け“長期戦”への移行を進めた一方で、ウクライナは頼りの欧米からの物資支援の先細りが懸念される。GDP(国内総生産)規模やエネルギー自給などの経済力格差が今後、ロシアに有利に働く可能性が高い。

米国の先端半導体の禁輸を中国以外の21カ国にも広げる措置はそれらの国を経由した軍事転用の「横流し」を防ぐ狙いだ。ウクライナ戦争でもロシアへ同様の横流しが起きており、規制強化で半導体の戦略物資化がさらに強まる。
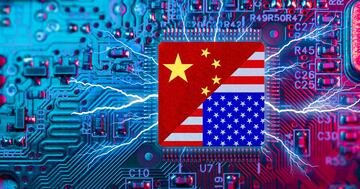
かつてない規模の経済制裁でもロシア経済は「打たれ強さ」が目立つ。エネルギーや農業の輸出競争力、豊富な金産出・保有に加え制裁に「抜け穴」があるからだ。戦争長期化でもプーチン体制が経済面から弱体化する可能性は高くないが、鍵を握るのはエネルギー価格の動向だ。
