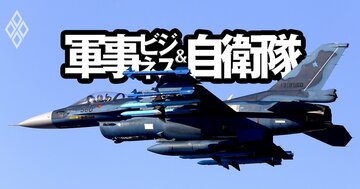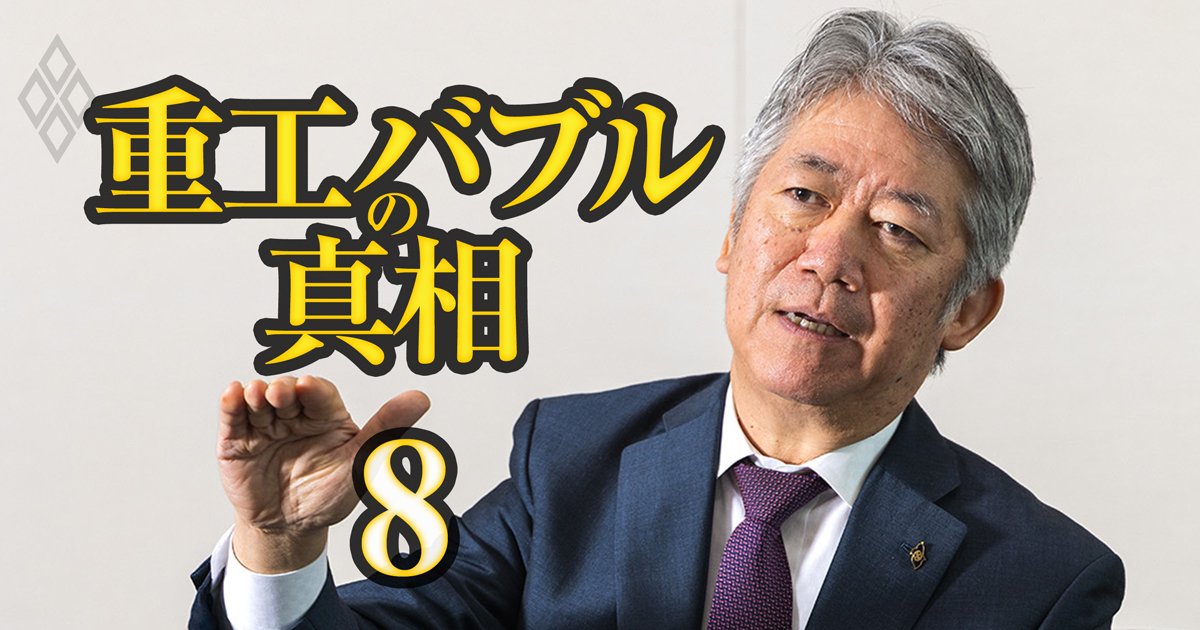 Photo by Yuji Nomura
Photo by Yuji Nomura
川崎重工業は重工各社の中で比較して、保持している事業が多い。幅広い事業を高い企業価値につなげる「コングロマリットプレミアム」をいかに実現させるのか。さらに化石燃料回帰の潮流の中、成長事業と位置付けてきた水素事業をどう展望するのか。特集『重工バブルの真相』の#8では橋本康彦社長に直撃した。(ダイヤモンド編集部 井口慎太郎)
「コングロマリットプレミアム」実現の戦略とは?
製品レベルの取捨選択は実施してきた
――2025年3月期は過去最高益でした。好業績は「需要に備えて帆を張っていた実力」か「事業環境による追い風」のどちらだと感じますか。
7割は実力で、3割は追い風でしょう。今まで取ってきた戦略が花開いたのです。これから防衛の追い風がだいぶ増えて業績に貢献し始めるでしょう。ただ、中国経済が落ち込み、米ボーイングの生産が戻り切っていません。
新型コロナウイルスの感染拡大前は、利益の6割は航空部門が稼いでいました。民間向けヘリコプター「BK117」は堅調ですが、一番稼いでいた米ボーイング向けの(航空機部品の)生産は、コロナ禍前に月産14機造っていたのが一時ゼロになりました。今ようやく7機まで戻りましたが、まだ半分です。精密機械とロボットは中国の景気に引っ張られるので、去年は非常に悪かったですが、今年は戻ってきています。
――フィジカルAI(人工知能)が注目されています。どんな展望を描いていますか。
ロボットメーカーには、技術面で(他社に対して)閉じた形を取る会社も多いですが、私はオープンに情報を開示し合って各社さんと協業しましょうというスタンスです。米マイクロソフトは神戸にAIのラボを構えていますが、われわれが誘致した経緯があります。米エヌビディア、NTTドコモビジネスとも協業し、ソニーグループとは遠隔操作のプラットフォームを提供する合弁会社を設立しています。
手術支援ロボットの「hinotori(ヒノトリ)」は今年度から黒字に転じる見込みです。手術件数も1万件を超えました。日本では医療従事者が1000万人を超え、製造業を上回る規模の労働市場となっていて、自動化・省人化の需要があります。一方で、われわれは価格だけで競争する単純作業の製品はあまり扱っていません。
――ロボットに用いる生成AI基盤モデルを複数企業で協業して開発する動きもあります。他社と組むことは考えていますか。
そこは極めて難しいでしょう。競争力の源泉になりますから。よく、フィジカルAIが普及するとロボットはコモディティ化するのではないかといいますが、そこまで簡単ではないですね。今、ロボットの指の動きが複雑になっています。人間で例えると、AIは大脳の大半、ロボットは小脳と神経、大脳の一部を構成しています。状況によって体を動かすとか、言ったことを動きに変換するとかは大脳だけでできるものではありません。ソフトとハードの技術がうまくつながることが重要です。
次ページでは、多くの事業を企業価値向上につなげる戦略や、世界で化石燃料への回帰が鮮明になる中での水素事業の展望を橋本社長に聞いた。