
阿部健児
「強い経済」実現を掲げる高市政権のもと「高市トレード」の活況にあった株式市場だが、総選挙で自民党が単独過半数を獲得するとなれば、日経平均株価は短期的に2000円程度の上昇が予想される。多党化継続や中道政権となれば成長戦略がみえないことや財政規律弛緩を嫌って、株価は下落で反応すると見込まれる。

高市政権の下、2026年の株式市場は年度末までに日経平均株価が「6万円」、TOPIX(東証株価指数)は「4000pt」到達が見込まれる。積極財政による巨額政府債務膨張懸念からの金利上昇や円高・円安両面での為替変動、政権基盤の弱さなどのリスクはあるが、供給力強化を目指した官民の投資主導の成長が実現する期待が株式市場では強い。

FRBが9月FOMCで利下げを再開、政策金利を2027年末には3%近辺まで下げられる見通しで米長期金利も一段と低下する。日本株もP/E(株価収益率)の上昇やAI・半導体関連株の好調もあり26年6月末のTOPIXは3500pt、日経平均株価は4万7000円を上回る可能性がある。

1~3月期の主要企業約200社の決算などから2025年、26年度の業績予想をすると、トランプ関税で5~10%の減益影響が見込まれるが、26年度は米国の中間選挙があり各国中央銀行の緩和政策が続くほか、AI、半導体、IT投資の堅調で前年度比で10.3%増の増益となり、過去最高益を更新する可能性が高い。
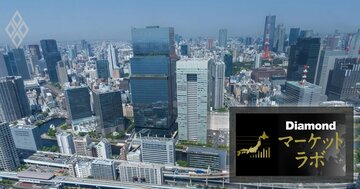
関税引き上げなどのトランプ政策の動向が各国経済の最大の不透明要因だが、16年ぶりの高水準となった日本の長期金利は今後、「1.1~1.9%」のボックス圏で推移し、株式市場は米経済の景気後退回避でTOPIXは2025年度末には3000ptを超えるメインシナリオが予想される。

日米株式市場の最大のリスクはトランプ第2期政権の政策の不確実性だが、減税や規制緩和のプラス効果と関税引き上げや移民規制のマイナス効果は相殺されると考えられる。米経済の軟着陸見通しや企業収益の好調を背景に、日米株価は「上昇傾向継続」がメインシナリオだ。

FRBが4年半ぶりの利下げに踏み出した。政策金利を通常より大きな0.5%引き下げで開始したことで米景気は軟着陸しトータルの利下げ幅は大きなものにならない可能性が高い。投資家のセンチメント改善などで日米株式市場は2025年にかけて日経平均株価は4万円台となり、S&P500は6000ptを上回る公算が大きい。
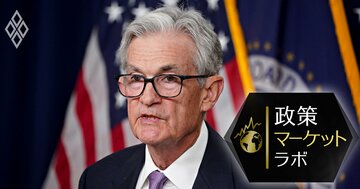
日本銀行は7月から国債買い入れ減額を始め、日本の長期金利の妥当レンジは「1.0~1.75%」から徐々に上方シフトする。今後、米長期金利低下の影響はあってもいずれ1%を上回る水準が定着する見通しだが、実質金利はマイナス0%台後半にとどまる。株価上昇と両立する展開が予想される。

異次元緩和の終了後も東京株式市場の活況は続く見通しだが、2023年度の相場をけん引してきたバリュー株(割安株)は米国の長期金利にピーク感が出たことからアウトパフォーム基調は一段落する一方で、海外投資家による日本株買いは続き、金融や半導体などの大型株の物色が続く。

#3
史上最高値を更新した日経平均株価の急騰をけん引する主役は外国人投資家だ。米経済の軟着陸見通しや日本経済のゼロインフレ脱却、日本企業の経営改善への期待などから今後も日本株投資は続き、2024年度末までに日経平均株価は4万3000円を上回ると予想する。

米経済は2023年、インフレ率が大幅低下する一方、失業率は低位で安定する「曇りなきディスインフレ」で長期金利も低下した。この流れの下で24年の日本株は債券から資金シフトやマイナス金利解除予想、日本企業の収益改善も加わって史上最高値を更新する可能性が高い。
