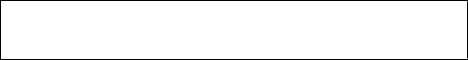数年前に、会社は誰のものなのか、という議論が盛り上がった。これは、「誰のもの」という言葉の意味を正確に定義しないと意味がない議論だった。とはいえ、株式会社の場合、会社の債務を差し引いた財産の最終的な所有者、会社の方針の最終的な決定者という意味では「株式会社は、株主のものだ」と見るのが自然だろう。
しかし、企業買収に対する心情的な抵抗感などもあって、会社は、株主に加えて、経営者、社員、債権者(融資している銀行や社債の保有者など)、さらには顧客などの広い意味での利害関係者全体のものだ(「ステークホルダー」という言葉がよく登場した)といわれてきた。
だが、利害関係者が自分によかれと思って影響力を行使するのは当然のことなので、そのさまざまなありさまを「会社は誰のものか」という問いでまとめるのは、あまり利口なアプローチではないと、筆者は当時も今も思っている。実質的に「誰のもの」なのかは、時々のルールや、関係個人の事情、ビジネス環境などで変化する。
企業によって事情は異なるが、日本の会社に限らず、会社の過半数の株式を買収しても、経営者を代えることくらいはできても、株主、あるいは乗り込んできた新しい経営者が会社をコントロールすることが難しい場合がある。株式の持ち合いなどによって、実質的に株主が会社の経営方針を決められないケースもあるし、既存の社員の協力が得られないと会社が機能しないこともある。伝統的な日本の大企業の多くにあって(同族企業をおおむね除く)、「社長」は、株主に選ばれた「会社の長」であるより、社員共同体の中で選ばれる「社員の長」の色彩が強い。