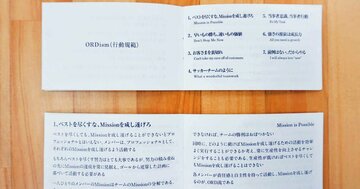写真はイメージです Photo:Ariel Skelley/gettyimages
写真はイメージです Photo:Ariel Skelley/gettyimages
京都先端科学大学教授/一橋ビジネススクール客員教授の名和高司氏が、このたび『シン日本流経営』(ダイヤモンド社)を上梓した。日本企業が自社の強みを「再編集」し、22世紀まで必要とされる企業に「進化」する方法を説いた渾身の書である。本記事では、その内容を一部抜粋・編集してお届けする。日本のビジネスパーソンは米国企業に憧れを抱きがちだ。米国流の経営モデルこそが「世界標準」だと高評価し、踏襲すれば成功できると考える経営者も多い。だが名和教授は、こうした風潮に冷ややかな目線を向ける。
本質を理解せずに
「アメリカ化」に憧れるべからず
海洋国家・日本は、「海外」に対してどのような価値を提供すべきか。簡単に言ってしまえば、それは日本の異質性と共感性である。海外の人々が同質性しか感じなければ、日本に来ることにも、日本を受け入れることにも、とりたてて価値を感じないはずだ。日本の独自性こそが価値なのである。
日本のビジネス用語に「ガラパゴス化」という言葉がある。その意味をAIに聞いてみると、早速次のような答えが返ってきた。
・日本の携帯電話市場が高度な機能を持つ独自の端末を発展させた一方で、海外では普及しなかったことから名付けられた。
なかなか要点をついた答えである。しかし、世界遺産ガラパゴス諸島が世界に類を見ない生物や生態系の宝庫であるように、日本もその異質性を価値に転換できる可能性がある。
珍獣やサブカルだけでなく、独自技術や製品も、ガラパゴス級に突き抜けた価値を提供できれば、世界に広く受け入れられるはずだ。たとえば任天堂は、ファミコン、DS、Wii、Switchなど、独自の世界を徹底的に追求することによって、国際的なデファクト化に成功している。
ただし「独りよがり」ではいけない。その独自性が、海外でも共感を持って受け入れられる必要がある。共感の導線やストーリーをいかに仕掛けるかが、カギとなる。
「モノ」であれば、それ自体が価値を伝える媒体となりうる。ソニーの家電製品や、ホンダのバイクはその典型例である。しかし、無形の「コト」の価値は、簡単には伝わらない。
茶の湯であれば岡倉天心、そして禅は鈴木大拙が、それぞれの価値を海外に広めることに大きく貢献した。どちらもすばらしい英語で、日本文化の奥義を説いたところが大きい。
 PHOTO (C) MOTOKAZU SATO
PHOTO (C) MOTOKAZU SATO京都先端科学大学 教授|一橋ビジネススクール 客員教授
名和高司 氏
東京大学法学部卒、ハーバード・ビジネス・スクール修士(ベーカー・スカラー授与)。三菱商事を経て、マッキンゼー・アンド・カンパニーにてディレクターとして約20年間、コンサルティングに従事。2010年より一橋ビジネススクール客員教授、2021年より京都先端科学大学教授。ファーストリテイリング、味の素、デンソー、SOMPOホールディングスなどの社外取締役、および朝日新聞社の社外監査役を歴任。企業および経営者のシニアアドバイザーも務める。 2025年2月に『シン日本流経営』(ダイヤモンド社)を上梓した。
しかし今日の日本のビジネスパーソンの中に、日本のコトの価値を、海外に分かりやすく伝えられる人は残念ながら稀である。いくら英語が堪能であっても、いや、そうであればあるほど、海外ズレして、日本の本質を理解していない「グローバル」人財が量産されてしまっているからではないだろうか。
さて経営の世界では、いまもなお、グローバル化の必要性が喧伝されている。しかし、ここまで述べてきた異質性と共感性という本質を理解せずに、単なるアメリカ化を、しかも数周遅れで唱えている論調がいまだに絶えない。特に経営を知らない学者や官僚、そして「学習モード」から抜け出せない経営者に多く見られる光景である。