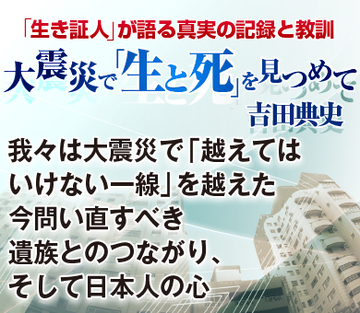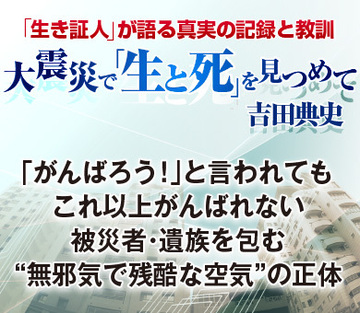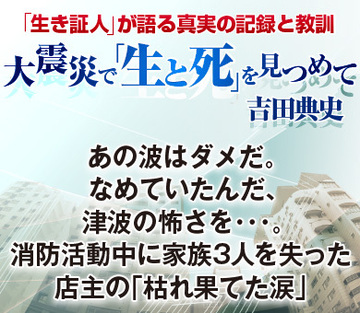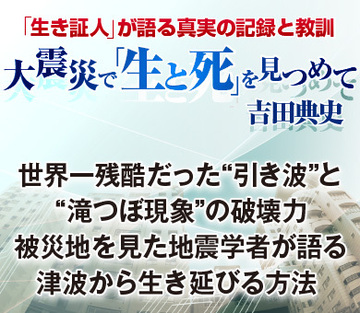3月11日の震災後、東京都の「心のケアチーム」の一員として被災地に赴き、現地の自治体職員らと被災者の心のケアに取り組んだ精神科医がいる。
今回は、その医師に取材を試みることで、震災の遺族が精神的な苦しみを抱き続ける背景に迫る。
月日が経っても苦しむ遺族の現状
心の傷を癒すべく奮闘するケアチーム
 (上)精神科医の飛鳥井 望氏。(下)財団法人東京都医学総合研究所(東京・世田谷区)
(上)精神科医の飛鳥井 望氏。(下)財団法人東京都医学総合研究所(東京・世田谷区)
「ただ立ち尽くすのみで、言葉が出てこなかった……」
精神科医で、東京都医学総合研究所の副所長を務める飛鳥井(あすかい)望氏は5月初め、岩手県の陸前高田市を訪れたときの印象を語った。
陸前高田市は、震災前の人口が2万4000人だったが、震災で死者・行方不明者が2000人を超えた。人口の1割を超える人が亡くなり、その割合は被災地の中でも高い。
「この地域ではとりわけ、ご遺族の心の変化が大きな問題となっており、自ずと心のケアが必要になる」
私は、3月11日の震災で家族を失った遺族の現在(取材は10月下旬)の心の状態を尋ねた。飛鳥井氏はこう答える。
「今回の震災に限らないが、家族が亡くなり、半年から1年が過ぎるくらいまでが、ご遺族の心理を捉える上で1つの分岐点になる。ほとんどの方が、その期間に精神的に苦しみながらも、悲嘆の状況から出口を見つけ出す」