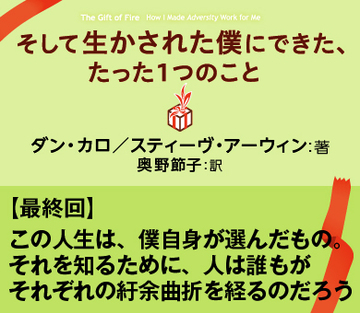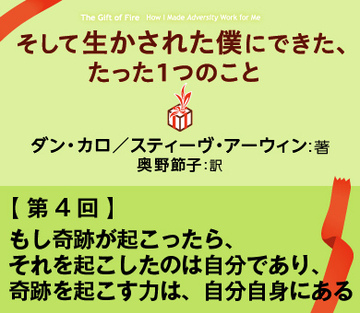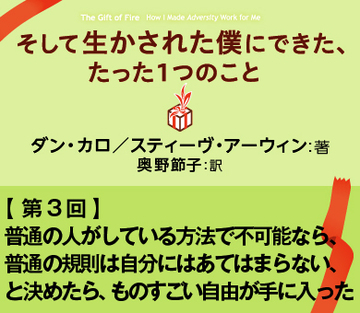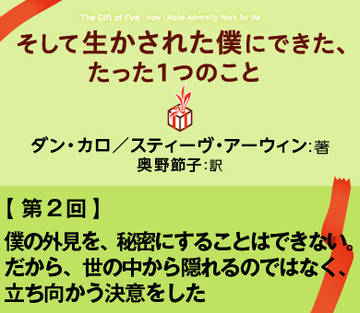僕に配られた「運命のカード」
1982年3月17日の朝は、その日が聖パトリック祭であること以外、僕たち家族の人生が永遠に変わってしまうなどと思わせるものは、何1つありませんでした。
その事件は、突然僕たちに降りかかり、人生は運命のカードを配ったのです。
ルイジアナ州南東部にしては、湿気がまったくなく、すっきり晴れあがった美しい朝だったそうです。その日は水曜日で、わが家はいつも通りに始まりました。
両親は早く起きて、朝のお祈りをし、7時半には朝食を終えました。
二人の兄は、身じたくをすませ、スクールバスに乗り遅れないよう家を飛び出していきました。母は僕を抱いたまま外へ出て、仕事へ出かける父に「行ってらっしゃい」のキスをしました。
父の車が出ていくと、母は庭の芝生がのびすぎていることに気づいたのです。
そして、芝刈りをすることにしました。
母は僕を、柵に囲まれたテラスの内側に下ろし、プールから離しておこうと思いました。好奇心いっぱいで活発な僕に、プールは危険このうえない場所だったからです。
しっかり見張っていられるように、母は作業をするところから1メートルほどの場所に僕を置きました。それから車庫へ向かうと、隅にあったガソリン缶から芝刈り機にガソリンを入れてきて、芝刈りを始めました。
母が芝刈り機を反対側へ向けたほんのわずかな瞬間、僕は母の視界からはずれました。
それは10秒にも満たない時間でしたが、僕には十分でした。
すばしこかった僕は、車庫の横のドアからすっと入り込み、お気に入りの小さな四輪車を探そうとしたのです。
車庫に入ったときだったのか、あるいは棚からおもちゃを引きずり降ろしたときだったのかは定かではありませんが、気づいたときには手遅れでした。
母が使ったばかりのガソリン缶をひっくり返してしまい、コンクリートの床には流れ出たガソリンが広がっていました。
目に見えないガスが床から立ちのぼり、数秒もせずに、隅にあった給湯装置の口火まで達して、車庫全体が燃え盛る地獄絵と化したのです。
僕はその真ん中に立っていました。摂氏千度以上に達した空気にあぶられ、またたく間に僕の皮膚は火ぶくれになり、骨にまで達するほど焼けただれてしまいました。
その火事は、ほんの一瞬でした。
でも、僕の人生に、決して消えることのない傷跡を残したのです。