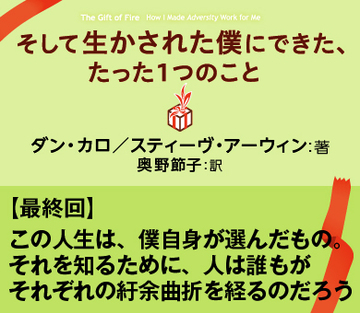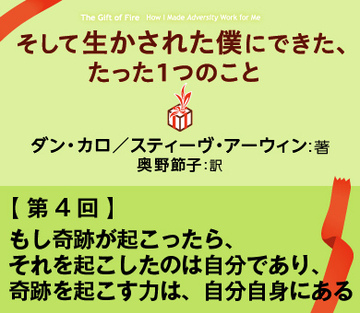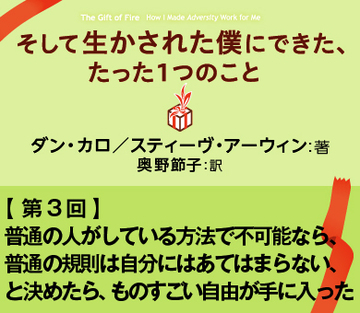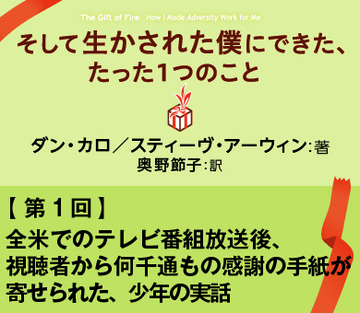長い病院での日々、心ない人たちの言動に傷つきながら学んだことは、「大切なのは外側でどう見えるかではなく、内側でどんな人間であるか」。ついに鏡を見つけ、自分の顔を見ることになった少年が抱いたのは、意外な感想と決意だった。感動の軌跡を追った連載、第2回。
昏睡状態の僕をよみがえらせたもの
何度もの皮膚移植を繰り返し、空気感染を防ぐためのプラスチックテントの中で、死んだように横たわっている僕。
そんな僕のベッドのそばに、母は毎日、朝早くから面会時間が終わるまで座り、包帯の上から僕の顔をなで、子守歌を歌い、童話を読んでくれたそうです。
そんなある週末のこと。
父が、映画『ロッキー2』のテーマ曲が入ったカセットテープを持ってきてくれました。父は、僕がこの映画を大好きなのを知っていたのです。
父がカセットをかけ、小さなスピーカーからあのテーマ曲が流れだした瞬間、ほとんど昏睡状態だった僕の体が、ピクピクと動き始めたのです。
数分もしないうちに、包帯を巻いた足が、音楽に合わせてトントンと拍子をとっていました。
僕は、何とかして起き上がり、プラスチックの覆いから這い出て病棟の中を走り出そうと闘っていたのです。
僕のこの反応を見て、両親は大喜びしました。
プラスチックテントと包帯の下で、愛するわが子が、今も生きていて、足を蹴っているのを目撃したのですから。
それは、回復に向けたとても長い道のりに、ためらいがちな最初の一歩を踏み出した瞬間でした。
 手術の数日後、ボストンのシュライナーズ小児病院で5歳の誕生日を祝う
手術の数日後、ボストンのシュライナーズ小児病院で5歳の誕生日を祝う
2週間後、父は子ども用のボクシンググローブを持ってボストンへ戻ってきました。
ちょうどその時、僕は新たに移植した皮膚の拒絶反応から回復しつつあったのですが、医師から許可をもらった父がグローブのひもを締めるやいなや、僕は医師や看護師を相手にジャブを繰り出したのです。
この2ヵ月後、僕はルイジアナの家に帰れるほどの回復をとげたのです。
それは、事故からちょうど4ヵ月後のことでした。