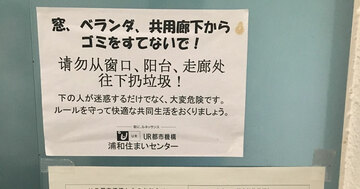『多文化主義のゆくえ 国際化をめぐる苦闘』
『多文化主義のゆくえ 国際化をめぐる苦闘』ウィル・キムリッカ著
(法政大学出版局/4800円)
移民などの民族的マイノリティの権利や文化をホスト国で認める「多文化主義」に近年、逆風が吹いている。2010年代初めにドイツのメルケル、英国のキャメロン両首相がともに「多文化主義の失敗」を口にし、移民統合の在り方に再考を促した。最近では、難民流入もあり、多文化主義を批判するポピュリスト政党の支持も伸びる。
本書が挑むのは、著者が言う「正真正銘の地雷原」に突入し、劣勢に立つ多文化主義の中でも「リベラル多文化主義」、すなわち民族的マイノリティの地位や文化の違いを公式に認め、公的な制度の主体とする政策を擁護することだ。その対象となってきたのは、「移民」だけではない。歴史的には、インディアンやアボリジニなど先住民への権利保障、政治的にはカナダのケベック州や英国から独立を目指すスコットランドのような地域文化の要求なども含む。
こうした多文化主義の複層的な側面だけでなく、途上国での多文化主義を含む地域的な多様性を網羅するのも特徴だ。国家分割の歴史を持つ東欧諸国などでは、マイノリティ問題が安全保障と分かち難く存在すること、植民地の経験を持つ途上国では、民族的マイノリティと先住民の線引きが重複することなどが詳述される。
夥しい数の事例からは、マイノリティの処遇は教育制度や言語政策に留(とど)まらず、経済的な再分配など複数領域に複雑に広がっていることに気付かされる。時間と空間の横断的な分析の中で強調されるのは、国際連合や専門機関、地域機構やNGOなど、国際的なネットワークにより、リベラル多文化主義が推し進められている点だ。
例えば、戦後、西ドイツの再軍備が認められた際、デンマークとマイノリティに関する互恵待遇協定が結ばれたし、アフリカ諸国では、地域的な民族紛争の解決プロセスに組み込まれたりするなど、多文化主義は国内的、国際的な次元にまたがって展開されている。
これは、多文化主義を通じて、国民国家での既存社会との境界線が組み直されることを意味する。その国が民主的であれば、民族的マイノリティも、集団総体として民主的になる好循環が生まれる。
先進国での移民の数は、戦後期で過去最高の水準に達し、途上国の人口移動もかつてないほどの勢いにある。「一国家・一民族・一言語」という前提条件が崩れているのは、どの国でも同じだ。多文化主義の理論的枠組みと豊富な事例紹介は、「労働力」や「移民」という言葉以外に異なる者への想像力を未(いま)だ持ち得ていない私たちにとって、大きな刺激となるだろう。
(選・評/北海道大学大学院法学研究科教授 吉田 徹)