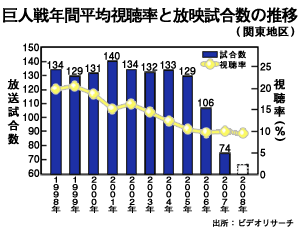阪神タイガースが18年ぶりのセ・リーグ優勝を決めた。大阪の街は今、歓喜の渦の中にいる。もはや大阪の景気を回復させるのは、万博開催ではなく、阪神の日本シリーズ制覇ではないかと言っても過言ではないくらいだ。
阪神タイガースとその熱狂的なファン、そしてホームタウンである大阪という都市との関係を、アメリカ人はどう見ているのだろうか? アメリカの名門、イェール大学のウィリアム・W・ケリー教授がフィールドワークを重ねて書き上げた『虎とバット 阪神タイガースの社会人類学』から、一部を抜粋して見てみたい。(初出:2019年6月23日)

猛虎応援団のその先
甲子園のライトスタンドの住人は、タイガースのファン文化の中心だが、チームを応援する人間はスタジアムの外、それこそ関西の隅々からその先にまで広がっていて、その様子はボストンのフェンウェイ・パークを首都に、ニューイングランド全域に住人が散らばる“レッドソックス・ネイション”によく似ている。もちろん、中心たる外野席の応援団は特別だ。人数で勝る内野席は、音量も統一感も外野にはかなわない。そしてもちろん、いつもチームを追いかけるファンでも、スタジアムを訪れるのはほんの一部でしかない。ほとんどの自称ファンは甲子園をめったに訪れず、テレビやラジオ、あるいは出勤や帰宅の合間に読む新聞など、それぞれの手段でチームを追う。
メディア(特にテレビとスポーツ紙)の登場によって、観客の行動と在り方との乖離が生じ、前者はスペクタクルにつながるが、後者は間接的な傍観者しか生み出さないとする説は数多い。特にテレビは“地元”のアイデンティティーを崩壊させ、ファンが応援するチームを「ころころ変える」要因をつくったと批判される。万能に近いメディアの登場で、ファン文化が大きく損なわれたという主張だ。
わたしとしては、その意見には賛同しかねる。確かに、仕事から帰った夜七時半、居間で冷たいビールを片手にごろごろしながらテレビでタイガースを観る一家の主人、あるいは満員電車に揺られながら、通勤途中に好きなスポーツ紙で応援しているチームの前夜の試合のニュースを読みふける会社員のファン体験は、甲子園に毎日駆けつける浪虎会のメンバーの体験とはまるで別ものだ。しかしそれは、テレビや紙媒体を通じた体験が、生観戦の濃密で、直接的で、自発的な体験に劣るという意味ではなく、メディアを通じた体験は性質が異なるという意味に近い。
アンドルー・ペインターが日本のバラエティー番組について述べたように、テレビ観戦からも、生観戦に似た「準濃密な」体験は生まれる。テレビなら投手の真うしろから試合を観られるし、複数のカメラアングルやリプレイ映像も楽しめる。解説者のコメントも独り占めできる。スポーツ紙のドラマティックな記事なら、色鮮やかな写真、印象的なかたちと大きさの文字、各種エピソード、スタッツ、サイドストーリーなど、ニュースというよりは漫画に近い体験が味わえる。