出版社とバーを営んでいた元敏腕経営者M
今でこそ想像すらつかないが、Mはかつて会社を経営していた。居住地の近くにある商店街に3階建てのビルを丸ごと借り上げ、1階と2階部分では「バー」を、3階では本業である「出版社」を営業していた。
彼が経営するバーは、毎晩店の外に人があふれるほど大盛況。一方、マルチ商法まがいのビジネスに手を染めていた会社を取引先として、書籍の製作・販売を請け負っていた出版社の経営は対照的だ。
取引先の社長と良好な関係を築いていたときは順調だった。発注された部数を印刷すればすべて買い取ってもらえる、「間違いない商売」ができていたからだ。しかし、相手の経営が傾いてくると、「これまでお前の会社を支えてやっただろ。その分を返せ!」と次第にムチャな要求をされるようになり、金銭トラブルへと発展していった。
取引先を失って出版社経営の雲行きが怪しくなるなか、当初はその赤字をバーの売上で補っていたものの、それすらも困難な事態へと陥ってバー兼事務所の家賃を数ヵ月滞納した挙句、昨年11月末に会社をたたむこととなった。
Mが真っ当な経営者としての資質を備えていたのかはわからない。ただ、若かりし頃に尋常ではない羽振りの良さを見せていたのは事実である。
バブル経済の先導者は「即死」もできない
大学を卒業して職を転々としながら過ごした20代を経て、Mが腰を据えたのは出版業界だった。時は80年代半ばから90年代初頭のバブル最盛期。Mの仕事はといえば、バブルに踊る日本経済を一層煽り立てることであった。
雑誌や夕刊紙の編集者への営業で執筆枠が確保できると、当時話題になっていた店や流行の文化を紹介する。実際の取材や執筆を自身で行なうことはなく、下請けのライターに指示を出しさえすればよかった。
バブル絶頂期のマスコミ業界の景気の良さは「今から考えれば狂っていた」と、当時を知る者たちは語る。上司から「毎週20万も経費の枠を取ってやってるのに、何で使いきれないんだ!」「新宿や渋谷なんか行くな!飲むならまず、銀座に行け」と怒られたエピソードなどは決して珍しい話ではないという。
執筆を依頼してくれた雑誌・新聞社から原稿料をもらう一方で、記事で紹介した店側からも「ぜひまた。今度は別の媒体でもうちの記事を」と、円高の今であれば海外旅行にも行けてしまうほどの「お車代」が手渡されることも日常茶飯事だった。
Mは「バブル消費煽り」の最先端に虚ろな情報生産工場を建設し、それはそれで勤勉に、落ちてくるカネを必死にかき集めていた。毎日のように記事の掲載枠を確保するための接待に勤しみ、人柄の良さを最大限利用して確保した枠をひたすら埋めていった。
そんな時代が続くはずもなく、文字通り、バブル経済は泡のようにはじけてしまった。しかし、バブルがはじけたからと言って、それがMにとっての「即死」を意味するわけではなかった。散り散りになりながらも残っている泡をかき集め続けることで、「真綿で首をしめられる」ように、破綻へのカウントダウンがジリジリと進む20年が始まったのだった。
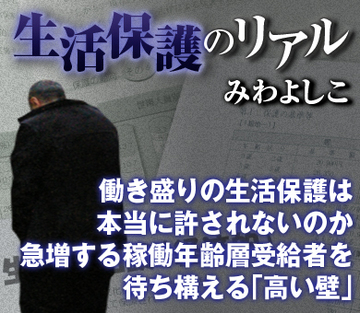
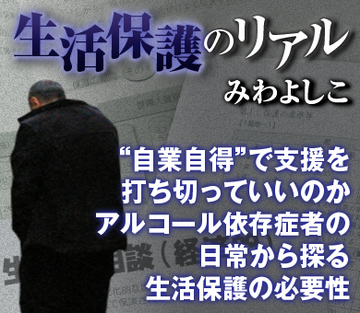
![[北欧現地インタビュー:お金と仕事編]バブルを生きてきた日本人は、「満足の閾値」がムダに上がってしまっている](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/5/6/360wm/img_56196426006247abd358bd0d167e16d1130789.jpg)
